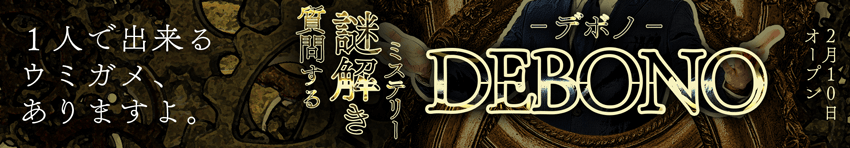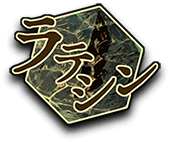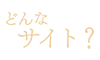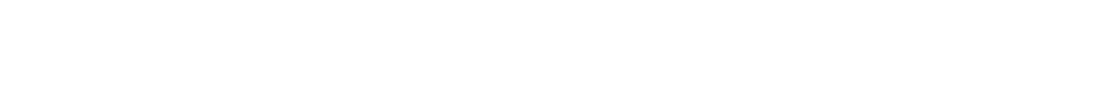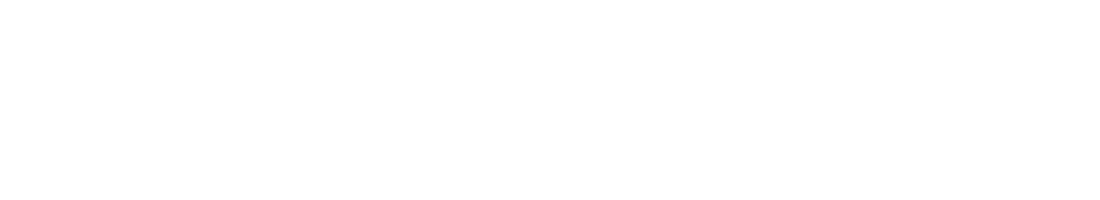「へっぽこスナイパーは食べ物を使う」「14ブックマーク」
太郎はへっぽこスナイパーだ。
太郎は、近頃、自ら直接手を下さずとも、ターゲットを始末するという方法にあこがれている。
そんなわけでターゲットに料理を提供してた太郎。
料理を食べさせればターゲットを死に至らしめると思ったからだ。
しかし、太郎の作戦はうまくいかなかった。
いったいどういうことだろう?
太郎は、近頃、自ら直接手を下さずとも、ターゲットを始末するという方法にあこがれている。
そんなわけでターゲットに料理を提供してた太郎。
料理を食べさせればターゲットを死に至らしめると思ったからだ。
しかし、太郎の作戦はうまくいかなかった。
いったいどういうことだろう?
15年07月27日 22:52
【ウミガメのスープ】 [3000才]
【ウミガメのスープ】 [3000才]
解説を見る
太郎は、昔、海難事故を起こしたというターゲットに、
ウミガメのスープを食べさせれば自殺するのではないかと考えて出してみた。
別に自殺しなかった。
もぐもぐ食べてた。
そういうこともある。
いっけね。
ウミガメのスープを食べさせれば自殺するのではないかと考えて出してみた。
別に自殺しなかった。
もぐもぐ食べてた。
そういうこともある。
いっけね。
「【言えない理由の先入観】」「14ブックマーク」
私の指導のもと、水平思考問題『ウミガメのスープ』出題練習をしているあなた。
しかしあなたは問題を出している途中で口をつぐんでしまった。
一体なぜでしょう?
しかしあなたは問題を出している途中で口をつぐんでしまった。
一体なぜでしょう?
16年09月07日 23:07
【新・形式】 [のりっこ。]
【新・形式】 [のりっこ。]
解説を見る
なぜあなたが口をつぐんでしまったのか?
“ その理由を考えてしまう事こそ、
真っ先に植え付けられた大きな先入観。 ”
ではなぜ、大抵の人が “ 口をつぐんだ理由を考えてしまう ” のか?
それはまさに、当問題の文末の仕業に他ならない。
“ 一体なぜでしょう? ”
私は、そもそも “ 理由など訊いていません。 ”
当問題文の通りの指導者として、
ウミガメのスープ出題の途中で口をつぐんでしまったあなたに
最後の問い掛け台詞を確認がてら教えたまでです。
当然、『でしょう?』のイントネーションにはくれぐれもご注意ください。
“ その理由を考えてしまう事こそ、
真っ先に植え付けられた大きな先入観。 ”
ではなぜ、大抵の人が “ 口をつぐんだ理由を考えてしまう ” のか?
それはまさに、当問題の文末の仕業に他ならない。
“ 一体なぜでしょう? ”
私は、そもそも “ 理由など訊いていません。 ”
当問題文の通りの指導者として、
ウミガメのスープ出題の途中で口をつぐんでしまったあなたに
最後の問い掛け台詞を確認がてら教えたまでです。
当然、『でしょう?』のイントネーションにはくれぐれもご注意ください。
「おもちゃやめぐり」「14ブックマーク」
「それ」は、特に男なら誰もが一度は持つものだ。
そして「それ」の多くは、こどもが持つ。
もし一度も持つことがなかったならば、それはきっと悲しいことだろう。
「それ」とは?
※初扉です。解答形式上、扉として出題しましたがウミガメのスープ感覚で結構でございます。

そして「それ」の多くは、こどもが持つ。
もし一度も持つことがなかったならば、それはきっと悲しいことだろう。
「それ」とは?
※初扉です。解答形式上、扉として出題しましたがウミガメのスープ感覚で結構でございます。
17年02月03日 07:39
【20の扉】 [おしゃけ]
【20の扉】 [おしゃけ]

初扉です。
解説を見る
出棺
葬式の際に、死者の棺を式場から送り出すこと。
様式によるが、基本的に故人に近しい男子数名で行われる。
多くは、故人の子になろうか。
いずれにせよ、死ぬまでに一度も「それ」を持たないことは悲しいことに違いないはずだ。
まして親に先立ったとすれば、その悲しみは計り知れない。
「それ」=棺桶
葬式の際に、死者の棺を式場から送り出すこと。
様式によるが、基本的に故人に近しい男子数名で行われる。
多くは、故人の子になろうか。
いずれにせよ、死ぬまでに一度も「それ」を持たないことは悲しいことに違いないはずだ。
まして親に先立ったとすれば、その悲しみは計り知れない。
「それ」=棺桶
「写生日和」「14ブックマーク」
海亀小学校2年生の児童が写生大会で描いた絵が多くの人の目に触れることとなったのは、その日の空に雲ひとつなかったからだという。いったいどういうことだろう?
16年09月13日 23:50
【ウミガメのスープ】 [az]
【ウミガメのスープ】 [az]
解説を見る
写生を終えた子どもたちが提出した絵を見て、担任教師は思わず呻き声を漏らした。子どもたちの描いた絵は、どれも#b#空が灰色で塗られていた#/b#からだ。
写生大会の日、天気予報は晴れ。本来ならば雲ひとつない快晴になるはずだった。それが何故こうも皆、灰色の空を描いたのか。担任教師はわかっている。子どもたちが描いた灰色の正体は雲などではない……すべて#red#工場からの排煙やスモッグ#/red#なのだ。
海亀小学校のある街では最近、大気汚染が急激に悪化している。工場が次々吐き出す煙のせいで、晴れているのにまともに見通しのきかない日も多い。工場のお陰で街の経済が発展したのは否めないところもあり、悪化する大気汚染に気付かぬふりをする住民も少なくなかった。
しかし、だからと言って、幼い子どもにこんな絵を描かせるようなことがあっていいはずはない。教師は決意を固めると、事情を説明する手紙と共に、子どもたちの絵の写真をマスコミ各社に送った。
マスコミはこれに反応し、子どもたちの描いた灰色の空の絵は、大気汚染の深刻化を示す資料として大々的に報道された。雲がなくても青空を描けないほどの大気汚染は社会の関心を呼び、子どもたちの絵は人々の注目を集めたのだった。
#b#【要約】#/b#
雲ひとつないにも関わらず、子どもたちは絵の空を灰色で塗った。空が排煙で覆われていたからだ。その絵は大気汚染の深刻化を示す資料としてマスコミに取り上げられ、多くの人の目に触れることとなった。
写生大会の日、天気予報は晴れ。本来ならば雲ひとつない快晴になるはずだった。それが何故こうも皆、灰色の空を描いたのか。担任教師はわかっている。子どもたちが描いた灰色の正体は雲などではない……すべて#red#工場からの排煙やスモッグ#/red#なのだ。
海亀小学校のある街では最近、大気汚染が急激に悪化している。工場が次々吐き出す煙のせいで、晴れているのにまともに見通しのきかない日も多い。工場のお陰で街の経済が発展したのは否めないところもあり、悪化する大気汚染に気付かぬふりをする住民も少なくなかった。
しかし、だからと言って、幼い子どもにこんな絵を描かせるようなことがあっていいはずはない。教師は決意を固めると、事情を説明する手紙と共に、子どもたちの絵の写真をマスコミ各社に送った。
マスコミはこれに反応し、子どもたちの描いた灰色の空の絵は、大気汚染の深刻化を示す資料として大々的に報道された。雲がなくても青空を描けないほどの大気汚染は社会の関心を呼び、子どもたちの絵は人々の注目を集めたのだった。
#b#【要約】#/b#
雲ひとつないにも関わらず、子どもたちは絵の空を灰色で塗った。空が排煙で覆われていたからだ。その絵は大気汚染の深刻化を示す資料としてマスコミに取り上げられ、多くの人の目に触れることとなった。
「小野寺さん」「14ブックマーク」
俺の大好きな小野寺は、普段俺を見もしないし声もかけてこない。
ある日、その小野寺が俺に
「ずっと見てた。大好きだよ。抱きしめたいくらいに」
と声をかけてきた。
それを聞いた俺はすぐに、小野寺から逃げ出したんだ。
なぜだと思う?

ある日、その小野寺が俺に
「ずっと見てた。大好きだよ。抱きしめたいくらいに」
と声をかけてきた。
それを聞いた俺はすぐに、小野寺から逃げ出したんだ。
なぜだと思う?
16年04月01日 22:47
【ウミガメのスープ】 [低空飛行便]
【ウミガメのスープ】 [低空飛行便]

この恋きっと嘘でもニセモノでもない……のかな? 83杯目。
解説を見る
俺は#red#寺#/red#社仏閣マニアで、中でも小野寺が大好きだ。
けれどあんな大きな建物がなぜかしゃべりだし(口なんてないのに)、
見つめ(目なんてないのに)、さらに抱きしめてきたら、
さすがに俺の身体が持たない。
というか怖い。
そんなわけで俺はすぐに逃げ出したんだ。
けれど今思えば、あれは観音様の声だったのかもしれないな。
何かが始まるきっかけだったのかもしれない。
けれどあんな大きな建物がなぜかしゃべりだし(口なんてないのに)、
見つめ(目なんてないのに)、さらに抱きしめてきたら、
さすがに俺の身体が持たない。
というか怖い。
そんなわけで俺はすぐに逃げ出したんだ。
けれど今思えば、あれは観音様の声だったのかもしれないな。
何かが始まるきっかけだったのかもしれない。