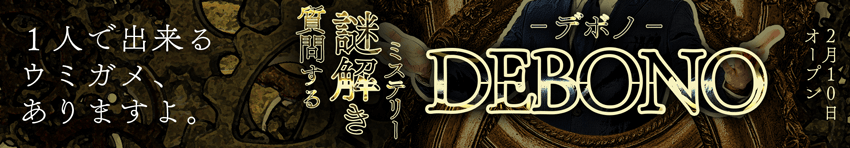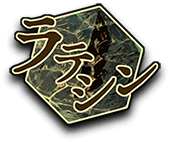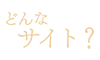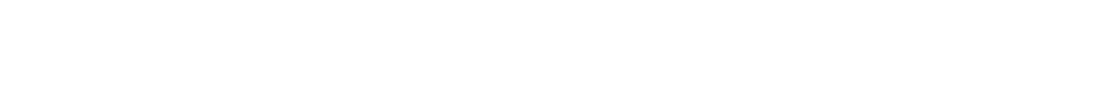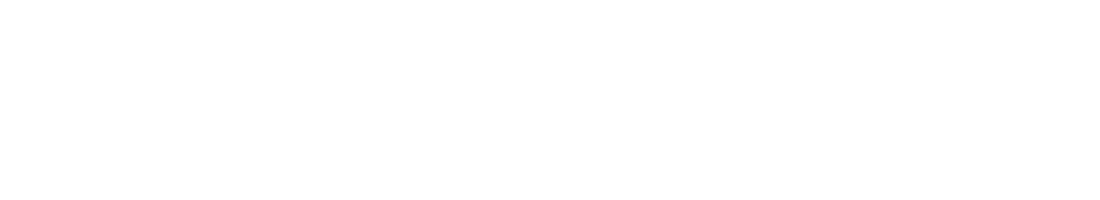「ケルベロスの長男」「6ブックマーク」
東欧の小国・シラネア共和国には
#b#「独裁政治は長く続かない」#/b#ことを意味する#red#「ケルベロスの長男」#/red#という教訓がある。
この「ケルベロスの長男」が、#b#「子供のしつけに丁度よい」#/b#ということで童話として書籍化され、販売されることになった。
当然、子供に対して独裁政治のことを説くような内容ではない。
それでは、童話・「ケルベロスのおにいさん」の教訓とは?
※ケルベロスは、ギリシャ神話で冥界の入り口を守っている3つ頭の番犬です。
#b#「独裁政治は長く続かない」#/b#ことを意味する#red#「ケルベロスの長男」#/red#という教訓がある。
この「ケルベロスの長男」が、#b#「子供のしつけに丁度よい」#/b#ということで童話として書籍化され、販売されることになった。
当然、子供に対して独裁政治のことを説くような内容ではない。
それでは、童話・「ケルベロスのおにいさん」の教訓とは?
※ケルベロスは、ギリシャ神話で冥界の入り口を守っている3つ頭の番犬です。
17年05月07日 20:37
【20の扉】 [アーク]
【20の扉】 [アーク]
解説を見る
食べ物は好き嫌いせずに食べよう。
【補足解説】
ケルベロスは3つ頭の番犬ですが、その身体は1つです。
このため、#b#3つの頭のうちどれか1つが食事をすれば栄養は補給できる#/b#と考えられます。
逆に言えば、1つの頭の発言力が強ければどんな食事でも独り占めをすることが可能です。
シラネアの教訓にいうケルベロスの長男は、長男という立場を利用して、
おいしいエルフの肉は独り占めし、硬くてまずいオークの肉は他の2頭の弟に処理させていました。
そんなことが続くうちに#b#不満を募らせた2頭の弟は、ある日協力して長男を殺すことにした#/b#のです。
このことから「ケルベロスの長男」が「独裁政治は長く続かない」という意味の教訓となりました。
さて、シラネアの教訓でケルベロスの長男が殺されたのは#red#食べ物の好き嫌いをしていた#/red#ことが一因です。
そこで出版社が「この教訓から好き嫌いはダメだということを伝えられるのでは?」と考え、童話として販売することにしたのです。
もしかしたら、この童話を購入した家庭では
「ピーマンもちゃんと食べないとケルベロスのおにいさんみたいになっちゃうよ」なんて言葉が聞けるのかもしれません。
【補足解説】
ケルベロスは3つ頭の番犬ですが、その身体は1つです。
このため、#b#3つの頭のうちどれか1つが食事をすれば栄養は補給できる#/b#と考えられます。
逆に言えば、1つの頭の発言力が強ければどんな食事でも独り占めをすることが可能です。
シラネアの教訓にいうケルベロスの長男は、長男という立場を利用して、
おいしいエルフの肉は独り占めし、硬くてまずいオークの肉は他の2頭の弟に処理させていました。
そんなことが続くうちに#b#不満を募らせた2頭の弟は、ある日協力して長男を殺すことにした#/b#のです。
このことから「ケルベロスの長男」が「独裁政治は長く続かない」という意味の教訓となりました。
さて、シラネアの教訓でケルベロスの長男が殺されたのは#red#食べ物の好き嫌いをしていた#/red#ことが一因です。
そこで出版社が「この教訓から好き嫌いはダメだということを伝えられるのでは?」と考え、童話として販売することにしたのです。
もしかしたら、この童話を購入した家庭では
「ピーマンもちゃんと食べないとケルベロスのおにいさんみたいになっちゃうよ」なんて言葉が聞けるのかもしれません。
「【大好きなお寿司】」「6ブックマーク」
みん『さしゃこの大好物なのに……… もう1枚って何だろ?』
15年06月29日 23:08
【亀夫君問題】 [のりっこ。]
【亀夫君問題】 [のりっこ。]
解説を見る
みん『ただいまーっ! さしゃこ、お寿司買って来たよ^^』
さしゃこ『わぁいママ、ありがとう!!!^^』
みん『そうそう、短冊もう1枚ねw
ママね、最初さしゃこのメールの意味がわからなかったんだよーw
【うにはいらない! もういちまいちょーだい!】 って。
それと、さしゃこが添付してた写メ、よく見たら短冊だったのね。
【おすしいっぱいたべられますよ】
って、短冊に文字を大きく書き過ぎて最後の【うに】が入らなかったんだねw
はい、新しい短冊あげるから、もう1回きちんとお願い事を書いて、
美味しいお寿司を食べながら今夜の七夕を楽しみましょうね♪^^』
さしゃこ『うん!!! さしゃこつぎはみずいろのたんざくにかくーっ!!!^^』
さしゃこ『わぁいママ、ありがとう!!!^^』
みん『そうそう、短冊もう1枚ねw
ママね、最初さしゃこのメールの意味がわからなかったんだよーw
【うにはいらない! もういちまいちょーだい!】 って。
それと、さしゃこが添付してた写メ、よく見たら短冊だったのね。
【おすしいっぱいたべられますよ】
って、短冊に文字を大きく書き過ぎて最後の【うに】が入らなかったんだねw
はい、新しい短冊あげるから、もう1回きちんとお願い事を書いて、
美味しいお寿司を食べながら今夜の七夕を楽しみましょうね♪^^』
さしゃこ『うん!!! さしゃこつぎはみずいろのたんざくにかくーっ!!!^^』
「君に花束」「6ブックマーク」
花屋に来た女が、花束を注文した。花屋の店員は、その女が使わないでくれと言った花を花束にして女に渡したのだが、女は怒るどころか大層喜んだ。
どういうことだろう?

どういうことだろう?
15年02月11日 15:32
【ウミガメのスープ】 [とかげ]
【ウミガメのスープ】 [とかげ]

束になったスープ
解説を見る
カランコロン…
「いらっしゃいませー!」
店員が入口のベルに合わせて声をかけると、落ち着いた雰囲気の女性の顔が覗いた。よく、この店に花を買いに来てくれる、常連客だ。
「こんにちは、お久しぶりですね。お孫さんはお元気ですか?」
「ええ、おかげさまで、風邪ひとつひかないみたいですよ」
にこやかにほほ笑むと、目元に笑い皺ができる。店員は彼女を見るたび、理想的な歳の重ね方だと感じていた。
「孫の誕生日につくっていただいた花束、お嫁さんも気に入ってくれたようで……またお祝い事のときにはお願いしますね」
「はい、もちろんです。ええと、では今日はお祝い事とは違うのですか?」
「今日は、主人のホワイトデーのお返しに、花束をつくっていただきたいのですが……小さなものも、つくれますか?」
女性は予算と数を提示する。店員は、その予算であれば、持ち運びしやすいサイズで十分華やかなものがつくれると説明した。
「ホワイトデーのお返しが花束なんて、オシャレですね。奥様のご提案なのですか?」
「いえ、主人です。普段はお菓子やハンカチが多いのですが、定年も間近ですし、あと数回しかお返しできないことを考えて、ちょっと変わったものにしたいと」
「自分で花束を買うことってなかなかないですから、喜ばれると思いますよ」
それで、と女性は鞄の中から小さく折りたたまれた紙を取りだした。
「こちらに書いてある花は、使わないでいただきたいのですが…」
渡されたリストには、定番のバラや、チューリップ、マーガレットなど、店にもよく置いてある花が並んでいる。
「我儘を言ってすみません」
「大丈夫ですよ……そうですね、ここに載っていないものでしたら、今店にスイートピーやダリアはありますし、カスミ草も……はい、お時間いただければつくれます」
「ありがとうございます、ではお願いしますね」
受け取りの時間を確認し、いつものように穏やかに微笑む女性だったが、店員の目には、彼女が少し、寂しそうに見えていた。
「妻がね、何やら花の名前をずらずらと紙に書き並べていて……これから花束を買うのだそうだが……」
数時間前に店に立ち寄った初老の男性は、この店によく花を買いに来てくれる女性のご主人だった。これから出社するという時間帯で、店はまだ開店していなかったのだが、店先で準備をしていた店員に話しかけてきたのだ。
男性は妻に、ホワイトデーのお返しとして社内の女性社員に花束を買うことを提案したのだという。それを聞いてここ数日、妻は本やインターネットで花を調べていたらしい。
「今日この店に買いに来るはずなんだが、妻の様子が気になってね。しかし僕は花なんて全然知識がなくて……妻が何をしたがっているか、君ならわかるかい?」
具体的にどんな花の名前が並んでいたかを聞き出した店員は、困惑する男性に向かって、こんな質問を投げかけた。
「ご主人は、奥様に花束をプレゼントしたことが、ありますか?」
男性は唐突な質問に一瞬押し黙り、そして記憶を探るようにして歯切れ悪く答えた。
「……おそらく、妻に贈ったことは、ない……ですかね」
「自分は貰ったことがないのに、ご主人が他の女性に花束を贈られる、というのは、あまり面白いものではないと思いますよ」
店員の少し意地悪な物言いに、倍ほども歳の違う男性は素直に自分の非を認め、なるほど、と気まずそうに呟いた。
「そんなこと、思い至りませんでした。確かに妻は不満も文句も言ったことがありませんが、僕のことを思って我慢してくれていたんですかね……」
落ち込む男性だったが、でも、と不思議そうな顔をする。
「それと、妻がつくっていた花のリストと、どう関係するのですか?」
「はい、そのこともあって、私から提案があるのですが……!」
店員の申し出に、男性は二つ返事で賛成した。慌ただしく駅に向かった男性を見送りながら、店員はどんな花束をつくろうか、楽しい想像に心躍らせていた。
カランコロン……
「いらっしゃいませ――あ、ご注文の花束、仕上がっていますよ!」
「こんにちは、ありがとうございます」
時間通りにやってきた女性に、店員は注文通りの花束を手渡す。
「綺麗につくってくださって、ありがとうございます」
「いえいえ、これが仕事ですから。ああ、それからこちら……」
店員は、大ぶりな花束を、女性に差し出した。
「こちらも、注文の品です」
「……え? いえ、頼んでいませんが……」
女性が戸惑うのも無理はない。大きなサイズの花束は注文していないし、そんなに立派な花束は、先ほど告げた予算全部を使っても買えそうにない。何より、その花束に使われている花は、女性が使わないで欲しいと言った花ばかりが使われていた。
「何かの間違いでは?」
「いえ、間違いではございません。今朝、きちんとご主人から注文を受けました」
「主人が?」
「そろそろいらっしゃるお時間だと思いますよ」
その声と同時に、入口のベルがカランコロン……と音を立てた。
朝、この花屋に立ち寄った初老の男性が、笑顔を浮かべながら店に入ってきた。
「注文の品、出来上がっていますよ」
「ありがとうございます……これはいいですね。花を知らない僕でも、見事なのがよくわかりますよ」
「あなた、どういうことなの?」
男性は女性――自分の妻の手から、ホワイトデー用の花束がいくつも入った紙袋を取り、代わりに大きな花束を彼女に持たせる。
「これは君へのプレゼントだよ。いつもありがとう」
笑顔の店員と夫を見比べ、状況がつかめない女性は、それでも素直に花束を受け取り、鮮やかな花々を茫然と見つめていたが。
「花言葉も、そのまま受け取ってくれ」
男性の言葉に、はっと顔を挙げた。
「わかっていたの?」
「店員さんに教えてもらったんだ。気が利かなくて申し訳なかった」
全てを理解した女性は、いつものように、穏やかな笑顔を浮かべた。目元の笑い皺が、いつもよりも深い。
「ありがとう……あなたにも、お礼を言わなくては。本当に、ありがとうございます」
「いえ、私はただ……」
店員は控えめに否定して、きっぱり言った。
「花を贈られて喜んでもらえる人が、一人でも多ければいい、それだけなんです」
#b#女性の夫が他の女性にプレゼントするための花束だったので、愛の言葉を花言葉に持つ花を除くよう、女性は希望した。夫は除かれた花を集めた花束を花屋に頼み、それを花屋が女性に渡したので、夫から愛の言葉を持つ花束を贈られた女性は喜んだのだった。#/b#
「いらっしゃいませー!」
店員が入口のベルに合わせて声をかけると、落ち着いた雰囲気の女性の顔が覗いた。よく、この店に花を買いに来てくれる、常連客だ。
「こんにちは、お久しぶりですね。お孫さんはお元気ですか?」
「ええ、おかげさまで、風邪ひとつひかないみたいですよ」
にこやかにほほ笑むと、目元に笑い皺ができる。店員は彼女を見るたび、理想的な歳の重ね方だと感じていた。
「孫の誕生日につくっていただいた花束、お嫁さんも気に入ってくれたようで……またお祝い事のときにはお願いしますね」
「はい、もちろんです。ええと、では今日はお祝い事とは違うのですか?」
「今日は、主人のホワイトデーのお返しに、花束をつくっていただきたいのですが……小さなものも、つくれますか?」
女性は予算と数を提示する。店員は、その予算であれば、持ち運びしやすいサイズで十分華やかなものがつくれると説明した。
「ホワイトデーのお返しが花束なんて、オシャレですね。奥様のご提案なのですか?」
「いえ、主人です。普段はお菓子やハンカチが多いのですが、定年も間近ですし、あと数回しかお返しできないことを考えて、ちょっと変わったものにしたいと」
「自分で花束を買うことってなかなかないですから、喜ばれると思いますよ」
それで、と女性は鞄の中から小さく折りたたまれた紙を取りだした。
「こちらに書いてある花は、使わないでいただきたいのですが…」
渡されたリストには、定番のバラや、チューリップ、マーガレットなど、店にもよく置いてある花が並んでいる。
「我儘を言ってすみません」
「大丈夫ですよ……そうですね、ここに載っていないものでしたら、今店にスイートピーやダリアはありますし、カスミ草も……はい、お時間いただければつくれます」
「ありがとうございます、ではお願いしますね」
受け取りの時間を確認し、いつものように穏やかに微笑む女性だったが、店員の目には、彼女が少し、寂しそうに見えていた。
「妻がね、何やら花の名前をずらずらと紙に書き並べていて……これから花束を買うのだそうだが……」
数時間前に店に立ち寄った初老の男性は、この店によく花を買いに来てくれる女性のご主人だった。これから出社するという時間帯で、店はまだ開店していなかったのだが、店先で準備をしていた店員に話しかけてきたのだ。
男性は妻に、ホワイトデーのお返しとして社内の女性社員に花束を買うことを提案したのだという。それを聞いてここ数日、妻は本やインターネットで花を調べていたらしい。
「今日この店に買いに来るはずなんだが、妻の様子が気になってね。しかし僕は花なんて全然知識がなくて……妻が何をしたがっているか、君ならわかるかい?」
具体的にどんな花の名前が並んでいたかを聞き出した店員は、困惑する男性に向かって、こんな質問を投げかけた。
「ご主人は、奥様に花束をプレゼントしたことが、ありますか?」
男性は唐突な質問に一瞬押し黙り、そして記憶を探るようにして歯切れ悪く答えた。
「……おそらく、妻に贈ったことは、ない……ですかね」
「自分は貰ったことがないのに、ご主人が他の女性に花束を贈られる、というのは、あまり面白いものではないと思いますよ」
店員の少し意地悪な物言いに、倍ほども歳の違う男性は素直に自分の非を認め、なるほど、と気まずそうに呟いた。
「そんなこと、思い至りませんでした。確かに妻は不満も文句も言ったことがありませんが、僕のことを思って我慢してくれていたんですかね……」
落ち込む男性だったが、でも、と不思議そうな顔をする。
「それと、妻がつくっていた花のリストと、どう関係するのですか?」
「はい、そのこともあって、私から提案があるのですが……!」
店員の申し出に、男性は二つ返事で賛成した。慌ただしく駅に向かった男性を見送りながら、店員はどんな花束をつくろうか、楽しい想像に心躍らせていた。
カランコロン……
「いらっしゃいませ――あ、ご注文の花束、仕上がっていますよ!」
「こんにちは、ありがとうございます」
時間通りにやってきた女性に、店員は注文通りの花束を手渡す。
「綺麗につくってくださって、ありがとうございます」
「いえいえ、これが仕事ですから。ああ、それからこちら……」
店員は、大ぶりな花束を、女性に差し出した。
「こちらも、注文の品です」
「……え? いえ、頼んでいませんが……」
女性が戸惑うのも無理はない。大きなサイズの花束は注文していないし、そんなに立派な花束は、先ほど告げた予算全部を使っても買えそうにない。何より、その花束に使われている花は、女性が使わないで欲しいと言った花ばかりが使われていた。
「何かの間違いでは?」
「いえ、間違いではございません。今朝、きちんとご主人から注文を受けました」
「主人が?」
「そろそろいらっしゃるお時間だと思いますよ」
その声と同時に、入口のベルがカランコロン……と音を立てた。
朝、この花屋に立ち寄った初老の男性が、笑顔を浮かべながら店に入ってきた。
「注文の品、出来上がっていますよ」
「ありがとうございます……これはいいですね。花を知らない僕でも、見事なのがよくわかりますよ」
「あなた、どういうことなの?」
男性は女性――自分の妻の手から、ホワイトデー用の花束がいくつも入った紙袋を取り、代わりに大きな花束を彼女に持たせる。
「これは君へのプレゼントだよ。いつもありがとう」
笑顔の店員と夫を見比べ、状況がつかめない女性は、それでも素直に花束を受け取り、鮮やかな花々を茫然と見つめていたが。
「花言葉も、そのまま受け取ってくれ」
男性の言葉に、はっと顔を挙げた。
「わかっていたの?」
「店員さんに教えてもらったんだ。気が利かなくて申し訳なかった」
全てを理解した女性は、いつものように、穏やかな笑顔を浮かべた。目元の笑い皺が、いつもよりも深い。
「ありがとう……あなたにも、お礼を言わなくては。本当に、ありがとうございます」
「いえ、私はただ……」
店員は控えめに否定して、きっぱり言った。
「花を贈られて喜んでもらえる人が、一人でも多ければいい、それだけなんです」
#b#女性の夫が他の女性にプレゼントするための花束だったので、愛の言葉を花言葉に持つ花を除くよう、女性は希望した。夫は除かれた花を集めた花束を花屋に頼み、それを花屋が女性に渡したので、夫から愛の言葉を持つ花束を贈られた女性は喜んだのだった。#/b#
「【要知識問題】『何枚?』」「6ブックマーク」
見えないのでABDEGILNPSを使い、
枚数を数えようとしてください。
枚数を数えようとしてください。
16年09月19日 17:07
【20の扉】 [のりっこ。]
【20の扉】 [のりっこ。]
解説を見る
Please be landing
(着陸してください)
というazさんの指示によりパイロットはヘリコプターを着陸させ、
あなたはそのヘリのプロペラ(羽根)の枚数が2枚である事が目視確認出来た。
(着陸してください)
というazさんの指示によりパイロットはヘリコプターを着陸させ、
あなたはそのヘリのプロペラ(羽根)の枚数が2枚である事が目視確認出来た。
「九段さん」「6ブックマーク」
カメオ「おとこはしんだ、な…?」
カメオの疑問を解決してあげてください。
【説明】
これは亀夫君問題です。
質問には「カメオ」が答えます。
カメオに状況を聞いたり、指示したりすることができます。

カメオの疑問を解決してあげてください。
【説明】
これは亀夫君問題です。
質問には「カメオ」が答えます。
カメオに状況を聞いたり、指示したりすることができます。
17年08月08日 15:46
【亀夫君問題】 [上3]
【亀夫君問題】 [上3]

おとこはしんだ、な
解説を見る
カメオが最初見ていた部分
-------
おとこ|
はしん|
だ、な|
-------
看板の全体
----------
|るきおとこ |
|よにはしん|
|ねなだ、な|
-----------
縦書きとして読むと、
こんな歳、お肌気になるよね
これはアンチエイジングの広告だったのだ。
-------
おとこ|
はしん|
だ、な|
-------
看板の全体
----------
|るきおとこ |
|よにはしん|
|ねなだ、な|
-----------
縦書きとして読むと、
こんな歳、お肌気になるよね
これはアンチエイジングの広告だったのだ。