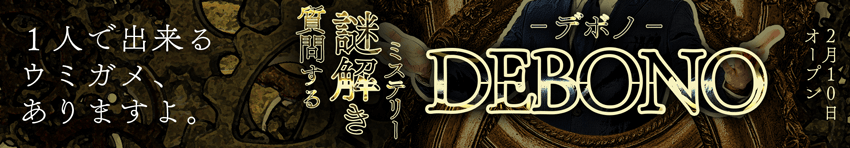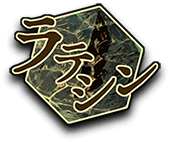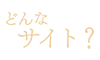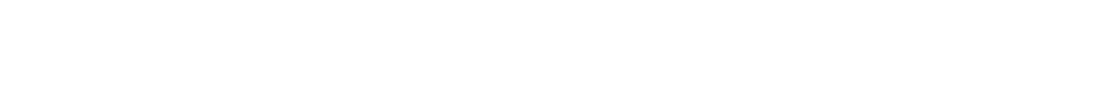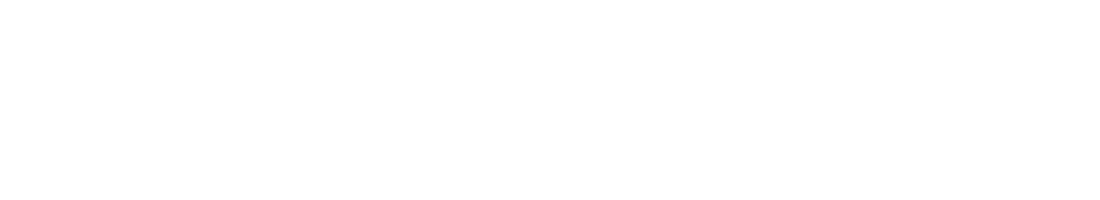「1200秒の誘拐」「6ブックマーク」
公園で遊んでいたカメオは誘拐された。
しかし20分後には何事もなく解放された。
身代金を払ったわけでもカメオが自分で抜け出したわけでもないなら
一体なぜだろう?
しかし20分後には何事もなく解放された。
身代金を払ったわけでもカメオが自分で抜け出したわけでもないなら
一体なぜだろう?
17年10月14日 19:51
【ウミガメのスープ】 [天童 魔子]
【ウミガメのスープ】 [天童 魔子]
解説を見る
最近、幼子から目を離してお喋りやスマホに夢中になる母親が増えている。
公園を管理するものとしては嘆かわしい限りだ。
目を離した隙に車道に飛び出したり事故に巻き込まれたらどうするつもりなのか?
だからちょっと子供を攫って
気付いた親がようやく心配してあたりを探し周り
警察に連絡しようか否か悩んだタイミングを見計らって子供を解放してやるのさ。
そうすれば今後、ちゃんと子供を見るようになるだろう?
公園を管理するものとしては嘆かわしい限りだ。
目を離した隙に車道に飛び出したり事故に巻き込まれたらどうするつもりなのか?
だからちょっと子供を攫って
気付いた親がようやく心配してあたりを探し周り
警察に連絡しようか否か悩んだタイミングを見計らって子供を解放してやるのさ。
そうすれば今後、ちゃんと子供を見るようになるだろう?
「初めての20の扉」「6ブックマーク」
「……が寝返りを打ちました。さてどうなった?」
「【A】と【B】になった。何故なら……」
【A】【B】には何を入れたらいいと思う?
※特別の断りがない限り、一回の質問で【A】【B】それぞれについて回答します。もちろん、【A】【B】を直接問う以外の質問も可です。

「【A】と【B】になった。何故なら……」
【A】【B】には何を入れたらいいと思う?
※特別の断りがない限り、一回の質問で【A】【B】それぞれについて回答します。もちろん、【A】【B】を直接問う以外の質問も可です。
14年09月15日 16:56
【20の扉】 [牛削り]
【20の扉】 [牛削り]

タイトルの通りです。お手柔らかにお願いします。
解説を見る
ラテシン歴2ヶ月の佐々木は、ついに20の扉の出題条件を満たし、
とっておきの問題を出題することにした。
記念すべき問題、投稿ミスがあってはいけないと、確認画面でチェックした。
すると……
#b#問題文#/b#
「歩兵が寝返りを打ちました。さてどうなった?」
#b#解説文#/b#
「redと/redになった。何故なら、将棋の『歩兵』の裏には『redと/red』が書かれているから」
#big5#佐#/big5#々木「あれ、おかしいなあ。『と』が赤くならない」
その時、どこからともなくこんな声が頭に響いた。
さるぼぼ「ああ、文字を赤くしたい場合はね、『#red##red##/red#』と『#red##/red##/red#』で挟むんだ」
佐々木「そうなの? 試してみるね」
その結果……
#b#問題文#/b#
「歩兵が寝返りを打ちました。さてどうなった?」
#b#解説文#/b#
「#red#と#/red#になった。何故なら、将棋の『歩兵』の裏には『#red#と#/red#』が書かれているから」
#big5#佐#/big5#々木「おお、赤くなった! ありがとう、天の声さん。これでやっと出題できるよ! #red#初めての20の扉#/red#、みんな楽しんでくれるかなあ」
さるぼぼ「そ、そう。これ20の扉なんだ……。がんばってね……(出来の悪いなぞなぞやん)」
#b#【解答】#/b#
穴埋めはそれぞれ、
【A】=#red#
【B】=#/red#
最初の「……」=歩兵
最後の「……」=「歩兵」の裏が「と」である、という説明。
でした。
※なお、佐々木が想定しているのは裏が朱色のタイプの駒のため、赤文字のフォントタグのみを正解とさせていただきました。
※出題経験がなくちんぷんかんぷんだった方、すみませんでした。
とっておきの問題を出題することにした。
記念すべき問題、投稿ミスがあってはいけないと、確認画面でチェックした。
すると……
#b#問題文#/b#
「歩兵が寝返りを打ちました。さてどうなった?」
#b#解説文#/b#
「redと/redになった。何故なら、将棋の『歩兵』の裏には『redと/red』が書かれているから」
#big5#佐#/big5#々木「あれ、おかしいなあ。『と』が赤くならない」
その時、どこからともなくこんな声が頭に響いた。
さるぼぼ「ああ、文字を赤くしたい場合はね、『#red##red##/red#』と『#red##/red##/red#』で挟むんだ」
佐々木「そうなの? 試してみるね」
その結果……
#b#問題文#/b#
「歩兵が寝返りを打ちました。さてどうなった?」
#b#解説文#/b#
「#red#と#/red#になった。何故なら、将棋の『歩兵』の裏には『#red#と#/red#』が書かれているから」
#big5#佐#/big5#々木「おお、赤くなった! ありがとう、天の声さん。これでやっと出題できるよ! #red#初めての20の扉#/red#、みんな楽しんでくれるかなあ」
さるぼぼ「そ、そう。これ20の扉なんだ……。がんばってね……(出来の悪いなぞなぞやん)」
#b#【解答】#/b#
穴埋めはそれぞれ、
【A】=#red#
【B】=#/red#
最初の「……」=歩兵
最後の「……」=「歩兵」の裏が「と」である、という説明。
でした。
※なお、佐々木が想定しているのは裏が朱色のタイプの駒のため、赤文字のフォントタグのみを正解とさせていただきました。
※出題経験がなくちんぷんかんぷんだった方、すみませんでした。
「料理人と華道家の相談」「6ブックマーク」
料理人と華道家が何か相談をしている。
料理人「卵焼き、肉じゃが、かな……」
華道家「なら、山桜、芍薬、だね……」
二人は何の相談をしているのだろうか?
※嘘は無し、リスト聞きはOKのルールです。

料理人「卵焼き、肉じゃが、かな……」
華道家「なら、山桜、芍薬、だね……」
二人は何の相談をしているのだろうか?
※嘘は無し、リスト聞きはOKのルールです。
14年09月15日 14:16
【20の扉】 [低空飛行便]
【20の扉】 [低空飛行便]

枠が空いているうちにこっそりと20の扉を初出題してみる。→こっそりはやめました。
解説を見る
料理人と華道家は#red#クロスワード問題#/red#を
相談しながら二人で解いていた。
そのクロスワード問題
↓
■や■し■
たまごやき
■ざ■く■
にくじやが
■ら■く■
相談しながら二人で解いていた。
そのクロスワード問題
↓
■や■し■
たまごやき
■ざ■く■
にくじやが
■ら■く■
「「コーラウミガメ味」 目にした者の言語中枢を破壊する」「6ブックマーク」
バス内でBさんと布団談義をしていたAさんは
サラリーマンが後ろでコーラウミガメ味を飲んでいるのを目にしてから
Bさんの言葉や呼びかけに反応しなくなった。
一体どういうこと?
サラリーマンが後ろでコーラウミガメ味を飲んでいるのを目にしてから
Bさんの言葉や呼びかけに反応しなくなった。
一体どういうこと?
16年09月16日 00:08
【ウミガメのスープ】 [入れ子]
【ウミガメのスープ】 [入れ子]
解説を見る
Bさんと#b#スマホのチャット#/b#で布団談義に花を咲かせていたAさん。
「やっぱり羽毛が一番だよね~」と送信しようとしたその時
#b#Aさんのスマホの電源が切れた。#/b#
充電切れである。
真っ暗になったスマホの画面にはAさんの真顔と
#red#後ろでコーラウミガメ味を飲んでいるサラリーマンが肩越しに映っていた。#/red#
スマホの電源が切れればチャットで反応できないのは当然であるので問題文のような状況が起こったのだ。
あと掛け布団は羽毛。異論は認める。
「やっぱり羽毛が一番だよね~」と送信しようとしたその時
#b#Aさんのスマホの電源が切れた。#/b#
充電切れである。
真っ暗になったスマホの画面にはAさんの真顔と
#red#後ろでコーラウミガメ味を飲んでいるサラリーマンが肩越しに映っていた。#/red#
スマホの電源が切れればチャットで反応できないのは当然であるので問題文のような状況が起こったのだ。
あと掛け布団は羽毛。異論は認める。
「失敗は成功のもと? 【要知識】」「6ブックマーク」
男は何度も何度も詰将棋に失敗したので、儲けることができた。
なぜ?
※ 補足知識
詰将棋とは、特定の局面から相手の王様を攻めて逃げ道を無くす(詰ませる) 将棋パズル。
150~200問を1冊にまとめた本が多く売られている。
将棋ファンが終盤の攻めを勉強するために読み、よく売れている。

なぜ?
※ 補足知識
詰将棋とは、特定の局面から相手の王様を攻めて逃げ道を無くす(詰ませる) 将棋パズル。
150~200問を1冊にまとめた本が多く売られている。
将棋ファンが終盤の攻めを勉強するために読み、よく売れている。
15年11月19日 19:28
【ウミガメのスープ】 [ひゅー]
【ウミガメのスープ】 [ひゅー]

問題文に補足知識あり
解説を見る
男は将棋棋士である。
詰将棋を作り、本を売ることを副業としている。
作るのは難しく、ぎりぎり王様を逃がしてしまう失敗作が1000個は生まれただろうか。
男は視点を変え、失敗作を「守る側が自分の王様を逃がす」問題として本にまとめた。
これが大ヒットして男は儲けることができた。
終盤の守りに関する本は、ほとんどなかったのである。
※ 森信雄 著『逃れ将棋』 が元ネタとなっております。
詰将棋を作り、本を売ることを副業としている。
作るのは難しく、ぎりぎり王様を逃がしてしまう失敗作が1000個は生まれただろうか。
男は視点を変え、失敗作を「守る側が自分の王様を逃がす」問題として本にまとめた。
これが大ヒットして男は儲けることができた。
終盤の守りに関する本は、ほとんどなかったのである。
※ 森信雄 著『逃れ将棋』 が元ネタとなっております。