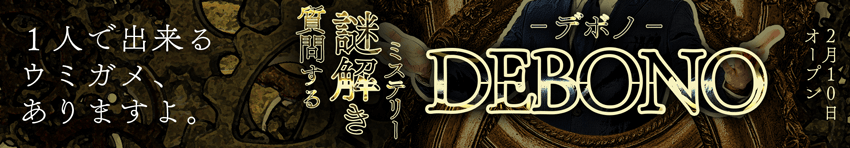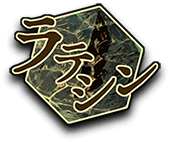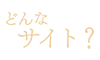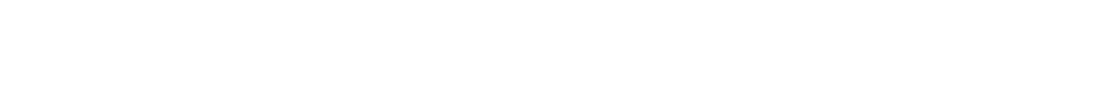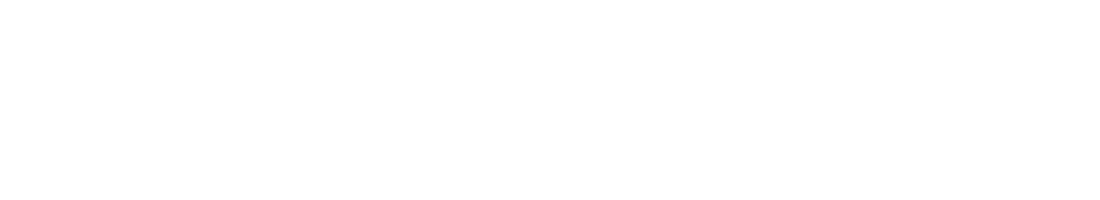「けして放棄ではない!」「124ブックマーク」
掃除をしていることを褒められたカメオは、すぐに掃除をやめてしまった。
一体なぜだろう?
一体なぜだろう?
15年08月18日 23:01
【ウミガメのスープ】 [甘木]
【ウミガメのスープ】 [甘木]
解説を見る
カメオはホウキ……ではなく掃除機で掃除をしていた。
#big5#ブオオオ……#/big5#
母「あら、カメオ掃除しているの?偉いわねぇ。」
#big5#ブオオオ……#/big5#
カメオ「……え?なんか言った?」
カメオは母が自分に向けて言ったことの内容を確認するために、#red#今使っている掃除機の電源を一旦切って掃除を中断した#/red#のだ。
#big5#ブオオオ……#/big5#
母「あら、カメオ掃除しているの?偉いわねぇ。」
#big5#ブオオオ……#/big5#
カメオ「……え?なんか言った?」
カメオは母が自分に向けて言ったことの内容を確認するために、#red#今使っている掃除機の電源を一旦切って掃除を中断した#/red#のだ。
「何の変哲もない小説」「123ブックマーク」
面白みのないストーリーで、どこにでもいるような魅力の薄い登場人物が、普段誰もが過ごしているような日常を送るだけの、無名の小説家による小説。
そんな何の変哲もない小説が、何の変哲もないために売れまくっているという。
どういうことだろう?

そんな何の変哲もない小説が、何の変哲もないために売れまくっているという。
どういうことだろう?
15年04月27日 22:50
【ウミガメのスープ】 [とかげ]
【ウミガメのスープ】 [とかげ]

ごく普通のスープ
解説を見る
その小説を呼んで、男は驚いた。
ごく普通の夫婦が、平凡な日常を過ごすだけの小説だった。
出てくる登場人物は、見た目も性格も思想もごく普通の人達で、魅力的でもなんでもない。
夫婦の暮す家は一般的なアパートで、置いてある家具や家電の描写は、当たり前過ぎて何の面白みもないものだった。
朝夫が出勤して、しばらくすると妻も仕事に出かけ、二人はそれぞれの職場でありきたりな仕事をこなし、どうってことはない友人達とのくだらない会話を交わし、家に帰ってからどこでも食べられそうな夕食をたいらげ、ベーシックなデザインのパジャマを着て、平均的な時間に就寝する。
男は、恐怖すら感じた。
これは……なぜ、こんなに、何の変哲もないのだ。
まるで自分の一日を書かれているかのような――
改めて、本の後ろに書いてある出版年月日を確認する。
何度見ても、男が持つその本は、今から100年以上前に書かれたSF小説だということに、変わりはなかった。
END
#b#100年以上前に書かれたSF小説が、何の変哲もないと感じるくらい今の生活を見事に言い当てていたため、未来を予言した書として有名になり、売れまくった。#/b#
ごく普通の夫婦が、平凡な日常を過ごすだけの小説だった。
出てくる登場人物は、見た目も性格も思想もごく普通の人達で、魅力的でもなんでもない。
夫婦の暮す家は一般的なアパートで、置いてある家具や家電の描写は、当たり前過ぎて何の面白みもないものだった。
朝夫が出勤して、しばらくすると妻も仕事に出かけ、二人はそれぞれの職場でありきたりな仕事をこなし、どうってことはない友人達とのくだらない会話を交わし、家に帰ってからどこでも食べられそうな夕食をたいらげ、ベーシックなデザインのパジャマを着て、平均的な時間に就寝する。
男は、恐怖すら感じた。
これは……なぜ、こんなに、何の変哲もないのだ。
まるで自分の一日を書かれているかのような――
改めて、本の後ろに書いてある出版年月日を確認する。
何度見ても、男が持つその本は、今から100年以上前に書かれたSF小説だということに、変わりはなかった。
END
#b#100年以上前に書かれたSF小説が、何の変哲もないと感じるくらい今の生活を見事に言い当てていたため、未来を予言した書として有名になり、売れまくった。#/b#
「11人いた」「115ブックマーク」
宇宙船には10人分の食糧が積み込まれていたが、乗っていたのは11人。途中で食糧が足りなくなり、仕方なく、誰が死ぬかを決めるためにくじを引くことにした。
たった1人、当たりを引いてしまったのは、男が愛する女だった。泣きわめいて嫌がる彼女を、男は自らの手で殺した。
彼女を愛するがゆえに。
どういうことだろう?

たった1人、当たりを引いてしまったのは、男が愛する女だった。泣きわめいて嫌がる彼女を、男は自らの手で殺した。
彼女を愛するがゆえに。
どういうことだろう?
15年11月11日 22:47
【ウミガメのスープ】 [とかげ]
【ウミガメのスープ】 [とかげ]

宇宙食スープ
解説を見る
思えば、この旅はそもそもスクランブルから始まった。
10人乗りの宇宙船による、冒険旅行。必要な生活用品や食糧は宇宙船に積み込まれているし、客室やキッチン、娯楽スペース、重力装置などの設備は整っているが、旅行会社のスタッフは添乗しない。コンピュータによる自動操縦のため、パイロットすらいない。
10人の乗客達が共同生活をしながら、約1ヶ月宇宙空間を漂う、今注目のツアーだ。
有名な観光衛星をいくつも眺められるコースでありながら、人件費がかからないという理由で旅費自体は比較的安価であるため、特に若い世代に人気だった。ちょっとしたサバイバル感覚を楽しめるというのも売りにしていた。
とはいえ、やはり一番予約が殺到するのは長期間休みが取りやすい盆暮れ正月の時期で、シーズンオフのその日――11月11日に出発するのは「スペース・ウォーク11号」だけだった。
むしろこの時期によく実施可能人数まで集まったなと感心していたくらいなので、時間通り無事に打ち上げられた「スペース・ウォーク11号」のロビーで初めて顔を合わせたとき、その場にいる人数の多さに驚いた。
10人どころか、11人いたのだ。
しかし、全員のチケットに「スペース・ウォーク11号」の名と正確な日時が記されていた。第一、宇宙船への搭乗は機械で管理されている。書類を偽造しても入れるはずがないのだ。
すぐに11人はお互いを疑うことをやめ、これは旅行会社の手配ミスか、あるいは11人のために2台の宇宙船を用意する経費と手間をケチったのであろうと結論づけた。
部屋はもともと予備として1部屋余分にあったため、全員が1人部屋を使えたし、食糧や衣類などは11人で分け合えば問題なさそうだった。
事前の説明で、もし何か不測の事態――スクランブルが発生したら、非常ボタンを押すように言われていた。10人乗りのはずの宇宙船に11人乗っているのは、まさにそんな非常事態ではあったが、非常ボタンを押すことには全員が反対した。非常ボタンを押せば、「スペース・ウォーク11号」は最悪自動操縦で地球に戻ってしまう。同じ旅行をもう1度頼むには、また休みの調整をしなくてはいけなくなるし、何より集まった11人は自然とすぐに打ち解けていた。このメンバーでまた同じ旅行するのは不可能だろうから、1人多かったくらいで旅行が中止になるのは勿体なく思えたのだ。
次のスクランブルはすぐに発生した。
この事態を一応旅行会社に伝えておくべきだろうという話が出て、出発から3日後、通信機器を使ってみることになったのだが、何度通信を試みても、雑音を拾うばかりで交信ができない。備え付けの通信機器だったので、取り外して修理するわけにもいかず、この旅行を終えるまでは、外部と連絡が取れないことが確定した。
「本当に、サバイバルのようだ」
ソラ――11人は初日から、お互いにコードネームをつけて呼び合っていた――はそんなイレギュラーを聞いても、快活に笑い飛ばした。彼はよく喋り、よく笑い、よく食べた。新人ながら成績優秀な営業マンという話も頷ける。自然と人を引き付ける好青年だった。
「1人多い上に連絡も取れないなんて。こんな経験、なかなかないぞ。もちろん旅行会社にはきっちりクレームを入れるが、話のネタとしては面白い」
皮肉屋のリクも、よくそんなことを口にして、手帳に日記のようなものをつけていた。帰ったら、所属している劇団の仲間に自慢するのだそうだ。次の芝居のネタにもなると言っていた。
この段階になっても、11人は実に楽観的であった。
調理師専門学校に通うウミが手掛けた美味しい料理を食べながら、地球上のあらゆる国を旅しているクモの話に耳を傾けるのは心地よかった。宇宙しか描かないと言い張っていたダイチが、こっそり皆の顔のデッサンをしていたことに笑い、アメのつくったでたらめで陽気な唄を大声で合唱するのも楽しかった。この11人で過ごす毎日があまりに充実していて、1人多いなんてことも、通信機器が使えないことも、些末なことに思えたのだ。
3つ目のスクランブルに気付いたのは、博識なカゼだった。彼は宇宙航空学を学んでいる大学院生だそうで、毎日熱心に観測をしていた。観測の結果、当初の予定とは宇宙船の軌道がずれていると気付いたのだ。
それを聞いた宇宙船オタクのタイヨウは、早速自動操縦になっているコックピットを調べてくれた。通信機器の不調の影響で微調整が効かず、軌道がずれたようだということだった。
ここに来てようやく、皆は不安を感じ始めた。皆の前では「なんとかなるって!」と言っていたナミですら、時折ふっと表情が暗くなったし、一人でトレーニングルームにこもることが増えた。
毎日お互いの好きな本について語り合っていたユキも、徐々に元気がなくなってきた。日本文学が好きなユキと、SFをこよなく愛する僕は、初日に竹取物語が最古のSFであることについての話題で盛り上がり、意気投合していた。けれど二人とも、このSF的展開を純粋に楽しむことはできそうになかった。
カゼとタイヨウのおかげで、この宇宙船は予定通りの観光はおろか、残念ながら地球に戻ることすらできないことが判明するのに時間はかからなかった。
さすがにもう、非常ボタンを押すことにためらいはなかった。この時点で既に半月ほど経っていた。11人はもう十年来の付き合いがある友人のような仲になっていた。地球に戻っても絶対に連絡を取り合おう、またこのメンバーで予定を合わせて再会しよう、と約束を交わし、全員でコックピット内の非常ボタンの前に集まった。
代表して、ソラがボタンを押す。
チカチカと非常灯が点滅し、非常ボタンの上に据えられたディスプレイには、「非常事態発生」という文字が現れる。その下に次々と、プログラム名らしき英数字が踊った。読み取れるのは「ERROR」という嫌な言葉だけだ。
しばらく英数字と「ERROR」を交互に表示し続けたのち、ようやく現れた日本語は、「非常事態応急対応11」だった。
「11? 11ってなんだ。その前の1から10は何だったんだ?」
アメが首をひねる。
「事前にデータで送られてたよ。ええと……1が地球本部への連絡、2が自動操縦による地球帰還……あれ、おかしいな。10までしか載ってない」
タブレットでデータを確認しながら、クモも困惑した表情を浮かべた。
「ねえ、これは……」
控え目に、一番奥で静かに見守っていたユキが声を上げる。ユキが指差すのは、それまでただの壁だった場所――どうも非常ボタンに呼応して自動的に扉のように開き、収納スペースが現れたのだ。
「瓶が……10本。何が入っているの?」
興味深そうに手を伸ばしたナミは、しかしすぐにさっと顔色を変えた。落としそうになったところをリクが慌ててキャッチし、そしてアメも瓶のラベルを見て目を見開く。
「……毒だ」
その言葉自身が毒であったかのように、しんと静まり返った。
それまでタブレットを見ていたクモが、静寂を無理やり引き裂いて、苦しげに告げる。
「非常事態の対応として、書かれているのは10個だけだ。その中には、手動運転で地球に戻ることや、近くの星に不時着することも含まれている。……その10個が、全部ダメだったんだろう。11番目はおそらく、本当の最終手段だ。表向きには載せられないような。だから、その……」
「つまり、苦しまないうちに死ねと」
ダイチが言いにくい部分を引き継いだ。
「スペース・ウォーク11号」が、ただの棺となった瞬間だった。
それからは、正直なところ、記憶が薄い。
すごいことが起こってしまったと、頭ではわかっているつもりなのだが、不思議と現実味はなかった。11人は暗黙のうちに、なるべくそれまでと同じように過ごしていた。何か手立てはないかと船内の設備や道具を探す人もいたが、大した収穫は得られなかった。ウミは意識して食糧を節約してくれたが、それでも食糧庫の中は日に日に寂しくなっていった。
僕はなるべくユキと共に過ごすようにしていた。宇宙でお気に入りのSF小説を読むことが夢だったが、それはもう叶った。平凡で何の取り柄もない僕には、他に思い残すことと言えばユキのことしかなかった。
非常ボタンを押してから更に1ヶ月が経ち、ソラから全員集まって欲しいという呼びかけがあったとき、全員がその意図を理解していた。
「本当に楽しい旅だった。こんなに楽しい経験は人生で初めてだった。皆もそうであることを願う。……率直に言おう、食糧がもう足りない」
ソラはいつものように笑顔で、そう言った。
「燃料と酸素も、残り僅かだ」
タイヨウが付け加えた。最後まで、何か方法はないかと探してくれていた彼だったが、今は実にあっけらかんとした表情をして続ける。
「食糧がなくて飢えるか、燃料が足りなくなって墜落するか、あるいは呼吸ができなくなるか……何が先にやってくるかはわからないけれど、でも俺達は確実に、死ぬ」
そして例のごとく、ダイチが一番言いにくい部分をこともなげに言い放った。
「苦しまずに死ぬなら、毒を飲むしかない。毒は、10人分だ」
毒の瓶は10本だった。僕たちは11人いた。
もしかしたら10本を11人で等分すれば、致死量に足りるかもしれない。しかしそれでは最悪、11人全員が苦しみながらも死ねない状態になるかもしれない。
もはや死ぬことは仕方ないとは言え、自分1人が孤独の中苦しみながら死ぬことを進んで請け負う者はいなかった。
「俺は、くじ引きを提案したい。本当は誰にも苦しんで欲しくないし、俺だって苦しみたくないけれど、仕方ない。誰が毒を飲んで死ぬか、決めよう」
リクの発案が残酷なことは承知で、しかし誰も反対しなかった。その展開を読んでいたのか、ウミは食糧庫からチューブ型のスープを持ってきた。それが最後のメニューらしい。毒を入れやすく、そして見分けがつかない。
毒の入った10杯のスープと、たった1杯の普通のスープ。
全員が1杯ずつ受け取り、いつものように「おやすみ」と挨拶をして、スープを手にそれぞれの部屋へ帰って行った。それが永遠の別れであることをあえて誰も口に出さず、しかし互いに固い握手を交わして、11人は別れた。
僕が次の日に目を覚ましたとき、聞こえてきたのは泣き叫ぶ声だけだった。いつもの明るい騒がしさはない。嫌だ、嫌だという悲痛な叫びがただ響く。
泣き声はドアの前からするらしかった。声は、ユキのものだ。時計は日本時間で午前11時。毒を飲んでいれば、既に死んでいるはずの時間。
彼女は、死ななかった。
当たりを引いたのだ。
鍵を開けてドアをスライドさせると、泣きわめいていた声がやみ、しゃがみこんだユキの姿が現れた。
「え……?」
呆気にとられたような表情を浮かべるユキから、聞かれる前に、答える。
「飲んでいなかったんだ」
スープのチューブを見せて、思わず涙も止まったユキに差し出した。
「君が飲め」
彼女は答えない。状況が理解できていないのか、口を開けてただ僕を見上げる。
「君が飲め。君の分が毒薬でなかったのだから、僕のこれは毒薬に間違いない。これで確実に死ねる」
「でも、でもそれだとあなたが」
「僕はいいんだ」
決めていた。もし、万が一ユキが当たりを引いてしまったら――
「まさか、最初から――」
止まっていた涙が、また湧きあがるようにポロポロと彼女の双眸からこぼれ落ちる。
僕は大馬鹿者だと思う。決意が揺らがないように、僕は彼女へきちんと理由を告げる。
「――愛しているから」
弱々しく抵抗する彼女を押さえつけ、その口にチューブを差し込んだ。泣きながら、彼女は少しずつ最後のスープを飲んだ。
飲み終わった後も、僕達2人は一緒にくだらない話をした。地球での生活のこと、他の9人の仲間のこと、それから、2人に待ち受けていたかもしれない未来について。
涙は止まらなかったが、時折見せるユキの笑顔は、相変わらず控え目で大人しくて、けれどこの世で一番愛くるしかった。
4時間経ったところで、彼女の呂律が怪しくなってきた。意識も朦朧としてきたようだ。それでも懸命に抗って、最後まで僕に話しかけようとしてくれていた。
「ありがとう、ツキ」
その言葉が、彼女の最後の言葉になった。
宇宙船は静かになった。
ここには11人いた。にぎやかだった。
ここから先は、死にたくても死ねない、辛い時間がただ流れるのだ。餓死か墜落死か窒息死か……わからないけれど、絶対に楽には死ねないということしか確実ではないこの状況で、僕はたった1人になってしまった。ユキの動かなくなった身体は、ベッドに横たえておいた。他の9人の姿も確認した。皆、穏やかな表情を浮かべて、眠るように死んでいた。
心の底から、良かったと思う。
こんな孤独、彼女に与えてしまわなくて、本当に良かったと。
静まり返った「スペース・ウォーク11号」が、10人の死体と1人の生き残りを乗せて、宇宙を行く。
ここには、11人いた。
11人、いたんだ。
END
#b#助かる見込みのない状況で、むごい死に方よりも毒を飲んで死ぬことを決意したが、その毒が1人分足りない。くじで生き残ることが決まってしまった女のために、男は自分の毒を彼女に飲ませて殺した。彼女を愛するがゆえに。#/b#
10人乗りの宇宙船による、冒険旅行。必要な生活用品や食糧は宇宙船に積み込まれているし、客室やキッチン、娯楽スペース、重力装置などの設備は整っているが、旅行会社のスタッフは添乗しない。コンピュータによる自動操縦のため、パイロットすらいない。
10人の乗客達が共同生活をしながら、約1ヶ月宇宙空間を漂う、今注目のツアーだ。
有名な観光衛星をいくつも眺められるコースでありながら、人件費がかからないという理由で旅費自体は比較的安価であるため、特に若い世代に人気だった。ちょっとしたサバイバル感覚を楽しめるというのも売りにしていた。
とはいえ、やはり一番予約が殺到するのは長期間休みが取りやすい盆暮れ正月の時期で、シーズンオフのその日――11月11日に出発するのは「スペース・ウォーク11号」だけだった。
むしろこの時期によく実施可能人数まで集まったなと感心していたくらいなので、時間通り無事に打ち上げられた「スペース・ウォーク11号」のロビーで初めて顔を合わせたとき、その場にいる人数の多さに驚いた。
10人どころか、11人いたのだ。
しかし、全員のチケットに「スペース・ウォーク11号」の名と正確な日時が記されていた。第一、宇宙船への搭乗は機械で管理されている。書類を偽造しても入れるはずがないのだ。
すぐに11人はお互いを疑うことをやめ、これは旅行会社の手配ミスか、あるいは11人のために2台の宇宙船を用意する経費と手間をケチったのであろうと結論づけた。
部屋はもともと予備として1部屋余分にあったため、全員が1人部屋を使えたし、食糧や衣類などは11人で分け合えば問題なさそうだった。
事前の説明で、もし何か不測の事態――スクランブルが発生したら、非常ボタンを押すように言われていた。10人乗りのはずの宇宙船に11人乗っているのは、まさにそんな非常事態ではあったが、非常ボタンを押すことには全員が反対した。非常ボタンを押せば、「スペース・ウォーク11号」は最悪自動操縦で地球に戻ってしまう。同じ旅行をもう1度頼むには、また休みの調整をしなくてはいけなくなるし、何より集まった11人は自然とすぐに打ち解けていた。このメンバーでまた同じ旅行するのは不可能だろうから、1人多かったくらいで旅行が中止になるのは勿体なく思えたのだ。
次のスクランブルはすぐに発生した。
この事態を一応旅行会社に伝えておくべきだろうという話が出て、出発から3日後、通信機器を使ってみることになったのだが、何度通信を試みても、雑音を拾うばかりで交信ができない。備え付けの通信機器だったので、取り外して修理するわけにもいかず、この旅行を終えるまでは、外部と連絡が取れないことが確定した。
「本当に、サバイバルのようだ」
ソラ――11人は初日から、お互いにコードネームをつけて呼び合っていた――はそんなイレギュラーを聞いても、快活に笑い飛ばした。彼はよく喋り、よく笑い、よく食べた。新人ながら成績優秀な営業マンという話も頷ける。自然と人を引き付ける好青年だった。
「1人多い上に連絡も取れないなんて。こんな経験、なかなかないぞ。もちろん旅行会社にはきっちりクレームを入れるが、話のネタとしては面白い」
皮肉屋のリクも、よくそんなことを口にして、手帳に日記のようなものをつけていた。帰ったら、所属している劇団の仲間に自慢するのだそうだ。次の芝居のネタにもなると言っていた。
この段階になっても、11人は実に楽観的であった。
調理師専門学校に通うウミが手掛けた美味しい料理を食べながら、地球上のあらゆる国を旅しているクモの話に耳を傾けるのは心地よかった。宇宙しか描かないと言い張っていたダイチが、こっそり皆の顔のデッサンをしていたことに笑い、アメのつくったでたらめで陽気な唄を大声で合唱するのも楽しかった。この11人で過ごす毎日があまりに充実していて、1人多いなんてことも、通信機器が使えないことも、些末なことに思えたのだ。
3つ目のスクランブルに気付いたのは、博識なカゼだった。彼は宇宙航空学を学んでいる大学院生だそうで、毎日熱心に観測をしていた。観測の結果、当初の予定とは宇宙船の軌道がずれていると気付いたのだ。
それを聞いた宇宙船オタクのタイヨウは、早速自動操縦になっているコックピットを調べてくれた。通信機器の不調の影響で微調整が効かず、軌道がずれたようだということだった。
ここに来てようやく、皆は不安を感じ始めた。皆の前では「なんとかなるって!」と言っていたナミですら、時折ふっと表情が暗くなったし、一人でトレーニングルームにこもることが増えた。
毎日お互いの好きな本について語り合っていたユキも、徐々に元気がなくなってきた。日本文学が好きなユキと、SFをこよなく愛する僕は、初日に竹取物語が最古のSFであることについての話題で盛り上がり、意気投合していた。けれど二人とも、このSF的展開を純粋に楽しむことはできそうになかった。
カゼとタイヨウのおかげで、この宇宙船は予定通りの観光はおろか、残念ながら地球に戻ることすらできないことが判明するのに時間はかからなかった。
さすがにもう、非常ボタンを押すことにためらいはなかった。この時点で既に半月ほど経っていた。11人はもう十年来の付き合いがある友人のような仲になっていた。地球に戻っても絶対に連絡を取り合おう、またこのメンバーで予定を合わせて再会しよう、と約束を交わし、全員でコックピット内の非常ボタンの前に集まった。
代表して、ソラがボタンを押す。
チカチカと非常灯が点滅し、非常ボタンの上に据えられたディスプレイには、「非常事態発生」という文字が現れる。その下に次々と、プログラム名らしき英数字が踊った。読み取れるのは「ERROR」という嫌な言葉だけだ。
しばらく英数字と「ERROR」を交互に表示し続けたのち、ようやく現れた日本語は、「非常事態応急対応11」だった。
「11? 11ってなんだ。その前の1から10は何だったんだ?」
アメが首をひねる。
「事前にデータで送られてたよ。ええと……1が地球本部への連絡、2が自動操縦による地球帰還……あれ、おかしいな。10までしか載ってない」
タブレットでデータを確認しながら、クモも困惑した表情を浮かべた。
「ねえ、これは……」
控え目に、一番奥で静かに見守っていたユキが声を上げる。ユキが指差すのは、それまでただの壁だった場所――どうも非常ボタンに呼応して自動的に扉のように開き、収納スペースが現れたのだ。
「瓶が……10本。何が入っているの?」
興味深そうに手を伸ばしたナミは、しかしすぐにさっと顔色を変えた。落としそうになったところをリクが慌ててキャッチし、そしてアメも瓶のラベルを見て目を見開く。
「……毒だ」
その言葉自身が毒であったかのように、しんと静まり返った。
それまでタブレットを見ていたクモが、静寂を無理やり引き裂いて、苦しげに告げる。
「非常事態の対応として、書かれているのは10個だけだ。その中には、手動運転で地球に戻ることや、近くの星に不時着することも含まれている。……その10個が、全部ダメだったんだろう。11番目はおそらく、本当の最終手段だ。表向きには載せられないような。だから、その……」
「つまり、苦しまないうちに死ねと」
ダイチが言いにくい部分を引き継いだ。
「スペース・ウォーク11号」が、ただの棺となった瞬間だった。
それからは、正直なところ、記憶が薄い。
すごいことが起こってしまったと、頭ではわかっているつもりなのだが、不思議と現実味はなかった。11人は暗黙のうちに、なるべくそれまでと同じように過ごしていた。何か手立てはないかと船内の設備や道具を探す人もいたが、大した収穫は得られなかった。ウミは意識して食糧を節約してくれたが、それでも食糧庫の中は日に日に寂しくなっていった。
僕はなるべくユキと共に過ごすようにしていた。宇宙でお気に入りのSF小説を読むことが夢だったが、それはもう叶った。平凡で何の取り柄もない僕には、他に思い残すことと言えばユキのことしかなかった。
非常ボタンを押してから更に1ヶ月が経ち、ソラから全員集まって欲しいという呼びかけがあったとき、全員がその意図を理解していた。
「本当に楽しい旅だった。こんなに楽しい経験は人生で初めてだった。皆もそうであることを願う。……率直に言おう、食糧がもう足りない」
ソラはいつものように笑顔で、そう言った。
「燃料と酸素も、残り僅かだ」
タイヨウが付け加えた。最後まで、何か方法はないかと探してくれていた彼だったが、今は実にあっけらかんとした表情をして続ける。
「食糧がなくて飢えるか、燃料が足りなくなって墜落するか、あるいは呼吸ができなくなるか……何が先にやってくるかはわからないけれど、でも俺達は確実に、死ぬ」
そして例のごとく、ダイチが一番言いにくい部分をこともなげに言い放った。
「苦しまずに死ぬなら、毒を飲むしかない。毒は、10人分だ」
毒の瓶は10本だった。僕たちは11人いた。
もしかしたら10本を11人で等分すれば、致死量に足りるかもしれない。しかしそれでは最悪、11人全員が苦しみながらも死ねない状態になるかもしれない。
もはや死ぬことは仕方ないとは言え、自分1人が孤独の中苦しみながら死ぬことを進んで請け負う者はいなかった。
「俺は、くじ引きを提案したい。本当は誰にも苦しんで欲しくないし、俺だって苦しみたくないけれど、仕方ない。誰が毒を飲んで死ぬか、決めよう」
リクの発案が残酷なことは承知で、しかし誰も反対しなかった。その展開を読んでいたのか、ウミは食糧庫からチューブ型のスープを持ってきた。それが最後のメニューらしい。毒を入れやすく、そして見分けがつかない。
毒の入った10杯のスープと、たった1杯の普通のスープ。
全員が1杯ずつ受け取り、いつものように「おやすみ」と挨拶をして、スープを手にそれぞれの部屋へ帰って行った。それが永遠の別れであることをあえて誰も口に出さず、しかし互いに固い握手を交わして、11人は別れた。
僕が次の日に目を覚ましたとき、聞こえてきたのは泣き叫ぶ声だけだった。いつもの明るい騒がしさはない。嫌だ、嫌だという悲痛な叫びがただ響く。
泣き声はドアの前からするらしかった。声は、ユキのものだ。時計は日本時間で午前11時。毒を飲んでいれば、既に死んでいるはずの時間。
彼女は、死ななかった。
当たりを引いたのだ。
鍵を開けてドアをスライドさせると、泣きわめいていた声がやみ、しゃがみこんだユキの姿が現れた。
「え……?」
呆気にとられたような表情を浮かべるユキから、聞かれる前に、答える。
「飲んでいなかったんだ」
スープのチューブを見せて、思わず涙も止まったユキに差し出した。
「君が飲め」
彼女は答えない。状況が理解できていないのか、口を開けてただ僕を見上げる。
「君が飲め。君の分が毒薬でなかったのだから、僕のこれは毒薬に間違いない。これで確実に死ねる」
「でも、でもそれだとあなたが」
「僕はいいんだ」
決めていた。もし、万が一ユキが当たりを引いてしまったら――
「まさか、最初から――」
止まっていた涙が、また湧きあがるようにポロポロと彼女の双眸からこぼれ落ちる。
僕は大馬鹿者だと思う。決意が揺らがないように、僕は彼女へきちんと理由を告げる。
「――愛しているから」
弱々しく抵抗する彼女を押さえつけ、その口にチューブを差し込んだ。泣きながら、彼女は少しずつ最後のスープを飲んだ。
飲み終わった後も、僕達2人は一緒にくだらない話をした。地球での生活のこと、他の9人の仲間のこと、それから、2人に待ち受けていたかもしれない未来について。
涙は止まらなかったが、時折見せるユキの笑顔は、相変わらず控え目で大人しくて、けれどこの世で一番愛くるしかった。
4時間経ったところで、彼女の呂律が怪しくなってきた。意識も朦朧としてきたようだ。それでも懸命に抗って、最後まで僕に話しかけようとしてくれていた。
「ありがとう、ツキ」
その言葉が、彼女の最後の言葉になった。
宇宙船は静かになった。
ここには11人いた。にぎやかだった。
ここから先は、死にたくても死ねない、辛い時間がただ流れるのだ。餓死か墜落死か窒息死か……わからないけれど、絶対に楽には死ねないということしか確実ではないこの状況で、僕はたった1人になってしまった。ユキの動かなくなった身体は、ベッドに横たえておいた。他の9人の姿も確認した。皆、穏やかな表情を浮かべて、眠るように死んでいた。
心の底から、良かったと思う。
こんな孤独、彼女に与えてしまわなくて、本当に良かったと。
静まり返った「スペース・ウォーク11号」が、10人の死体と1人の生き残りを乗せて、宇宙を行く。
ここには、11人いた。
11人、いたんだ。
END
#b#助かる見込みのない状況で、むごい死に方よりも毒を飲んで死ぬことを決意したが、その毒が1人分足りない。くじで生き残ることが決まってしまった女のために、男は自分の毒を彼女に飲ませて殺した。彼女を愛するがゆえに。#/b#
「ウィル・オ・ウィスプ・ガール」「114ブックマーク」
私達の村の近くにある、『出る』と噂の不気味な林道。
そこにはある一つのルールが存在する。
その林道で、
『もし一人ぼっちで歌う少女を見かけたら、絶対に関わってはいけない』
というものだ。
なぜそんなルールが存在するのだろう?
そこにはある一つのルールが存在する。
その林道で、
『もし一人ぼっちで歌う少女を見かけたら、絶対に関わってはいけない』
というものだ。
なぜそんなルールが存在するのだろう?
14年08月22日 21:37
【ウミガメのスープ】 [ruxyo]
【ウミガメのスープ】 [ruxyo]
解説を見る
私達の村に住む一人の少女。
病気の母のために、毎日朝早くに街に働きに出て、夜遅くに帰ってくる。
その不気味な林道は、街に続く唯一の道だが、
近くには墓もあり、死んだ村人達の幽霊が出るともっぱらの噂だった。
幼い少女が夜遅くに一人でその林道を通るのは、相当な勇気がいることだろう。
だから、少女は怖さを紛らわすために陽気な歌を歌う。泣きそうになりながら歌う。
あまりにも健気でかわいそうなので、#red#その林道に出る『村人の幽霊』である私達#/red#は、
少女を怖がらせないために、彼女が通る間は視界の届かない場所に隠れることに決めたのだった。
おかげで少女は幽霊を見たことはなく、仕事に支障をきたしたこともない。
お母ちゃん、早く良くなるといいね。
病気の母のために、毎日朝早くに街に働きに出て、夜遅くに帰ってくる。
その不気味な林道は、街に続く唯一の道だが、
近くには墓もあり、死んだ村人達の幽霊が出るともっぱらの噂だった。
幼い少女が夜遅くに一人でその林道を通るのは、相当な勇気がいることだろう。
だから、少女は怖さを紛らわすために陽気な歌を歌う。泣きそうになりながら歌う。
あまりにも健気でかわいそうなので、#red#その林道に出る『村人の幽霊』である私達#/red#は、
少女を怖がらせないために、彼女が通る間は視界の届かない場所に隠れることに決めたのだった。
おかげで少女は幽霊を見たことはなく、仕事に支障をきたしたこともない。
お母ちゃん、早く良くなるといいね。
「恋するフォーチュンクッキー」「103ブックマーク」
今日はバレンタインデー。
カメタは幼馴染のカメコからハート形のクッキーを貰ったのですが、なぜか悲しげな様子です。
一体何故でしょうか?
カメタは幼馴染のカメコからハート形のクッキーを貰ったのですが、なぜか悲しげな様子です。
一体何故でしょうか?
14年04月01日 22:36
【ウミガメのスープ】 [脳内カーニバル]
【ウミガメのスープ】 [脳内カーニバル]
解説を見る
実はカメタはカメコの事が好きでした。
そんなカメコから貰ったクッキーは、雑な四角い生地がハート形に「くり抜かれた」クッキーでした。
くり抜いた方のちゃんとしたクッキーは誰にあげたんだろう・・・と少し悲しげなカメタでした。
そんなカメコから貰ったクッキーは、雑な四角い生地がハート形に「くり抜かれた」クッキーでした。
くり抜いた方のちゃんとしたクッキーは誰にあげたんだろう・・・と少し悲しげなカメタでした。