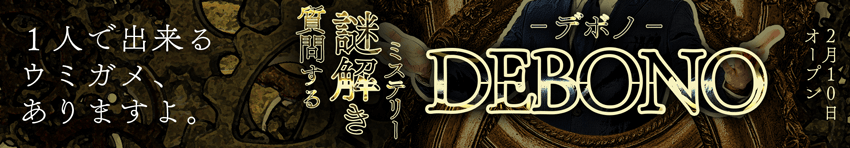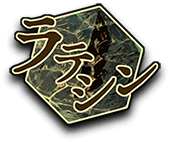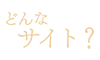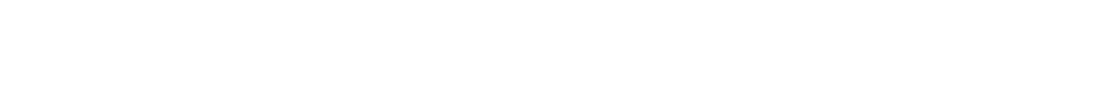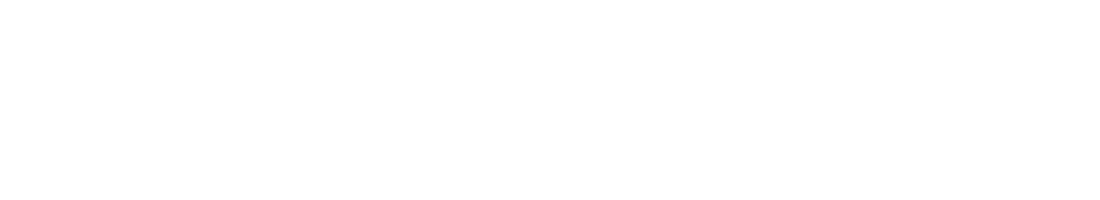「予知能力者の逮捕」「9ブックマーク」
犬山は予知能力者である。大体二日先のことまでなら自分に何が起こるか予知することができる。
その能力を生かしてテストでは常に満点を取り、万引きなどをしても捕まることはなかった。
だがある日、犬山はとある犯罪の現行犯として捕まってしまった。
予知能力を使えばこの事は当然予知できたはずなのだが……
何故犬山はそのような事をしたのだろう?
その能力を生かしてテストでは常に満点を取り、万引きなどをしても捕まることはなかった。
だがある日、犬山はとある犯罪の現行犯として捕まってしまった。
予知能力を使えばこの事は当然予知できたはずなのだが……
何故犬山はそのような事をしたのだろう?
16年05月15日 09:17
【ウミガメのスープ】 [耳たぶ犬]
【ウミガメのスープ】 [耳たぶ犬]
解説を見る
この世には自分ではどうしようもないことがある。
そんな子供でも知っていることに犬山が気づいたのは、自分が誰かに殺人事件の犯人に仕立て上げられそうになっていると予知した時だった。
気づいたときにはその計画を止めることもできない事を悟った。おそらく計画は何年も前から考えられていたことなのだろう。
犬山が犯人にされないために必要なことは、アリバイを作ることだった。だが犯人もそんな事は想定しているだろう。友人や家族、果ては近隣住民と一緒にいたとしてもそんなものはアリバイとは言えない。
そして犬山は、#b#究極のアリバイを作ることにした#/b#
計画は何年も前から立てられたものだ。大きなイレギュラーがあれば計画を中止し誰も死なないかもしれない。死人が出なくて済むなら、刑務所に数ヶ月閉じ込められるくらい楽なものだ。
#red#彼は殺人犯として逮捕される前に他の犯罪の現行犯として捕まることを選んだ#/red#
…退学になったのはこの際諦めよう。人命救助のためには仕方ない。
そんな子供でも知っていることに犬山が気づいたのは、自分が誰かに殺人事件の犯人に仕立て上げられそうになっていると予知した時だった。
気づいたときにはその計画を止めることもできない事を悟った。おそらく計画は何年も前から考えられていたことなのだろう。
犬山が犯人にされないために必要なことは、アリバイを作ることだった。だが犯人もそんな事は想定しているだろう。友人や家族、果ては近隣住民と一緒にいたとしてもそんなものはアリバイとは言えない。
そして犬山は、#b#究極のアリバイを作ることにした#/b#
計画は何年も前から立てられたものだ。大きなイレギュラーがあれば計画を中止し誰も死なないかもしれない。死人が出なくて済むなら、刑務所に数ヶ月閉じ込められるくらい楽なものだ。
#red#彼は殺人犯として逮捕される前に他の犯罪の現行犯として捕まることを選んだ#/red#
…退学になったのはこの際諦めよう。人命救助のためには仕方ない。
「花柄の白いワンピース」「9ブックマーク」
「あなたが助けてくれなければ、私はあの事故で死んでいました」
ヒロキの乗った車椅子を押しながら、ヨウコはいつものように感謝を告げた。
しかしヒロキは誰の命も救ってはいないし、そもそもヨウコは"あの事故"で死にかけてなどいない。
だとすれば、ヨウコはなぜ、このようなことを言うのだろう?
ヒロキの乗った車椅子を押しながら、ヨウコはいつものように感謝を告げた。
しかしヒロキは誰の命も救ってはいないし、そもそもヨウコは"あの事故"で死にかけてなどいない。
だとすれば、ヨウコはなぜ、このようなことを言うのだろう?
16年05月10日 20:00
【ウミガメのスープ】 [牛削り]
【ウミガメのスープ】 [牛削り]
解説を見る
■
田所多恵は、その事故の目撃者の一人である。
大学の講義の合間の暇をつぶそうと、ドーナツ屋のテラス席でコーヒーを飲んでいた。スマートフォンの電池残量が少なくなっていることに気付き、ゲームをやめてぼんやりと通りを眺めていたという。
昼前の時間帯で、人通りはまばらだった。ドーナツ屋は交差点に面しており、多恵の目の前には横断歩道がキャンパスの方まで伸びている。一人の女性が、その先で信号待ちをしていた。花柄の白いワンピースを着た背の高い女性で、「お花みたいな人」と多恵は表現した。
歩行者用の信号が青に変わって、ワンピースの女性が歩き出した。他に横断歩道を渡っている人はいなかった。
彼女が横断歩道の真ん中まで来たとき、多恵はふと、妙な胸騒ぎを覚えた。これは単なる予感じゃない、と、多恵は思ったという。視線を横に向けると、その違和感の正体がわかった。
交差点に差しかかろうとしている乗用車が、猛スピードのまま、まったく減速する様子を見せないのである。多恵がヤバいと思わず口にしたときには、すでに事は起きていた。
自分の方に向かってくる車に気付くも、足がすくんでしまった女性。
そこへ、どこからともなく一人の男性が走ってきて、彼女を突き飛ばした。
その瞬間、車が何かに当たる鈍い音が響いた。
車は車道をそれ、電信柱に激突して止まった。
多恵の目は、不自然な方向に脚を曲げ、血まみれで倒れている男性の姿をとらえていた。
「えっと、119番」
多恵は電池残量の少なくなったスマートフォンを起動した。
☆
悪夢から覚めたとき、元宮浩樹は左手にぬくもりを感じていた。誰かが手を握ってくれているのだとわかった。
目を開くと、そこには白いワンピース姿の女性が腰掛けていた。腰の辺りに大きな黄色の花がプリントされている。
彼女は彼の目を見て、ヒッと息を呑んだ。
「も、元宮さん」
誰だろう、と思った。それにここは、病院?
「ちょっと待っててください。今お医者さん呼んできます」
医師により脳波や心拍のチェックが行われた。いくつか簡単な質問もされた。
「軽い記憶障害があるようですが、脳に目立った異常は無いようですね。ここまで回復するとは、正直奇跡的です。ただし、運動機能に後遺症が残るかもしれません。リハビリは必ず行ってください」
浩樹は自分の腕や脚に包帯が巻かれていることに気付いた。
医師が去ると、ワンピースの女性がまた現れた。浩樹はとりあえず会釈した。
「元宮さん、意識が戻られて、本当に私、嬉しいです」
泣き出しそうな笑顔で彼女は言った。
「あの、気を悪くしたらごめん。俺ぜんぜん今の状況を把握できてないんだけど、えっと、あなたは、誰?」
「あ……」彼女は口元を手で押さえた。「そうですよね、ちゃんと説明しなくちゃ、混乱しますよね。交通事故のことは覚えてます?」
「交通事故……」
交通事故と聞いて、フラッシュバックする光景があった。迫りくる車、立ちすくむ女性、目の前に伸ばされた自分の腕。
「そうか、俺は車に轢かれたんだ」
「はい。あなたが助けてくださったのが、私です。戸倉葉子といいます」
「葉子さん」と、浩樹は繰り返した。「俺は、どれくらい眠っていたの?」
「三ヶ月、です」伏目がちにそう言った。
「あの」彼女は不意に立ち上がった。「まず、お礼を言わせてください。助けていただいて、本当にありがとうございました。このご恩は、必ず……」
深々と下げられた彼女の頭を、浩樹はしばらく見つめていた。
そこへ、浩樹の母親がやってきた。浩樹の姿を見るや否や、わんわんと泣き出した。ひとしきり泣いた後、今後の話になった。
「あなた、実家に戻らない? その身体だし、一人暮らしってわけにはいかないでしょう。お母さんもそんなに頻繁に行き来できないし」
「大学をやめてってことか?」
「大丈夫よ。就職先はお父さんがなんとかしてくれるから」
「大学はやめないよ、絶対。三ヶ月くらいの遅れなら、取り戻せる」
「そういうことじゃないでしょ、浩樹。生活はどうするのよ」
「どうにでもなるさ」
「浩樹」
守られすぎている、と思っていた。幼い頃から、望めば何でも買ってもらえた。生活に不自由は何もなかった。失敗はすべて許された。出来心で万引きをしてしまった日も、ストレスのせいだと解釈され、父親によってうやむやにされた。大学も、親のコネで一流のところに入れてやると言われた。浩樹はそれを断り、勉強した。一流とはいえないが、そこそこ名のある大学に合格した。
生まれて初めて、自分で勝ち取ったものだった。
「あの」
母親ではない女性の声がした。見ると、ワンピースの女性。さっき、葉子と名乗っていた。
「私が、浩樹さんの生活のお手伝いをします。だから、こっちにいさせてあげてください」
母は目を丸くした。
「あなた、でも」
「浩樹さんに救っていただいた命です。一生かけてでも、恩返しがしたいんです。浩樹さんは、ご迷惑ですか?」
「いや……」浩樹は母親と葉子の顔を見比べた。「お願いするよ」
「浩樹あなた」
「母さん、気持ちを考えてみてくれよ。俺と、それからこの、葉子さんの」
「お願いします」葉子は母親に向かって頭を下げた。
母親は戸惑うような表情を浮かべた後、大きくため息をついた。
「わかったわ。でも、辛くなったらいつでも戻ってくるのよ。それから葉子さん、あんまり思いつめなくていいからね」
葉子が頭を上げた。母の肩越しに、彼女と目が合った。葉子は小さく笑った。浩樹も返事をするように、小さく笑った。
葉子との二人三脚の日々が始まった。
彼女はリハビリに辛抱強く付き合ってくれたし、大学の遅れを取り戻せるよう、ノートやプリントをかき集めてくれた。葉子は学部こそ違うが、同じ大学の同級生なのだという。
退院後も車イス生活を余儀なくされた浩樹のもとへ、葉子は毎日通って、あれこれと世話を焼いてくれた。
「あなたがいなかったら私は死んでいたんです。このくらい当然なんですよ」
葉子が何度も何度も感謝の気持ちを告げてくれるから、浩樹は頼りきっているという負い目を感じずに済んだ。
違和感に気付いたのは、次に葉子が花柄の白いワンピースを着てきた日であった。
「こんにちは、浩樹さん。今日もよろしくお願いします」
「ああ、よろしく……」
そう言いながら彼は、葉子のワンピースのすそを見ていた。
何か、おかしい。彼はそう思った。
「じゃあさっそく、掃除しちゃいますね」
葉子が掃除用具の置いてあるクローゼットを開けると、中のモップが倒れてきた。彼女はとっさに、腕を顔の前でクロスした。
「あ」と浩樹は思わずもらした。
「ごめんなさい、大きな音立てちゃって。どうかしました?」
「いや」思いついたことがあった。「ねえそのワンピース、どこで買ったの?」
★
「ねえそのワンピース、どこで買ったの?」
そう問いかける元宮浩樹の目には、いつもと違うシリアスな光があった。
「え、どうしてですか?」
「いや、よく似合っているからさ。センスのいい店なんだろうなって」
「えっと、小杉にある、アントワープっていう小さなお店です」
「アントワープ、ね。ありがとう」
「いえ……あ、じゃあ掃除しちゃいますね」
家具の上のほこりを払いながら、葉子は思った。自分は何か失敗をしてしまったのではないか。
知らず、葉子はあの事故のことを思い返していた。
事故現場は凄惨だった。電信柱に突っ込み大破した車。群がる人々。車道の真ん中で、大量の血を流して倒れている男性。そして……。
葉子は頭を振る。もう夢の中で何度も見てきた映像だ。本当は忘れてしまいたかった。
しかしどんなに頭を振っても、今思い浮かべてしまった光景は離れてくれない。
回想の中、彼女はまるで幽霊のように、現場を俯瞰で見ていた。
と、彼女は何か、気付いてはいけないものに気付いた気がした。今の俯瞰図に、おかしなところがある。どこだ、どこ……。
葉子の手からはたきが落ちた。
現場に倒れている女性。着ているのは……。
血に染まった白いワンピース……。
☆
葉子が帰った後、浩樹は「アントワープ」をインターネットで調べ、電話をかけた。
「はい、アントワープです」
「あの、お尋ねしたいことがありまして」
「なんでしょう」
「そちらで、白いワンピースを扱っているでしょう?」
「白いワンピース、ですか」
「ほら、大きな花が付いていて……」浩樹は思い出せる限りの特徴を並べた。
「ああ」電話の向こうの男は、声のトーンを少し上げた。「去年の春、そんなのを入れた覚えがあります。今はもう扱ってないけど」
「そうなんですか」浩樹は少しショックを受けた。「それで、どんな人が買っていったかとか、覚えていますか?」
「うーん、もしかしてお客さん、探偵さんか何か?」
「あ、いえ」ちょっと訊きすぎたかなと思った。「あの、人探しをしていまして」
「人探しねえ。協力したいのは山々ですが、一年も前のことだし、お客さんいっぱい来る時期だから、いちいち誰が買ったかとか、覚えてないですよ」
「そうですか。ありがとうございます」
「その人、見つかるといいですね」
浩樹は電話を切った。
見つかるといい、か。果たして本当にそうだろうか。
浩樹の頭の中には、ひとつの推理が出来上がろうとしていた。
胸糞悪い、けれど、それを責めることもできない、ひとつの真実──。
★
戸倉葉子はその日、夜勤明けで、午前中を寝て過ごしていた。
けたたましいコール音に起こされたのが、正午少し前。携帯電話のサブディスプレイには、「戸倉実花」と表示されていた。
咳をひとつしてから通話ボタンを押すと、聞きなれない男の声がした。
「戸倉葉子さんの携帯電話ですか?」
「はい、そうですが」
「失礼ですが、戸倉実花さんとはどういったご関係で?」
唐突になんだ、と葉子はムッとする。
「実花は姉ですが」
「そうですか。申し送れました。水平警察署の北山と申します。先ほど実花さんが交通事故にあわれ、緊急搬送されました。場所は……」
葉子は意識が遠のいていくような感覚を味わった。
メモをもとに病院に着くと、すぐに集中治療室に通された。実花はベッドに横たえられていた。頭や手足に巻かれた包帯が痛々しい。
「実花」
葉子は駆け寄り、力なく垂れ下がった彼女の手を握った。その冷たさにハッとする。
「実花、死なないで」
どんなに見つめても、彼女の目や口は開かなかった。
無機質な電子音が鳴った。医師が時刻を読み上げた。実花は死んだ。
「実花、実花、みかあああ」
医師から肩を叩かれるまで、葉子は姉の名を叫び続けた。
その後、事故の経緯について説明を受けた。葉子は上の空でそれを聞いた。
突っ込んできた車の運転手は、運転中に心臓発作を起こして死んでいたこと。
実花を助けようとして、突き飛ばしてくれた人がいたこと。
それでも間に合わず、二人とも轢かれてしまったこと。
その男性が、意識不明の重体で入院していること。
「あの」葉子は警察の説明を遮った。
ひとつだけ、聞き逃せないことがあった。
「姉が死んだってこと、その男性には内緒にしておいてもらえませんか」
葉子の胸には、このときひとつの決意があった。
☆
元宮浩樹は数日間の逡巡の末、組み立てた推理を葉子に突きつけてみることにした。
何も知らないふりを続けることなど耐えられないし、それにもしかしたら、推理が間違えているかもしれない。
間違いであってほしいと、彼は望んでいた。
「ねえ、葉子さん」
声をかけると、彼女は不自然なほどうろたえた。
「な、なんでしょう」
「訊きたいことがあるんだ。この間着ていたワンピースのことだけど、あれ、事故の日も着てたよね」
「え、そ、そうでしたっけ」
「うん。事故前の記憶はかなりとんでるんだけど、何故かぶつかる瞬間のことだけは、はっきり思い出せるんだ。俺が突き飛ばした女性が着ていたのは、花柄の白いワンピースだった」
「そ、それがいったい」
「まあ座りなよ」
葉子は向かいの椅子に腰掛けた。
「ちょっと聞いて。おかしなところがあったら指摘してよ」
浩樹はひとつ咳払いをした。
「あの日のワンピースと、この間のワンピースが同じものだったとする。すると、おかしなことになる。あれだけの事故で、服が血で汚れたり、破れたりしないわけがない。実際俺の服は全部使い物にならなくなったしね。汚れの目立つ白い服が、あんなに綺麗な状態で残っているはずがない」
「か、買ったんです。お気に入りだったから、もう一着買い直したんです」
「アントワープで? でも、あの服が店に並んでいたのは、去年の春シーズンだけだったはずだよ」
「調べたんですか?」
「うん」浩樹は葉子の目を見つめた。「真実が知りたかったからね」
葉子は目をそらす。「最初から二着買っていた、と私が言ったら、どうします?」
「その可能性も考えた。でも、同じ服を二着も買う女性はあまりいないだろう。それより俺は、もっとありえそうな説明に行き当たったよ。君は……」浩樹は少しだけ言いよどむ。「いや、君たちは、おそろいでワンピースを買ったんだ」
「君たち……?」
「そう、たぶん、姉妹だ」
葉子は顔を伏せた。表情を見られたくないのだろう。
「事故にあったのは、君じゃなく、お姉さんか妹さんの方だ」
浩樹は自分の推理が外れることを願っていた。しかし今の葉子を見れば、真実がどちらなのかは、明々白々だった。
「姉です」
葉子は静かに言った。
★
隠し通せるとなんて、思っていなかった。ワンピースの一件がなくたって、いずればれるはずの嘘だった。でも、本当のことを言うことが、葉子にはどうしてもできなかったのだ。
「お姉さんか……。君がこういうことをしているってことは、彼女はもう」
葉子は彼の目を見ないまま、頷いた。
「そうか。この推理、当たってほしくなかったんだけどな」
葉子は顔を上げることができなかった。
「彼女はあの事故で死んだ。俺は助けることができなかった。重大な後遺症を負ってまで助けようとした俺は、誰も助けることができなかった」
「いえ……」反論しなければ、と葉子は思った。しかしやっとのことで振り絞った声は、か細く、彼の耳には届かなかった。
「君はそんな俺を哀れんだ。英雄気取りで飛び込んで、何も守れず、ただ勝手に負傷しただけの馬鹿な男を、かわいそうだと思ったんだ。だから彼女が生きているように振舞って、俺を騙したんだ」
「そんな……」
「俺はとんだ裸の王様さ」
「ち」葉子は大きく息を吸い込んだ。「違う!」
浩樹は一瞬、ひるんだように見えた。
「何が違うんだ」
葉子は浩樹をまっすぐに見つめた。
「私は……いえ、私たちは、仲の良い姉妹でした」
語り始めれば、言葉はすらすらと出てきた。
「あのワンピースは、おっしゃる通り、お揃いで買ったものです。姉とは二つ離れていましたが、趣味も性格も一緒で、お互いの気持ちが手に取るようにわかりました。そうでなければ生きてこられませんでした。小さい頃に両親から裏切られて、そのせいで色んな人から酷い差別を受けました。頼れるのはお互いだけでした。誰も守ってなんかくれない。みんな自分のことしか考えていない。当たり前です。守ることは、大きなリスクを伴うんですから」
いつの間にか、葉子の頬を涙が伝っていた。
「私には」葉子は自分の声が震えているのに気がついた。
「私には、わかるんです。死の瞬間、姉がどんな気持ちでいたのか。姉は、嬉しかったと思うんです。危険を顧みず走ってきてくれたあなたの姿を見て、その手のひらの力強さを身体に感じて、初めて守ってもらえると思ったんです。それは生き延びることよりもずっと……。だから私は、もうお礼を言えなくなってしまった姉に代わって、あなたにお礼を言おうと誓いました。一生をかけてでも、お礼を言い続けようと」
「そうか……」
しばらく、二人とも黙っていた。継ぐべき言葉を探していた。そんな言葉などないとわかっていながら。
「ねえ」初めに口を開いたのは、浩樹の方だった。「お姉さんの名前は、なんていうんだい?」
葉子は手の甲で涙を拭った。
「実花、といいます。姉が花で、私が葉っぱ」
「へえ」浩樹は噛み締めるように、深く頷いた。「綺麗な名前だね。お姉さんも、君も」
「はい」
「今度、お姉さん……実花さんのお墓に連れて行ってくれないか。手を合わせたい」
葉子は微笑んだ。
「姉も喜ぶと思います。あの」
「なに?」
「これからも、その、そばにいて、いいですか?」
浩樹はあきれたようにため息をついた。
「俺は実花さんに誓うよ。葉子さんを一生守りますってね」
#big5#【この問題の正解】#/big5#
#b#事故にあったのは、ヨウコの姉のミカである。#/b#
#b#ヒロキは事故の際、ミカを助けようとして一緒に被害にあい、意識不明の重体となる。#/b#
#b#助けは間に合っておらず、ミカはその事故で命を落としてしまった。#/b#
#b#姉を助けるためにヒロキが重い後遺症を負ってしまったことを知ったヨウコ。#/b#
#b#彼に自分の行為が無駄であったと思わせたくなかったので、ヨウコは事故の被害者を演じ、ヒロキに救われたよう装った。#/b#
#big5#【真実】#/big5#
#b#ヨウコは、ミカが、自分を助けようとしてくれたヒロキに心から感謝しながら死んでいったのだと確信した。#/b#
#b#もうお礼を言うことのできないミカに代わり、自分が一生ヒロキにお礼を言い続けようと決意した。#/b#
田所多恵は、その事故の目撃者の一人である。
大学の講義の合間の暇をつぶそうと、ドーナツ屋のテラス席でコーヒーを飲んでいた。スマートフォンの電池残量が少なくなっていることに気付き、ゲームをやめてぼんやりと通りを眺めていたという。
昼前の時間帯で、人通りはまばらだった。ドーナツ屋は交差点に面しており、多恵の目の前には横断歩道がキャンパスの方まで伸びている。一人の女性が、その先で信号待ちをしていた。花柄の白いワンピースを着た背の高い女性で、「お花みたいな人」と多恵は表現した。
歩行者用の信号が青に変わって、ワンピースの女性が歩き出した。他に横断歩道を渡っている人はいなかった。
彼女が横断歩道の真ん中まで来たとき、多恵はふと、妙な胸騒ぎを覚えた。これは単なる予感じゃない、と、多恵は思ったという。視線を横に向けると、その違和感の正体がわかった。
交差点に差しかかろうとしている乗用車が、猛スピードのまま、まったく減速する様子を見せないのである。多恵がヤバいと思わず口にしたときには、すでに事は起きていた。
自分の方に向かってくる車に気付くも、足がすくんでしまった女性。
そこへ、どこからともなく一人の男性が走ってきて、彼女を突き飛ばした。
その瞬間、車が何かに当たる鈍い音が響いた。
車は車道をそれ、電信柱に激突して止まった。
多恵の目は、不自然な方向に脚を曲げ、血まみれで倒れている男性の姿をとらえていた。
「えっと、119番」
多恵は電池残量の少なくなったスマートフォンを起動した。
☆
悪夢から覚めたとき、元宮浩樹は左手にぬくもりを感じていた。誰かが手を握ってくれているのだとわかった。
目を開くと、そこには白いワンピース姿の女性が腰掛けていた。腰の辺りに大きな黄色の花がプリントされている。
彼女は彼の目を見て、ヒッと息を呑んだ。
「も、元宮さん」
誰だろう、と思った。それにここは、病院?
「ちょっと待っててください。今お医者さん呼んできます」
医師により脳波や心拍のチェックが行われた。いくつか簡単な質問もされた。
「軽い記憶障害があるようですが、脳に目立った異常は無いようですね。ここまで回復するとは、正直奇跡的です。ただし、運動機能に後遺症が残るかもしれません。リハビリは必ず行ってください」
浩樹は自分の腕や脚に包帯が巻かれていることに気付いた。
医師が去ると、ワンピースの女性がまた現れた。浩樹はとりあえず会釈した。
「元宮さん、意識が戻られて、本当に私、嬉しいです」
泣き出しそうな笑顔で彼女は言った。
「あの、気を悪くしたらごめん。俺ぜんぜん今の状況を把握できてないんだけど、えっと、あなたは、誰?」
「あ……」彼女は口元を手で押さえた。「そうですよね、ちゃんと説明しなくちゃ、混乱しますよね。交通事故のことは覚えてます?」
「交通事故……」
交通事故と聞いて、フラッシュバックする光景があった。迫りくる車、立ちすくむ女性、目の前に伸ばされた自分の腕。
「そうか、俺は車に轢かれたんだ」
「はい。あなたが助けてくださったのが、私です。戸倉葉子といいます」
「葉子さん」と、浩樹は繰り返した。「俺は、どれくらい眠っていたの?」
「三ヶ月、です」伏目がちにそう言った。
「あの」彼女は不意に立ち上がった。「まず、お礼を言わせてください。助けていただいて、本当にありがとうございました。このご恩は、必ず……」
深々と下げられた彼女の頭を、浩樹はしばらく見つめていた。
そこへ、浩樹の母親がやってきた。浩樹の姿を見るや否や、わんわんと泣き出した。ひとしきり泣いた後、今後の話になった。
「あなた、実家に戻らない? その身体だし、一人暮らしってわけにはいかないでしょう。お母さんもそんなに頻繁に行き来できないし」
「大学をやめてってことか?」
「大丈夫よ。就職先はお父さんがなんとかしてくれるから」
「大学はやめないよ、絶対。三ヶ月くらいの遅れなら、取り戻せる」
「そういうことじゃないでしょ、浩樹。生活はどうするのよ」
「どうにでもなるさ」
「浩樹」
守られすぎている、と思っていた。幼い頃から、望めば何でも買ってもらえた。生活に不自由は何もなかった。失敗はすべて許された。出来心で万引きをしてしまった日も、ストレスのせいだと解釈され、父親によってうやむやにされた。大学も、親のコネで一流のところに入れてやると言われた。浩樹はそれを断り、勉強した。一流とはいえないが、そこそこ名のある大学に合格した。
生まれて初めて、自分で勝ち取ったものだった。
「あの」
母親ではない女性の声がした。見ると、ワンピースの女性。さっき、葉子と名乗っていた。
「私が、浩樹さんの生活のお手伝いをします。だから、こっちにいさせてあげてください」
母は目を丸くした。
「あなた、でも」
「浩樹さんに救っていただいた命です。一生かけてでも、恩返しがしたいんです。浩樹さんは、ご迷惑ですか?」
「いや……」浩樹は母親と葉子の顔を見比べた。「お願いするよ」
「浩樹あなた」
「母さん、気持ちを考えてみてくれよ。俺と、それからこの、葉子さんの」
「お願いします」葉子は母親に向かって頭を下げた。
母親は戸惑うような表情を浮かべた後、大きくため息をついた。
「わかったわ。でも、辛くなったらいつでも戻ってくるのよ。それから葉子さん、あんまり思いつめなくていいからね」
葉子が頭を上げた。母の肩越しに、彼女と目が合った。葉子は小さく笑った。浩樹も返事をするように、小さく笑った。
葉子との二人三脚の日々が始まった。
彼女はリハビリに辛抱強く付き合ってくれたし、大学の遅れを取り戻せるよう、ノートやプリントをかき集めてくれた。葉子は学部こそ違うが、同じ大学の同級生なのだという。
退院後も車イス生活を余儀なくされた浩樹のもとへ、葉子は毎日通って、あれこれと世話を焼いてくれた。
「あなたがいなかったら私は死んでいたんです。このくらい当然なんですよ」
葉子が何度も何度も感謝の気持ちを告げてくれるから、浩樹は頼りきっているという負い目を感じずに済んだ。
違和感に気付いたのは、次に葉子が花柄の白いワンピースを着てきた日であった。
「こんにちは、浩樹さん。今日もよろしくお願いします」
「ああ、よろしく……」
そう言いながら彼は、葉子のワンピースのすそを見ていた。
何か、おかしい。彼はそう思った。
「じゃあさっそく、掃除しちゃいますね」
葉子が掃除用具の置いてあるクローゼットを開けると、中のモップが倒れてきた。彼女はとっさに、腕を顔の前でクロスした。
「あ」と浩樹は思わずもらした。
「ごめんなさい、大きな音立てちゃって。どうかしました?」
「いや」思いついたことがあった。「ねえそのワンピース、どこで買ったの?」
★
「ねえそのワンピース、どこで買ったの?」
そう問いかける元宮浩樹の目には、いつもと違うシリアスな光があった。
「え、どうしてですか?」
「いや、よく似合っているからさ。センスのいい店なんだろうなって」
「えっと、小杉にある、アントワープっていう小さなお店です」
「アントワープ、ね。ありがとう」
「いえ……あ、じゃあ掃除しちゃいますね」
家具の上のほこりを払いながら、葉子は思った。自分は何か失敗をしてしまったのではないか。
知らず、葉子はあの事故のことを思い返していた。
事故現場は凄惨だった。電信柱に突っ込み大破した車。群がる人々。車道の真ん中で、大量の血を流して倒れている男性。そして……。
葉子は頭を振る。もう夢の中で何度も見てきた映像だ。本当は忘れてしまいたかった。
しかしどんなに頭を振っても、今思い浮かべてしまった光景は離れてくれない。
回想の中、彼女はまるで幽霊のように、現場を俯瞰で見ていた。
と、彼女は何か、気付いてはいけないものに気付いた気がした。今の俯瞰図に、おかしなところがある。どこだ、どこ……。
葉子の手からはたきが落ちた。
現場に倒れている女性。着ているのは……。
血に染まった白いワンピース……。
☆
葉子が帰った後、浩樹は「アントワープ」をインターネットで調べ、電話をかけた。
「はい、アントワープです」
「あの、お尋ねしたいことがありまして」
「なんでしょう」
「そちらで、白いワンピースを扱っているでしょう?」
「白いワンピース、ですか」
「ほら、大きな花が付いていて……」浩樹は思い出せる限りの特徴を並べた。
「ああ」電話の向こうの男は、声のトーンを少し上げた。「去年の春、そんなのを入れた覚えがあります。今はもう扱ってないけど」
「そうなんですか」浩樹は少しショックを受けた。「それで、どんな人が買っていったかとか、覚えていますか?」
「うーん、もしかしてお客さん、探偵さんか何か?」
「あ、いえ」ちょっと訊きすぎたかなと思った。「あの、人探しをしていまして」
「人探しねえ。協力したいのは山々ですが、一年も前のことだし、お客さんいっぱい来る時期だから、いちいち誰が買ったかとか、覚えてないですよ」
「そうですか。ありがとうございます」
「その人、見つかるといいですね」
浩樹は電話を切った。
見つかるといい、か。果たして本当にそうだろうか。
浩樹の頭の中には、ひとつの推理が出来上がろうとしていた。
胸糞悪い、けれど、それを責めることもできない、ひとつの真実──。
★
戸倉葉子はその日、夜勤明けで、午前中を寝て過ごしていた。
けたたましいコール音に起こされたのが、正午少し前。携帯電話のサブディスプレイには、「戸倉実花」と表示されていた。
咳をひとつしてから通話ボタンを押すと、聞きなれない男の声がした。
「戸倉葉子さんの携帯電話ですか?」
「はい、そうですが」
「失礼ですが、戸倉実花さんとはどういったご関係で?」
唐突になんだ、と葉子はムッとする。
「実花は姉ですが」
「そうですか。申し送れました。水平警察署の北山と申します。先ほど実花さんが交通事故にあわれ、緊急搬送されました。場所は……」
葉子は意識が遠のいていくような感覚を味わった。
メモをもとに病院に着くと、すぐに集中治療室に通された。実花はベッドに横たえられていた。頭や手足に巻かれた包帯が痛々しい。
「実花」
葉子は駆け寄り、力なく垂れ下がった彼女の手を握った。その冷たさにハッとする。
「実花、死なないで」
どんなに見つめても、彼女の目や口は開かなかった。
無機質な電子音が鳴った。医師が時刻を読み上げた。実花は死んだ。
「実花、実花、みかあああ」
医師から肩を叩かれるまで、葉子は姉の名を叫び続けた。
その後、事故の経緯について説明を受けた。葉子は上の空でそれを聞いた。
突っ込んできた車の運転手は、運転中に心臓発作を起こして死んでいたこと。
実花を助けようとして、突き飛ばしてくれた人がいたこと。
それでも間に合わず、二人とも轢かれてしまったこと。
その男性が、意識不明の重体で入院していること。
「あの」葉子は警察の説明を遮った。
ひとつだけ、聞き逃せないことがあった。
「姉が死んだってこと、その男性には内緒にしておいてもらえませんか」
葉子の胸には、このときひとつの決意があった。
☆
元宮浩樹は数日間の逡巡の末、組み立てた推理を葉子に突きつけてみることにした。
何も知らないふりを続けることなど耐えられないし、それにもしかしたら、推理が間違えているかもしれない。
間違いであってほしいと、彼は望んでいた。
「ねえ、葉子さん」
声をかけると、彼女は不自然なほどうろたえた。
「な、なんでしょう」
「訊きたいことがあるんだ。この間着ていたワンピースのことだけど、あれ、事故の日も着てたよね」
「え、そ、そうでしたっけ」
「うん。事故前の記憶はかなりとんでるんだけど、何故かぶつかる瞬間のことだけは、はっきり思い出せるんだ。俺が突き飛ばした女性が着ていたのは、花柄の白いワンピースだった」
「そ、それがいったい」
「まあ座りなよ」
葉子は向かいの椅子に腰掛けた。
「ちょっと聞いて。おかしなところがあったら指摘してよ」
浩樹はひとつ咳払いをした。
「あの日のワンピースと、この間のワンピースが同じものだったとする。すると、おかしなことになる。あれだけの事故で、服が血で汚れたり、破れたりしないわけがない。実際俺の服は全部使い物にならなくなったしね。汚れの目立つ白い服が、あんなに綺麗な状態で残っているはずがない」
「か、買ったんです。お気に入りだったから、もう一着買い直したんです」
「アントワープで? でも、あの服が店に並んでいたのは、去年の春シーズンだけだったはずだよ」
「調べたんですか?」
「うん」浩樹は葉子の目を見つめた。「真実が知りたかったからね」
葉子は目をそらす。「最初から二着買っていた、と私が言ったら、どうします?」
「その可能性も考えた。でも、同じ服を二着も買う女性はあまりいないだろう。それより俺は、もっとありえそうな説明に行き当たったよ。君は……」浩樹は少しだけ言いよどむ。「いや、君たちは、おそろいでワンピースを買ったんだ」
「君たち……?」
「そう、たぶん、姉妹だ」
葉子は顔を伏せた。表情を見られたくないのだろう。
「事故にあったのは、君じゃなく、お姉さんか妹さんの方だ」
浩樹は自分の推理が外れることを願っていた。しかし今の葉子を見れば、真実がどちらなのかは、明々白々だった。
「姉です」
葉子は静かに言った。
★
隠し通せるとなんて、思っていなかった。ワンピースの一件がなくたって、いずればれるはずの嘘だった。でも、本当のことを言うことが、葉子にはどうしてもできなかったのだ。
「お姉さんか……。君がこういうことをしているってことは、彼女はもう」
葉子は彼の目を見ないまま、頷いた。
「そうか。この推理、当たってほしくなかったんだけどな」
葉子は顔を上げることができなかった。
「彼女はあの事故で死んだ。俺は助けることができなかった。重大な後遺症を負ってまで助けようとした俺は、誰も助けることができなかった」
「いえ……」反論しなければ、と葉子は思った。しかしやっとのことで振り絞った声は、か細く、彼の耳には届かなかった。
「君はそんな俺を哀れんだ。英雄気取りで飛び込んで、何も守れず、ただ勝手に負傷しただけの馬鹿な男を、かわいそうだと思ったんだ。だから彼女が生きているように振舞って、俺を騙したんだ」
「そんな……」
「俺はとんだ裸の王様さ」
「ち」葉子は大きく息を吸い込んだ。「違う!」
浩樹は一瞬、ひるんだように見えた。
「何が違うんだ」
葉子は浩樹をまっすぐに見つめた。
「私は……いえ、私たちは、仲の良い姉妹でした」
語り始めれば、言葉はすらすらと出てきた。
「あのワンピースは、おっしゃる通り、お揃いで買ったものです。姉とは二つ離れていましたが、趣味も性格も一緒で、お互いの気持ちが手に取るようにわかりました。そうでなければ生きてこられませんでした。小さい頃に両親から裏切られて、そのせいで色んな人から酷い差別を受けました。頼れるのはお互いだけでした。誰も守ってなんかくれない。みんな自分のことしか考えていない。当たり前です。守ることは、大きなリスクを伴うんですから」
いつの間にか、葉子の頬を涙が伝っていた。
「私には」葉子は自分の声が震えているのに気がついた。
「私には、わかるんです。死の瞬間、姉がどんな気持ちでいたのか。姉は、嬉しかったと思うんです。危険を顧みず走ってきてくれたあなたの姿を見て、その手のひらの力強さを身体に感じて、初めて守ってもらえると思ったんです。それは生き延びることよりもずっと……。だから私は、もうお礼を言えなくなってしまった姉に代わって、あなたにお礼を言おうと誓いました。一生をかけてでも、お礼を言い続けようと」
「そうか……」
しばらく、二人とも黙っていた。継ぐべき言葉を探していた。そんな言葉などないとわかっていながら。
「ねえ」初めに口を開いたのは、浩樹の方だった。「お姉さんの名前は、なんていうんだい?」
葉子は手の甲で涙を拭った。
「実花、といいます。姉が花で、私が葉っぱ」
「へえ」浩樹は噛み締めるように、深く頷いた。「綺麗な名前だね。お姉さんも、君も」
「はい」
「今度、お姉さん……実花さんのお墓に連れて行ってくれないか。手を合わせたい」
葉子は微笑んだ。
「姉も喜ぶと思います。あの」
「なに?」
「これからも、その、そばにいて、いいですか?」
浩樹はあきれたようにため息をついた。
「俺は実花さんに誓うよ。葉子さんを一生守りますってね」
#big5#【この問題の正解】#/big5#
#b#事故にあったのは、ヨウコの姉のミカである。#/b#
#b#ヒロキは事故の際、ミカを助けようとして一緒に被害にあい、意識不明の重体となる。#/b#
#b#助けは間に合っておらず、ミカはその事故で命を落としてしまった。#/b#
#b#姉を助けるためにヒロキが重い後遺症を負ってしまったことを知ったヨウコ。#/b#
#b#彼に自分の行為が無駄であったと思わせたくなかったので、ヨウコは事故の被害者を演じ、ヒロキに救われたよう装った。#/b#
#big5#【真実】#/big5#
#b#ヨウコは、ミカが、自分を助けようとしてくれたヒロキに心から感謝しながら死んでいったのだと確信した。#/b#
#b#もうお礼を言うことのできないミカに代わり、自分が一生ヒロキにお礼を言い続けようと決意した。#/b#
「【ウミガメのスープを解いたから…】」「9ブックマーク」
刑事「なんで、被害者を殺したんだ?」
加賀「奴がウミガメのスープを完璧に解いたからですよ」
刑事「どういうことだ?」
加賀「奴がウミガメのスープを完璧に解いたからですよ」
刑事「どういうことだ?」
16年02月22日 21:43
【ウミガメのスープ】 [東雲篠葉]
【ウミガメのスープ】 [東雲篠葉]
解説を見る
#red#※長いので下で要約してます#/red#
加賀「俺の親父が自殺したことは知ってますよね?」
刑事「ああ、自殺した理由は不明だったな」
加賀「俺本当は知ってるんですよ、自殺した理由。まあ、知っているというより推理したと言った方が正しいんですがね。親父と兄が昔、海難事故を起こして遭難したこと知ってますか?当然、知ってますよね。その時の話を親父から聞いてたわけですよ、俺は。親父は一緒に遭難した乗組員がウミガメを捕まえてくれてスープにして食べたから飢えを凌げて助かった。あいつらには本当に感謝してるって。ただ兄はその前に衰弱死してしまって本当にやりきれないって罪悪感をすごく感じてましたよ。まあ父親なら当たり前ですよね」
刑事「その話はもう20年前の話だろ?それが理由で自殺したならもっと早く自殺してたんじゃないか?」
加賀「刑事さん、親父が死ぬ前に何を食べたか知ってます?」
刑事「ウミガメのスープだろ?それがどうかしたか?」
加賀「察しが悪いなあ、だから自殺した理由を解けないんですよ。親父が遭難した時に食べたのはウミガメのスープ、そして死ぬ前に食べたのもウミガメのスープ。ちなみに親父は遭難した時から死ぬ前の20年間の間に俺の知っている限りはウミガメのスープを食してないですよ。まあ物が珍しいですから、当たり前と言えば当たり前ですけどね」
刑事「死ぬ前に思い出の味を食したって別に不思議ではないだろ」
加賀「本当に察しが悪いですね。じゃあもう一つヒント、親父は兄の死体を一度も見てない。そもそも親父が兄の死を知ったのは助けられた後なんですよ。乗組員たちは助けられるまでは兄のことを色々とごまかしてたんだそうです。そうじゃないと、息子の死体を見たら親父が自殺しかねないって乗組員たちが気を利かせたらしいんですが・・・、あと兄の死体は乗組員たちが弔ってくれたとも親父が言ってましたね」
刑事「おい、ウミガメのスープってまさか・・・」
加賀「流石に気づきましたか。あくまで俺の推測でしたけどね。ウミガメのスープは兄のスープだったって。それに親父は本物のウミガメのスープを飲んで気付いた。それだと自殺した理由に納得できません?」
刑事「ああ・・・、だがそれはあくまで推測だ。親父さんが勘違いしてたとも・・・」
加賀「だから真実を確かめるために乗組員たちとの飲みの席を用意したわけですよ。変に勘繰られないように、俺の知り合いも呼びましたけどね。それで皆が丁度いいでき具合になった時にね、ゲームを提案したんですよ「俺の出す問題に答えられた人の今日の飲み代は俺が持ちます」って。それで俺が推理した親父の自殺理由を答えにした問題を出したんです。
『とある海辺のレストランに男が入店しウミガメのスープを注文した。男はウミガメのスープを一口飲むとウェイターを呼び「これは本当にウミガメのスープですか?」と問いかけた。ウェイターは「さようでございます」と答えた。それを聞いた男は店を後にし自殺した。いったい何故?』
こんな問題だったかな。あとルールとしてYESNOで答えられる質問なら俺に質問をしても良いってルールを付けた。最初はみんな何のこっちゃ分からないわけですよ。親父の自殺の詳しい経緯までは、乗組員も含めてみんな知らないですからね。でも、誰だったかなあ「男の過去は重要ですか?」って質問をしてきた人がいてね、俺が「YES!良い質問だ」って答えたら、一人の乗組員がねどんどんいい質問を投げかけるようになったんですよ「海は関係ありますか?」とか「男は海難事故を起こしたことがありますか?」とか。その質問した後だったかなその乗組員が問題の答えを言い始めたんですよ。それも完璧すぎるほどに。答えてる途中に親父のことだって気付かないのもどうかと思いますが」
刑事「その時のことを知っているから、簡単に答えられるわけか。それで、お前の推理が真実だと分かったから復讐をしたのか?」
加賀「それ位だったら留まれますよ。だって正しいって予想してたわけですから。真実を確かめたかっただけで殺す気もなかったしね。ただね、俺の推理、用意した解答を凌駕して完璧に答えちゃったら流石の俺も頭に血が上っちゃって耐えられなくなりましたね」
刑事「どういうことだ?」
加賀「奴が言った解答はね
『男は、過去に海難事故を起こして仲間や息子と共に遭難してた。#red#食料が島にほとんど無かったから俺は弱っていた男の息子を殺してスープにした。#/red#その時、流石に悪いと思った乗組員は男にもウミガメのスープだと偽って飲ませることにした。その後男は無事に救助された。それで、助かった後に本当のウミガメのスープを食べた男は、遭難した時に食べたスープは自分の息子だと気づいて自殺してしまった』」
刑事「『食料が島にほとんど無かったから#red#俺は#/red#弱っていた男の息子を殺してスープにした。』って」
加賀「語るに落ちるとはこのことですよ。『俺』って…、途中で『乗組員』って言い換えてますけどもう遅い」
刑事「……」
加賀「弱っていたとはいえ兄は生きてたんですよ!それを殺してスープにした!?挙句の果てにはそれを親父に食わせた!?流石にこんな話聞かされたら、あんただって頭に血が上るでしょ?他の乗組員もビックリしてましたね。多分、殺したっていうのは誰にも教えてなかったんでしょう」
刑事「……」
加賀「その時、俺が正気だったかどうかなんて分かりませんが、動機は分かってもらえましたか?」
要約
加賀は父親が自殺した理由を確かめるために、自分の推理を「ウミガメのスープ」という問題として一緒に遭難した乗組員たちの前で出した。
それを答えた被害者(一緒に遭難した乗組員の一人)が用意していた答えを超える真実(#red#スープにした息子は俺が殺した#/red#)を吐いたため、加賀はカッとなり殺してしまった。
加賀「俺の親父が自殺したことは知ってますよね?」
刑事「ああ、自殺した理由は不明だったな」
加賀「俺本当は知ってるんですよ、自殺した理由。まあ、知っているというより推理したと言った方が正しいんですがね。親父と兄が昔、海難事故を起こして遭難したこと知ってますか?当然、知ってますよね。その時の話を親父から聞いてたわけですよ、俺は。親父は一緒に遭難した乗組員がウミガメを捕まえてくれてスープにして食べたから飢えを凌げて助かった。あいつらには本当に感謝してるって。ただ兄はその前に衰弱死してしまって本当にやりきれないって罪悪感をすごく感じてましたよ。まあ父親なら当たり前ですよね」
刑事「その話はもう20年前の話だろ?それが理由で自殺したならもっと早く自殺してたんじゃないか?」
加賀「刑事さん、親父が死ぬ前に何を食べたか知ってます?」
刑事「ウミガメのスープだろ?それがどうかしたか?」
加賀「察しが悪いなあ、だから自殺した理由を解けないんですよ。親父が遭難した時に食べたのはウミガメのスープ、そして死ぬ前に食べたのもウミガメのスープ。ちなみに親父は遭難した時から死ぬ前の20年間の間に俺の知っている限りはウミガメのスープを食してないですよ。まあ物が珍しいですから、当たり前と言えば当たり前ですけどね」
刑事「死ぬ前に思い出の味を食したって別に不思議ではないだろ」
加賀「本当に察しが悪いですね。じゃあもう一つヒント、親父は兄の死体を一度も見てない。そもそも親父が兄の死を知ったのは助けられた後なんですよ。乗組員たちは助けられるまでは兄のことを色々とごまかしてたんだそうです。そうじゃないと、息子の死体を見たら親父が自殺しかねないって乗組員たちが気を利かせたらしいんですが・・・、あと兄の死体は乗組員たちが弔ってくれたとも親父が言ってましたね」
刑事「おい、ウミガメのスープってまさか・・・」
加賀「流石に気づきましたか。あくまで俺の推測でしたけどね。ウミガメのスープは兄のスープだったって。それに親父は本物のウミガメのスープを飲んで気付いた。それだと自殺した理由に納得できません?」
刑事「ああ・・・、だがそれはあくまで推測だ。親父さんが勘違いしてたとも・・・」
加賀「だから真実を確かめるために乗組員たちとの飲みの席を用意したわけですよ。変に勘繰られないように、俺の知り合いも呼びましたけどね。それで皆が丁度いいでき具合になった時にね、ゲームを提案したんですよ「俺の出す問題に答えられた人の今日の飲み代は俺が持ちます」って。それで俺が推理した親父の自殺理由を答えにした問題を出したんです。
『とある海辺のレストランに男が入店しウミガメのスープを注文した。男はウミガメのスープを一口飲むとウェイターを呼び「これは本当にウミガメのスープですか?」と問いかけた。ウェイターは「さようでございます」と答えた。それを聞いた男は店を後にし自殺した。いったい何故?』
こんな問題だったかな。あとルールとしてYESNOで答えられる質問なら俺に質問をしても良いってルールを付けた。最初はみんな何のこっちゃ分からないわけですよ。親父の自殺の詳しい経緯までは、乗組員も含めてみんな知らないですからね。でも、誰だったかなあ「男の過去は重要ですか?」って質問をしてきた人がいてね、俺が「YES!良い質問だ」って答えたら、一人の乗組員がねどんどんいい質問を投げかけるようになったんですよ「海は関係ありますか?」とか「男は海難事故を起こしたことがありますか?」とか。その質問した後だったかなその乗組員が問題の答えを言い始めたんですよ。それも完璧すぎるほどに。答えてる途中に親父のことだって気付かないのもどうかと思いますが」
刑事「その時のことを知っているから、簡単に答えられるわけか。それで、お前の推理が真実だと分かったから復讐をしたのか?」
加賀「それ位だったら留まれますよ。だって正しいって予想してたわけですから。真実を確かめたかっただけで殺す気もなかったしね。ただね、俺の推理、用意した解答を凌駕して完璧に答えちゃったら流石の俺も頭に血が上っちゃって耐えられなくなりましたね」
刑事「どういうことだ?」
加賀「奴が言った解答はね
『男は、過去に海難事故を起こして仲間や息子と共に遭難してた。#red#食料が島にほとんど無かったから俺は弱っていた男の息子を殺してスープにした。#/red#その時、流石に悪いと思った乗組員は男にもウミガメのスープだと偽って飲ませることにした。その後男は無事に救助された。それで、助かった後に本当のウミガメのスープを食べた男は、遭難した時に食べたスープは自分の息子だと気づいて自殺してしまった』」
刑事「『食料が島にほとんど無かったから#red#俺は#/red#弱っていた男の息子を殺してスープにした。』って」
加賀「語るに落ちるとはこのことですよ。『俺』って…、途中で『乗組員』って言い換えてますけどもう遅い」
刑事「……」
加賀「弱っていたとはいえ兄は生きてたんですよ!それを殺してスープにした!?挙句の果てにはそれを親父に食わせた!?流石にこんな話聞かされたら、あんただって頭に血が上るでしょ?他の乗組員もビックリしてましたね。多分、殺したっていうのは誰にも教えてなかったんでしょう」
刑事「……」
加賀「その時、俺が正気だったかどうかなんて分かりませんが、動機は分かってもらえましたか?」
要約
加賀は父親が自殺した理由を確かめるために、自分の推理を「ウミガメのスープ」という問題として一緒に遭難した乗組員たちの前で出した。
それを答えた被害者(一緒に遭難した乗組員の一人)が用意していた答えを超える真実(#red#スープにした息子は俺が殺した#/red#)を吐いたため、加賀はカッとなり殺してしまった。
「【ラテクエ62-2】 ピンク」「9ブックマーク」
ラテラル大学の食堂で生姜焼き定食を食べた生徒のほとんどが
花粉症になったと報告が上がった。
しかし大学側はこれと言った対策は行わず生徒たちを笑っていた。
一体なぜ?
花粉症になったと報告が上がった。
しかし大学側はこれと言った対策は行わず生徒たちを笑っていた。
一体なぜ?
16年03月27日 20:11
【ウミガメのスープ】 [天童 魔子]
【ウミガメのスープ】 [天童 魔子]
解説を見る
私達のクラスにピーちゃんがやってきた。 (´・ω・`)ピー
生き物の命の大切さを知るため
私達はこれからピーちゃんを飼育し
#red#食べなければならない。#/red#
ピーちゃんの飼育は本当に大変だった。(´・ω・`)ピー
だけどもいつの間にか嫌いじゃなかった。(´・ω・`)ピー
クラスのみんなはピーちゃんが好きだった。(´・ω・`)ピー
何かもめ事があると真っ先にピーちゃんが止めに入り(´・ω・`)ピー
孤独な時は相談を聞いたりもしてくれた。(´・ω・`)ピー
そして
ピーちゃんを食べる時が来た。
当然クラスはピーちゃんを食べることに反対派と推奨派に分かれて大揉めした。
この頃にはもうクラスのみんなにも愛着が出来てしまい
いざ処分するとなると可哀想で出来ないと言う生徒と
それは人間のエゴだ。ピーちゃんの存在意義を考えれば食べてやることが最大の敬意となるっと
意見をお互いに譲らなかった。
クラスはこのままバラバラになってしまうと感じた時
それを止めたのもピーちゃんだった。(´・ω・`)ピー
大きくなった重そうな身体をゆっくり振るわせ
ピーちゃんはクラスの仲裁に入った。(´・ω・`)ピーピー
(みんな・・・・ケンカはやめて・・・・・いつもみたいに仲よくしよう・・・・・・)
当然ピーちゃんは喋れないが
ピーちゃんの目には自分の事よりもクラスのみんなを気遣う優しさに満ちていた。
そしてピーちゃんはまるで分っているかのように自分の足で食べる事推奨の元へ向かいクラス皆を見回した。
こうしてピーちゃんの意思を尊重すると言う結論に至りピーちゃんは出荷されていった。
だけどお別れの言葉は無かった。
クラスのみんなで話し合って決めたのだ。
ピーちゃんにサヨナラなんて言わない。
ピーちゃんは決して可哀想なんかじゃない
そして涙は見せないっと。
ピーちゃんは悲しむのが何より嫌うから
それにお別れなんてしたら泣いてしまう
そしてピーちゃんが豚肉となって戻ってきた。
それはスーパーで見る普通の豚肉だった。
大学の調理室で料理され
クラス皆で食べることになっていた。
とても美味しい生姜焼きとトン汁になってしまったピーちゃん。
ありがとう ありがとう ありがとう
一口する度に思い出が満ちてくてしまう
「あぁ~くそ。今日は花粉が多いな。」
男子が鼻水を垂らした。
「本当、花粉が多いね。」
女子が何度も目を擦った。
これは泣いているのではない花粉症のせいだ。
クシャミをする振りをして涙を拭う
先生たちは生徒たちの成長を感じて来年度から義務化しようと微笑んだのです。
生き物の命の大切さを知るため
私達はこれからピーちゃんを飼育し
#red#食べなければならない。#/red#
ピーちゃんの飼育は本当に大変だった。(´・ω・`)ピー
だけどもいつの間にか嫌いじゃなかった。(´・ω・`)ピー
クラスのみんなはピーちゃんが好きだった。(´・ω・`)ピー
何かもめ事があると真っ先にピーちゃんが止めに入り(´・ω・`)ピー
孤独な時は相談を聞いたりもしてくれた。(´・ω・`)ピー
そして
ピーちゃんを食べる時が来た。
当然クラスはピーちゃんを食べることに反対派と推奨派に分かれて大揉めした。
この頃にはもうクラスのみんなにも愛着が出来てしまい
いざ処分するとなると可哀想で出来ないと言う生徒と
それは人間のエゴだ。ピーちゃんの存在意義を考えれば食べてやることが最大の敬意となるっと
意見をお互いに譲らなかった。
クラスはこのままバラバラになってしまうと感じた時
それを止めたのもピーちゃんだった。(´・ω・`)ピー
大きくなった重そうな身体をゆっくり振るわせ
ピーちゃんはクラスの仲裁に入った。(´・ω・`)ピーピー
(みんな・・・・ケンカはやめて・・・・・いつもみたいに仲よくしよう・・・・・・)
当然ピーちゃんは喋れないが
ピーちゃんの目には自分の事よりもクラスのみんなを気遣う優しさに満ちていた。
そしてピーちゃんはまるで分っているかのように自分の足で食べる事推奨の元へ向かいクラス皆を見回した。
こうしてピーちゃんの意思を尊重すると言う結論に至りピーちゃんは出荷されていった。
だけどお別れの言葉は無かった。
クラスのみんなで話し合って決めたのだ。
ピーちゃんにサヨナラなんて言わない。
ピーちゃんは決して可哀想なんかじゃない
そして涙は見せないっと。
ピーちゃんは悲しむのが何より嫌うから
それにお別れなんてしたら泣いてしまう
そしてピーちゃんが豚肉となって戻ってきた。
それはスーパーで見る普通の豚肉だった。
大学の調理室で料理され
クラス皆で食べることになっていた。
とても美味しい生姜焼きとトン汁になってしまったピーちゃん。
ありがとう ありがとう ありがとう
一口する度に思い出が満ちてくてしまう
「あぁ~くそ。今日は花粉が多いな。」
男子が鼻水を垂らした。
「本当、花粉が多いね。」
女子が何度も目を擦った。
これは泣いているのではない花粉症のせいだ。
クシャミをする振りをして涙を拭う
先生たちは生徒たちの成長を感じて来年度から義務化しようと微笑んだのです。
「臥薪嘗胆」「9ブックマーク」
毎日毎食、彼の食事は同じメニューだ。
世界にはもっとうまいものがある? そんなことはわかってる。
たまには野菜も食べた方がいい? それがどうした。
すべては彼が生きるため、出口のない問いを続けた結果選んだ道なのだ。
どういうことだろう?

世界にはもっとうまいものがある? そんなことはわかってる。
たまには野菜も食べた方がいい? それがどうした。
すべては彼が生きるため、出口のない問いを続けた結果選んだ道なのだ。
どういうことだろう?
17年08月23日 23:40
【ウミガメのスープ】 [娘虎]
【ウミガメのスープ】 [娘虎]

原案:滝杉こげおさん。経緯は雑談欄にて。
解説を見る
彼は3年前、筏ごとクジラにのまれてしまった。
以来、脱出の方法を探している。
口の方からはいつも水が入り込み抜け出せない。
尻の方から出るのはクジラに本当に消化された時だ。
なら、どうするか。
出口がないなら作ってしまえと考えた彼は、
それから毎日クジラの肉を切り取って食べている。
いつかこの厚い体に大きな穴が開くと信じて。
以来、脱出の方法を探している。
口の方からはいつも水が入り込み抜け出せない。
尻の方から出るのはクジラに本当に消化された時だ。
なら、どうするか。
出口がないなら作ってしまえと考えた彼は、
それから毎日クジラの肉を切り取って食べている。
いつかこの厚い体に大きな穴が開くと信じて。