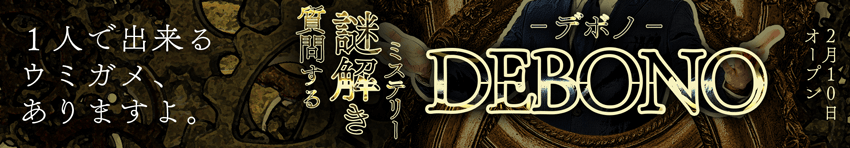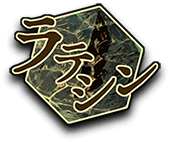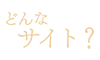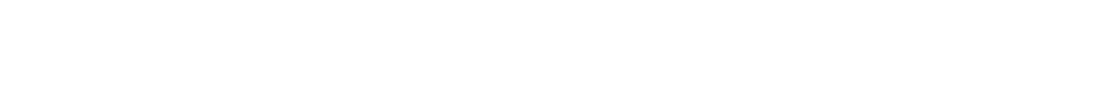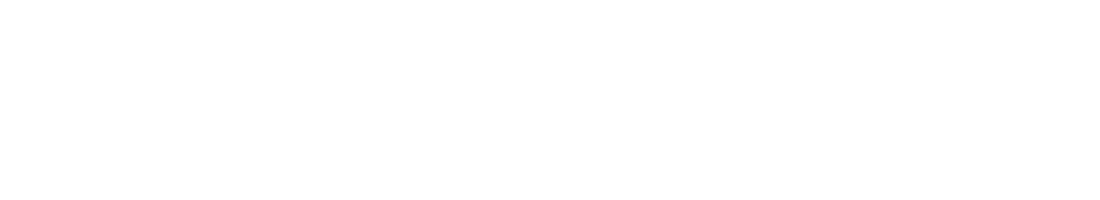項目についての説明はラテシンwiki!
時々ウミガメのスープ(問題ページ)
ある男が、とある海の見えるレストランで「ウミガメのスープ」を注文した。
男はそのスープを一口飲んだところで止め、シェフを呼んだ。
「これは本当にウミガメのスープですか?」
「はい。ウミガメのスープに間違いございません。」
「…そうですか…」
男はスプーンを置き、代金を払って店を出ると、自殺した。
状況を解き明かしてください。
男はそのスープを一口飲んだところで止め、シェフを呼んだ。
「これは本当にウミガメのスープですか?」
「はい。ウミガメのスープに間違いございません。」
「…そうですか…」
男はスプーンを置き、代金を払って店を出ると、自殺した。
状況を解き明かしてください。
15年12月14日 22:49
【ウミガメのスープ】 [えぜりん]
【ウミガメのスープ】 [えぜりん]
解説を見る
男は、嗅覚を失って絶望し、自殺を考えている元料理人である。(多分味覚障害が先に出ると思うが、それでもOK。)
もう料理の美味しさがわからなくなり、死ぬ前に、ライバルの作るスープに「マズい!」と言いたくて来店した。
だが男は丁重にもてなされて充分満足してしまい、結局何も文句が言えなかった。
あとは予定通り自殺。
以下、無駄に長い解説です。途中放棄OKです。
反省しています。今後は自重します。
美味しいウミガメのスープで有名な店の料理長であったその男は、非常に敏感で優れた感覚の持ち主で、的確な料理の評論家でもあった。
男は必要以上に正直であることでも知られていた。
本当は「嘘をつく能力が低かった」だけなのだが、他者には無遠慮で失礼なヤツだと思われていた。
男の辛辣な物言いは罵倒に等しく、通常の精神の持ち主には耐えられないほどで……それ故に、男は不幸になったのだ。
ある日、男は批判した相手に殴られ、転んだ拍子にしたたか頭を打ち付けた。
幸い命に別状はなかった…と普通なら言うべきところなのだろうが、男にとっては死んだ方がましだったのだろう。
男は軽い脳内出血が元で、完全に嗅覚を失ってしまったのだ。それは男に、常人の想像以上の絶望をもたらした。
実は嗅覚は味覚と密接な関係にある。味わいの大半は匂いであると言っても過言ではない。嗅覚が失われてしまうと、味は舌が感ずる五味だけになってしまう。
人間の嗅覚は他の動物の比較から鈍いと称されがちだなのだが、それでも一万種を嗅ぎ分ける奥深さを持つのだ。
男の損失はあまりにも大きかった。何を食べても味気なかった。
甘いとか、苦いとか、そういう本来の「味」はわかる。しかし白砂糖の甘味なのか穀物の甘味なのか、魚のわたの苦味なのか焦げ目の苦味なのか、どうしても区別することができないのだ。
もちろん男はもう料理人の仕事を続けることはできなかった。他人の料理を食して毒のような薬のような批評を吐き散らすこともできなくなった。
ここぞとばかりに反撃し始めた周囲の人間は、なけなしの男の生き甲斐をことごとく剥ぎ取った。
店も、瀟洒な豪邸もいつの間にか人手に渡っていた。
男の元に残っていたのは、少しばかりのカネと、小さな銀のティースプーンだけだった。
スプーンは料理人として初めての収入を得たときに買ったもので、それからというもの男は常にこれを持ち歩き、数限りない料理の味見をしたものだ。
だが、もうこのスプーンを使うこともない。
それでも男はどうしても手放すことができず、懐にしまいこんでいたのだ。
* * * * * * *
ある小雪のちらつく晩、男は海辺の街の道端に立っていた。
この冬一番の寒さが男の体を締め上げる。
今まで何とか生きてはきたが、経済的にも体力的にも、何より精神的に限界だった。何もかも終わりにしたかった。
最上級の味を知り尽くした男の、食に対する欲求と矜持はあまりに大きく、完全に男の生命力を押し潰してしまっていた。
わずかのうちにたちまち痩せ衰えた男を見て、かつて有名だったその名を思い出す者は誰もいない。
男はポケットの小銭を集めて手のひらの上で数えてみた。
「ああ、これは…」
男は自嘲気味にひとりごちた。
「ウミガメのスープ一杯分だな。」
そういえば、この近くに彼の店があったはずだと男は考えた。
若い頃から男が目標にし、後にライバルとして意識したが、ついぞ勝つことのできなかったシェフ。
男の夢は、シェフのウミガメのスープを飲んで「これではダメだ」と言ってやって、「俺のスープを飲んでみろ」と胸を張って差し出すことだった。
『もうそれも叶わない。』
そう思った時、ふと、男の情念に黒い炎が上がった。
『これはチャンスではないのか?』
料理を味わう能力を失った男だが、そんな今だからこそ心の底から言えるだろう。「このスープは不味い!」と。
「それを最後の晩餐としよう…」
男はつぶやき、件のレストランに向けて歩き出した。
* * * * * * *
雪は次第に激しさを増し、レストランに着く頃にはそこここに積もって宵闇を青く染めていた。
その中にぽっかりと、暖かな色のキャンドルライトが浮かんでいる。
男はあかぎれとしもやけで真っ赤になった手でドアを引いた。ふんわりとしたぬくもりが彼を包み、冷え切った体を潤した。
…以前の彼ならこの瞬間に店の客の食べている料理をすべて当てられたものだった。
ありとあらゆる素材の香りに包まれて、えも言われぬ至福を感じたのだ。
この店がスパイスの一つ一つまでこだわり、吟味しているということまでもが手に取るようにわかった。
でも今は何も感じなかった。
なめらかな身のこなしの給仕が、男を奥のテーブルに案内しようとした。男は首を横に降り、ドア横の小さなテーブルを指差した。
それは混んでいる時でも滅多に使われることのないテーブルだということを、男は知っていた。
だが、どうせスープだけ飲んで帰るのだ。そして、今から自分のしようとしていることを考えると…さすがに他の客の目を集めるような場所は避けたかった。
男はウミガメのスープを注文した。
ほどなくスープ皿が運ばれてきた。
いつも最高の香りで男を打ちのめしてきたスープが満たされている…はずだ。
スプーンを手に取ろうとして男は訝しんだ。それは木のスプーンだったのだ。
一瞬『俺には粗末な木のカトラリーで充分だと言いたいのか?』という台詞が浮かんだが、即時撤回した。
自分も料理人だったからわかる。これは明らかに、木製のスプーンの中では最も上等の代物だ。手入れも行き届いている。
持ってみると人肌程度のぬくもりが心地良い。太めの丸みを帯びた柄は、腫れて動かしにくい男の手にしっくり馴染み、また支えるのに苦労のいらぬ軽さであった。
スープに目をやると、白磁の器と澄んだ琥珀色のスープにキャンドルの灯りが揺れている。
添えられたハーブはすみずみまで張りつめ、あふれる生命力を感じさせる。
男は涙ぐんだ。こんな美しい料理は久しぶりだと思った。
いつも料理を前にすると香りと味とに全神経を集中させていた男は、今まで食器の手触りやスープの細かい見た目には気づかずにいたのだ。
この店は、料理の味以外でも一流のレストランだったのだと初めて気づいた。
だが味は。
スープを口に運んだ男の味蕾が捉えたのは、塩味とダシのうま味とわずかな甘味だけだった。
「これがあのウミガメのスープなのか?自分が目標とした最高級のスープなのか?」
たとえようもない寂しさが男を襲う。
しかしこのスープのなんと絶妙な温度だろう。
人の舌が耐えられるギリギリの熱さ。喉奥を温め、さらにじんわりと胸の下まで広がっていく温感に男は身をゆだねた。
男はしばし考えた。
自分の決心が揺らいでいるのを感じていたのだ。
だが思い切って給仕を呼んだ。
「シェフと話がしたいんだが。」
すぐに厨房からシェフが姿を見せ、男のテーブルにやって来た。なぜか歩き方がぎこちない。
「いらっしゃいませ。」
シェフはそれだけ言ってちょっと目をみはると、古い友人に微笑みかけるように目を細めた。男が誰なのか気付いたらしい。
「これは本当にウミガメのスープですか?」
固い声で男はたずねた。
「はい。ウミガメのスープに間違いございません。」
シェフの自信に満ちた、しかし衒(てら)いのない声を聞いたとき、男は自らの完全なる敗北を悟った。
間違いなくこのスープは、今の男にとって最高に旨いスープなのだ…と。
男は自問する。
『嗅覚のあった頃の、最盛期の自分に、このスープが作れただろうか?』
『否。五感がすべて正常に機能していたにも関わらず、目や手や皮膚感覚で味わうスープの旨さをまるっきり見過ごしてきたのではなかったか?』
『これでは勝てる道理がない。』
それに気づいてしまったからには、もう男にはスープを罵倒することなどとてもできなかった。
男はかすれた声で言った。
「…そうですか…」
そしてシェフに向かって深々と頭を下げた。
その時、男はシェフの右足が奇妙な形態をしているのに気がついた。
先程の歩き方はこのためだったのだ。シェフの右足は義足だった。
よく見ると右手の様子もだいぶおかしい。
多分シェフにとっても、年月は決して優しいそよ風ばかりではなかったのだ。
利き腕の機能を損なった後の数多の戦いの中から、シェフはさらなるもてなしの極意を拾い上げてきたに違いない。
持ちやすい木のスプーンも、シェフが自ら選定したのだろう。
顔をゆがめ、再びシェフの顔を見た男に向かい、今度はシェフがゆっくりと、深々と、最敬礼をした。
「いつも御来店ありがとうございます。どうぞごゆっくりおくつろぎください。」
常に男より前を歩いていたシェフの心からの謝意に、男はもう何も返すことができなかった。
ただただ、ゆっくりと厨房へと戻っていくシェフの背中を見送るばかりだった。
男は静かにスープを飲み、ウミガメの肉の歯ごたえや煮込まれた野菜の舌触りを味わった。
スープを最後まで飲み干そうとして、男はふと手を止め、懐からナフキンに包まれた細長いもの…駆け出しの料理人だった頃からの相棒だった銀のティースプーンを取り出した。
男はくすんだスプーンでスープを口に運び、つぶやく。
「今までありがとう。」
そして、わずかにスープの残った皿の中にスプーンをそっと横たわらせた。
男はポケットの中からすべての小銭を出し、スプーンを包んでいたナフキンに乗せてテーブルに置いた。
『これでもう、自分にはなにも残っていない。カネも未練も。なにもかも。』
来店前からボロボロだった男の自尊心はさらにすりつぶされてしまっていたが、細かい目のザルで丁寧に裏ごしされ、クリーミーなソースにしてもらえたような満足感があった。
* * * * * * *
男は扉を押し開け、店を出た。
雪はさらに激しく降り、男の髪に混じりこんだが、男は寒さを感じなかった。不思議な高揚感が男を包んでいる。
臓腑に収めたウミガメのスープも、中から男を温めてくれていた。
「今ならば。」
男は足元を見ながらつぶやく。
「今ならば笑って地獄に行けそうだ。」
人生の終着点でやっと自分の愚かさに気付いた男は、ただただ恥じ入るばかりであったが、それでもたったひとつだけ胸を張れることがあった。
『自分の目標としてあのシェフを選んだこと。結局足元にも及ばずに終わった自分だけど、彼を見出したことだけは褒められるべきだ。』
そう男は思った。
雪の積もった地面が途絶える。一歩先は崖の突端だ。
男は体ごと向き直り、もう遥か遠くなったレストランの明かりにもう一度深く頭を下げた。
顔をあげた時、男の顔は不思議と明るく、なごやかな笑みまで浮かべていた。
男は身を翻し、子どもが駆け出すような軽快な足裁きで、全く躊躇なく突端を越えた。
一瞬風が強くなる。
渦巻く雪と共に、男の体は暗い海面で消えた。
* * * * * * *
とある海の見えるレストランには、扉の横に小さなテーブルと椅子がある。
テーブルには、ちょっと擦り切れてはいるけれどパリッと糊の利いたナフキンが広げられ、その上にピカピカに磨かれたティースプーンがひとつ置いてある。
もう誰もその席に着くことはないのだが、なぜか時々、柔らかに湯気をたてるウミガメのスープが置かれているのだという。
【完】
もう料理の美味しさがわからなくなり、死ぬ前に、ライバルの作るスープに「マズい!」と言いたくて来店した。
だが男は丁重にもてなされて充分満足してしまい、結局何も文句が言えなかった。
あとは予定通り自殺。
以下、無駄に長い解説です。途中放棄OKです。
反省しています。今後は自重します。
美味しいウミガメのスープで有名な店の料理長であったその男は、非常に敏感で優れた感覚の持ち主で、的確な料理の評論家でもあった。
男は必要以上に正直であることでも知られていた。
本当は「嘘をつく能力が低かった」だけなのだが、他者には無遠慮で失礼なヤツだと思われていた。
男の辛辣な物言いは罵倒に等しく、通常の精神の持ち主には耐えられないほどで……それ故に、男は不幸になったのだ。
ある日、男は批判した相手に殴られ、転んだ拍子にしたたか頭を打ち付けた。
幸い命に別状はなかった…と普通なら言うべきところなのだろうが、男にとっては死んだ方がましだったのだろう。
男は軽い脳内出血が元で、完全に嗅覚を失ってしまったのだ。それは男に、常人の想像以上の絶望をもたらした。
実は嗅覚は味覚と密接な関係にある。味わいの大半は匂いであると言っても過言ではない。嗅覚が失われてしまうと、味は舌が感ずる五味だけになってしまう。
人間の嗅覚は他の動物の比較から鈍いと称されがちだなのだが、それでも一万種を嗅ぎ分ける奥深さを持つのだ。
男の損失はあまりにも大きかった。何を食べても味気なかった。
甘いとか、苦いとか、そういう本来の「味」はわかる。しかし白砂糖の甘味なのか穀物の甘味なのか、魚のわたの苦味なのか焦げ目の苦味なのか、どうしても区別することができないのだ。
もちろん男はもう料理人の仕事を続けることはできなかった。他人の料理を食して毒のような薬のような批評を吐き散らすこともできなくなった。
ここぞとばかりに反撃し始めた周囲の人間は、なけなしの男の生き甲斐をことごとく剥ぎ取った。
店も、瀟洒な豪邸もいつの間にか人手に渡っていた。
男の元に残っていたのは、少しばかりのカネと、小さな銀のティースプーンだけだった。
スプーンは料理人として初めての収入を得たときに買ったもので、それからというもの男は常にこれを持ち歩き、数限りない料理の味見をしたものだ。
だが、もうこのスプーンを使うこともない。
それでも男はどうしても手放すことができず、懐にしまいこんでいたのだ。
* * * * * * *
ある小雪のちらつく晩、男は海辺の街の道端に立っていた。
この冬一番の寒さが男の体を締め上げる。
今まで何とか生きてはきたが、経済的にも体力的にも、何より精神的に限界だった。何もかも終わりにしたかった。
最上級の味を知り尽くした男の、食に対する欲求と矜持はあまりに大きく、完全に男の生命力を押し潰してしまっていた。
わずかのうちにたちまち痩せ衰えた男を見て、かつて有名だったその名を思い出す者は誰もいない。
男はポケットの小銭を集めて手のひらの上で数えてみた。
「ああ、これは…」
男は自嘲気味にひとりごちた。
「ウミガメのスープ一杯分だな。」
そういえば、この近くに彼の店があったはずだと男は考えた。
若い頃から男が目標にし、後にライバルとして意識したが、ついぞ勝つことのできなかったシェフ。
男の夢は、シェフのウミガメのスープを飲んで「これではダメだ」と言ってやって、「俺のスープを飲んでみろ」と胸を張って差し出すことだった。
『もうそれも叶わない。』
そう思った時、ふと、男の情念に黒い炎が上がった。
『これはチャンスではないのか?』
料理を味わう能力を失った男だが、そんな今だからこそ心の底から言えるだろう。「このスープは不味い!」と。
「それを最後の晩餐としよう…」
男はつぶやき、件のレストランに向けて歩き出した。
* * * * * * *
雪は次第に激しさを増し、レストランに着く頃にはそこここに積もって宵闇を青く染めていた。
その中にぽっかりと、暖かな色のキャンドルライトが浮かんでいる。
男はあかぎれとしもやけで真っ赤になった手でドアを引いた。ふんわりとしたぬくもりが彼を包み、冷え切った体を潤した。
…以前の彼ならこの瞬間に店の客の食べている料理をすべて当てられたものだった。
ありとあらゆる素材の香りに包まれて、えも言われぬ至福を感じたのだ。
この店がスパイスの一つ一つまでこだわり、吟味しているということまでもが手に取るようにわかった。
でも今は何も感じなかった。
なめらかな身のこなしの給仕が、男を奥のテーブルに案内しようとした。男は首を横に降り、ドア横の小さなテーブルを指差した。
それは混んでいる時でも滅多に使われることのないテーブルだということを、男は知っていた。
だが、どうせスープだけ飲んで帰るのだ。そして、今から自分のしようとしていることを考えると…さすがに他の客の目を集めるような場所は避けたかった。
男はウミガメのスープを注文した。
ほどなくスープ皿が運ばれてきた。
いつも最高の香りで男を打ちのめしてきたスープが満たされている…はずだ。
スプーンを手に取ろうとして男は訝しんだ。それは木のスプーンだったのだ。
一瞬『俺には粗末な木のカトラリーで充分だと言いたいのか?』という台詞が浮かんだが、即時撤回した。
自分も料理人だったからわかる。これは明らかに、木製のスプーンの中では最も上等の代物だ。手入れも行き届いている。
持ってみると人肌程度のぬくもりが心地良い。太めの丸みを帯びた柄は、腫れて動かしにくい男の手にしっくり馴染み、また支えるのに苦労のいらぬ軽さであった。
スープに目をやると、白磁の器と澄んだ琥珀色のスープにキャンドルの灯りが揺れている。
添えられたハーブはすみずみまで張りつめ、あふれる生命力を感じさせる。
男は涙ぐんだ。こんな美しい料理は久しぶりだと思った。
いつも料理を前にすると香りと味とに全神経を集中させていた男は、今まで食器の手触りやスープの細かい見た目には気づかずにいたのだ。
この店は、料理の味以外でも一流のレストランだったのだと初めて気づいた。
だが味は。
スープを口に運んだ男の味蕾が捉えたのは、塩味とダシのうま味とわずかな甘味だけだった。
「これがあのウミガメのスープなのか?自分が目標とした最高級のスープなのか?」
たとえようもない寂しさが男を襲う。
しかしこのスープのなんと絶妙な温度だろう。
人の舌が耐えられるギリギリの熱さ。喉奥を温め、さらにじんわりと胸の下まで広がっていく温感に男は身をゆだねた。
男はしばし考えた。
自分の決心が揺らいでいるのを感じていたのだ。
だが思い切って給仕を呼んだ。
「シェフと話がしたいんだが。」
すぐに厨房からシェフが姿を見せ、男のテーブルにやって来た。なぜか歩き方がぎこちない。
「いらっしゃいませ。」
シェフはそれだけ言ってちょっと目をみはると、古い友人に微笑みかけるように目を細めた。男が誰なのか気付いたらしい。
「これは本当にウミガメのスープですか?」
固い声で男はたずねた。
「はい。ウミガメのスープに間違いございません。」
シェフの自信に満ちた、しかし衒(てら)いのない声を聞いたとき、男は自らの完全なる敗北を悟った。
間違いなくこのスープは、今の男にとって最高に旨いスープなのだ…と。
男は自問する。
『嗅覚のあった頃の、最盛期の自分に、このスープが作れただろうか?』
『否。五感がすべて正常に機能していたにも関わらず、目や手や皮膚感覚で味わうスープの旨さをまるっきり見過ごしてきたのではなかったか?』
『これでは勝てる道理がない。』
それに気づいてしまったからには、もう男にはスープを罵倒することなどとてもできなかった。
男はかすれた声で言った。
「…そうですか…」
そしてシェフに向かって深々と頭を下げた。
その時、男はシェフの右足が奇妙な形態をしているのに気がついた。
先程の歩き方はこのためだったのだ。シェフの右足は義足だった。
よく見ると右手の様子もだいぶおかしい。
多分シェフにとっても、年月は決して優しいそよ風ばかりではなかったのだ。
利き腕の機能を損なった後の数多の戦いの中から、シェフはさらなるもてなしの極意を拾い上げてきたに違いない。
持ちやすい木のスプーンも、シェフが自ら選定したのだろう。
顔をゆがめ、再びシェフの顔を見た男に向かい、今度はシェフがゆっくりと、深々と、最敬礼をした。
「いつも御来店ありがとうございます。どうぞごゆっくりおくつろぎください。」
常に男より前を歩いていたシェフの心からの謝意に、男はもう何も返すことができなかった。
ただただ、ゆっくりと厨房へと戻っていくシェフの背中を見送るばかりだった。
男は静かにスープを飲み、ウミガメの肉の歯ごたえや煮込まれた野菜の舌触りを味わった。
スープを最後まで飲み干そうとして、男はふと手を止め、懐からナフキンに包まれた細長いもの…駆け出しの料理人だった頃からの相棒だった銀のティースプーンを取り出した。
男はくすんだスプーンでスープを口に運び、つぶやく。
「今までありがとう。」
そして、わずかにスープの残った皿の中にスプーンをそっと横たわらせた。
男はポケットの中からすべての小銭を出し、スプーンを包んでいたナフキンに乗せてテーブルに置いた。
『これでもう、自分にはなにも残っていない。カネも未練も。なにもかも。』
来店前からボロボロだった男の自尊心はさらにすりつぶされてしまっていたが、細かい目のザルで丁寧に裏ごしされ、クリーミーなソースにしてもらえたような満足感があった。
* * * * * * *
男は扉を押し開け、店を出た。
雪はさらに激しく降り、男の髪に混じりこんだが、男は寒さを感じなかった。不思議な高揚感が男を包んでいる。
臓腑に収めたウミガメのスープも、中から男を温めてくれていた。
「今ならば。」
男は足元を見ながらつぶやく。
「今ならば笑って地獄に行けそうだ。」
人生の終着点でやっと自分の愚かさに気付いた男は、ただただ恥じ入るばかりであったが、それでもたったひとつだけ胸を張れることがあった。
『自分の目標としてあのシェフを選んだこと。結局足元にも及ばずに終わった自分だけど、彼を見出したことだけは褒められるべきだ。』
そう男は思った。
雪の積もった地面が途絶える。一歩先は崖の突端だ。
男は体ごと向き直り、もう遥か遠くなったレストランの明かりにもう一度深く頭を下げた。
顔をあげた時、男の顔は不思議と明るく、なごやかな笑みまで浮かべていた。
男は身を翻し、子どもが駆け出すような軽快な足裁きで、全く躊躇なく突端を越えた。
一瞬風が強くなる。
渦巻く雪と共に、男の体は暗い海面で消えた。
* * * * * * *
とある海の見えるレストランには、扉の横に小さなテーブルと椅子がある。
テーブルには、ちょっと擦り切れてはいるけれどパリッと糊の利いたナフキンが広げられ、その上にピカピカに磨かれたティースプーンがひとつ置いてある。
もう誰もその席に着くことはないのだが、なぜか時々、柔らかに湯気をたてるウミガメのスープが置かれているのだという。
【完】
総合点:2票 物語:2票
最初最後
物語部門エリム
【投票一覧】
【投票一覧】
「問題文はジャンルの由来ともなった有名問題。この題材をしっかりと膨らませ、独自の設定の物語が完成しています。これがまた非常に読みごたえがある1作。結末は問題文に描かれている通り悲しいものだが、登場人物の持つ誇りや温かさが描きこまれているので、後味の悪さがありません。スープのようにほっと染み入る作品です。」
2015年12月18日23時
物語部門牛削り
【投票一覧】
【投票一覧】
「行間のひとつひとつに、濃密な物語が隠されている。ウミガメのスープには、推理してトリックを解き明かす知的興奮を味わう楽しみ方と、小説として提示されるのとは違った緩急のある物語を堪能する楽しみ方との、二つがあると思う。後者の場合、物語重視ではあるが、小説ではなくウミガメのスープだからこそできる効果、というのが不可欠だろう。当問題は、問題文ですでに結末が明かされていて、そこに向かって主人公の心理がどう動くのかを質疑・解説で丹念に追いかけて行くという、この形式でなければ得られなかった楽しさが詰まっていた。」
2015年12月18日12時
最初最後