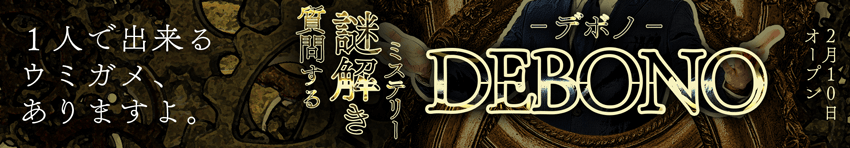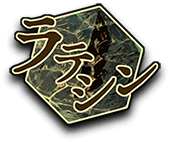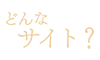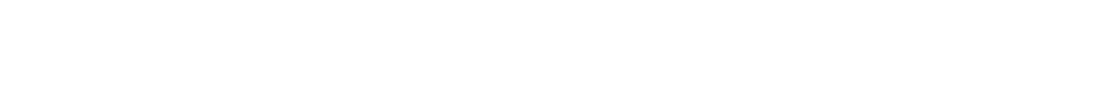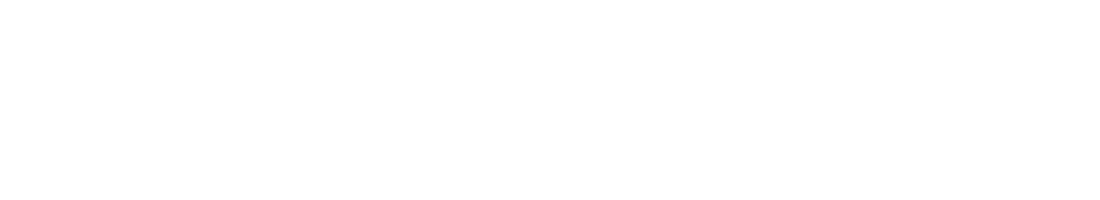項目についての説明はラテシンwiki!
千本ワインの毒(問題ページ)
千本のワインを前に、男は三人の息子達にこう投げかけた。
「ここに千本のワインがある。すべて同じ銘柄、同じ年のワインだ。このうち1本に毒を入れた。ワインを一滴でも飲めば24時間で死んでしまうほどの毒だ。毒自体に味はなく、24時間経たなければ毒入りワインを飲んだかどうか判別できない。毒見のためにうちの召使を何人使っても構わない。お前達は毒入りワインを見つけ出せるか?」
実直な父からの問いかけに、三人の息子達は一瞬顔を見合わせる。
生真面目な長男はすぐさま、「では私に千人の召使を与えてください」と願い出た。
ひねくれ者の次男はそれを聞いて、「俺は召使一人で十分だ」と言い放った。
最後に一番賢い三男が、「兄さん達には毒入りワインを見つけ出せないよ」と笑った。
三男はなぜそんなことを言ったのだろうか?
「ここに千本のワインがある。すべて同じ銘柄、同じ年のワインだ。このうち1本に毒を入れた。ワインを一滴でも飲めば24時間で死んでしまうほどの毒だ。毒自体に味はなく、24時間経たなければ毒入りワインを飲んだかどうか判別できない。毒見のためにうちの召使を何人使っても構わない。お前達は毒入りワインを見つけ出せるか?」
実直な父からの問いかけに、三人の息子達は一瞬顔を見合わせる。
生真面目な長男はすぐさま、「では私に千人の召使を与えてください」と願い出た。
ひねくれ者の次男はそれを聞いて、「俺は召使一人で十分だ」と言い放った。
最後に一番賢い三男が、「兄さん達には毒入りワインを見つけ出せないよ」と笑った。
三男はなぜそんなことを言ったのだろうか?
15年10月16日 23:12
【ウミガメのスープ】【批評OK】 [とかげ]
【ウミガメのスープ】【批評OK】 [とかげ]
解説を見る
父が呼んでいると執事から告げられ、三男が部屋にやってきたときには、既に長男と次男が緊張した面持ちで父と向き合っていた。父と二人の兄達の間に置かれたテーブルには、幾つものワインボトルが並んでおり、その不可思議な光景に思わず声をあげそうになったが、すべてを飲み込んで三男は空いた末席に腰を下ろした。
彼を連れてきた初老の執事が静かに扉を閉めると、父は三人の兄弟達と目線を合わせながら、低く響く声で語り始めた。
「今日、お前達を呼んだ理由は、薄々気づいているだろう。隠す必要もないので、はっきりと言っておく――私の跡継ぎを決めたいのだ」
三人の息子達は誰も驚いた様子がなく、ただ父の次の言葉を待っていた。
父は以前から、跡継ぎを誰にするか決めかねているという旨の発言を繰り返していた。そして実直で合理を好む父が、ただ長子だからという理由で長男を選ぶようなつまらない真似をしないことも、息子達にはわかっていた。
「お前達三人は、それぞれ良いところがある。お前達の誰が跡継ぎであっても、立派に責務をこなしてくれることを私は信じているし、三人で協力してくれるであろうこともわかっている。ただ、やはり正式な跡継ぎは一人だ。それはまだ私の頭が正常に働いてくれるうちに、決めておきたい」
父の言葉に、三人はただ頷いた。
ここで唐突に、父は目の前に並ぶワインに目を向けた。
「ここに千本のワインがある。すべて同じ銘柄、同じ年のワインだ。このうち1本に毒を入れた。ワインを一滴でも飲めば24時間で死んでしまうほどの毒だ。毒自体に味はなく、24時間経たなければ毒入りワインを飲んだかどうか判別できない。毒見のためにうちの召使を何人使っても構わない。お前達は毒入りワインを見つけ出せるか?」
突然の問いかけに、三人の息子達は一瞬顔を見合わせる。
跡継ぎの話とどう繋がるのか、わからないはずがなかった。
生真面目な長男はすぐさま、「では私に千人の召使を与えてください」と願い出た。
「我が家の召使は父上のためであれば命を捨てられる、忠誠心の強い者ばかりです。一人一本ずつ、毒見をさせます。24時間経てば一人死ぬでしょう。死んだ召使が飲んだワインが毒入りとわかります」
ひねくれ者の次男はそれを聞いて、「俺は召使一人で十分だ」と言い放った。
「一人の召使に、毎日一本ずつ毒見させるんだ。千本なら三年以内で終わる。時間はかかるが、召使を千人も使うなんていう非現実的な方法よりはよっぽどいいだろう」
「なんだって」
長男は不機嫌そうに次男を睨んだ。
「父上は何人でもと仰った。確かに我が家には千人も召使はいないが、一日だけなら雇えば良かろう。そもそも父上は迅速な仕事を好む。毒見に三年も費やす方が馬鹿げているのではないか?」
指摘された次男は、頬杖をついて長男の鋭い眼差しを遮った。
「確かに親父は召使のみならず、ここらの土地の住人達に慕われている。一日だけ雇うにしても人は集まるだろう。しかし、慈悲深い親父にとって、誰が死ぬかわからないような毒見は耐え難いはずさ。むしろ志願者を募り、一人だけ毒見させればいいじゃないか。第一、親父はこれが緊急の仕事であるとは言っていないぜ?」
父の意向を組もうとする彼らの発言に、父自身はイエスともノーとも答えない。
そんな彼らの様子を見守っていた一番賢い三男は、「兄さん達には毒入りワインを見つけ出せないよ」と笑った。
「どういうことだ」
「何か思いついたのか」
兄達の探るような視線にはあえて気付かぬ素振りで、三男は彼らの疑問に質問で返す。
「よく考えて見て欲しい。『迅速な仕事を好む』父さんが、千本のワインの中の一本だけに毒を混ぜるなんて、無意味なことをするのはなぜか。『慈悲深い』父さんが、召使とは言え必ず一人は死ななければならない毒見をさせようとするのはなぜか」
兄達へ向けたような言葉面だったが、三男の笑顔は沈黙を守る父に向けられていた。
「父さんは、『ワインを一滴でも飲めば24時間で死んでしまう』と言った。しかも、『毒自体に味はなく、24時間経たなければ毒入りワインを飲んだかどうか判別できない』……僕は毒に詳しいわけじゃないけれど、少し考えれば、おかしなことに気付くはずだ。そんな毒を、なぜ父さんが入手できたのだろう?」
兄二人は、要領を得ない様子で押し黙る。彼らのために、三男は続けた。
「ワインをたった一滴飲むだけで確実に死ぬほど強力で、しかもそれが24時間経つまでまったくわからないだなんて……そんな都合の良い毒、存在するのか? もし存在するとしても、医者でも薬剤師でもない父さんが手に入れられるんなら、今頃そこら中で毒殺事件が起こっているはずだよ」
父は無表情のまま、三男を見つめる。
「もしそんな毒が存在するのならば、正当な手段で入手できるはずがない。父さんは確かに地主で権力もあるし、金もある。けれど、兄さん達も知っての通り、父さんは本当に実直な人だ。不誠実なことを嫌う。正当に入手できるはずがない毒を、父さんが持っているはずがない」
ようやく三男の言いたいことがわかってきたのか、長男と次男は息をのんだ。
「どう考えたっておかしいんだ。三人の息子のうち誰に跡を継がせるかなんていう個人的な問題のために、わざわざそんな毒を不当に入手し、大切な召使を殺してしまうような余興を、父さんが好むわけがないじゃないか」
三男は立ち並ぶ千本のワインを指し示した。
「千本のワインの中に、毒入りワインは存在しない。だから兄さん達は、何人召使を雇おうとも、何年かかろうとも、毒入りワインを見つけ出せないよ」
しばし続いた静寂を打ち破ったのは、父の笑い声であった。
本当におかしそうに、そして本当に嬉しそうに、父は三男に優しい眼差しを向ける。
「その通りだ。やはりお前は賢いな。……生まれた順番こそ三番目だが、我が一族の当主に最も相応しい」
長男と次男に、もはや反論の余地はなかった。
「お前がこの家を継ぐといい」
父の宣言に、三男は恭しく一礼した。
「君のおかげだ」
寝床に入る三男の身支度を手伝っていた執事は、そんな三男――次期当主の言葉に、誇らしげに微笑んだ。
役目を終えた千本のワインは三男が貰い受け、先程まで三男と執事の二人で祝杯をあげていた。いつもより陽気な反応をする執事は、少々酔いが回っていたのだろう。
「ありがとうございます、そんな風に言って頂けるなんて、光栄です。しかし坊っちゃんの機転がなければ、私の情報など意味がないものでした」
長年この家に仕え、召使達を束ねてきた初老の執事にとって、人懐っこい三男は孫のような可愛い存在であった。数日前、三男にだけ「お父上から不思議な言い付けがありました」と伝えてしまったのも、ついつい三男贔屓してしまう執事のお節介であった。
執事から、「父上が同じ銘柄、同じ年のワインを千本用意するよう言われました。坊っちゃんたちには内密に、とも仰せでした」と聞いた三男は、最初は首をひねっていた。あの父は無意味にそんなことを言うような人ではない。銘柄や年に指定がないことから、父自身が飲みたいわけでも、誰かに贈りたいわけでもなさそうだ。執事によると、用意したワインを父自身が確認することもなく、ただ自分が声をかけるまで、息子達がわからないような場所へ隠しておけと言ったそうだ。隠し場所については、父自身も知らないはずだという。
色々と思慮を巡らせた末、もしかしたら、と跡継ぎ問題の件に思い至った。長男に譲るにしても、長男であること以外に何かしら理由をつけるはずだとは思っていたが、これはひょっとすると自分にも機会があるかもしれない、と。
千本のワインをどう使うつもりなのかは、もちろん父からの問いを聞くまでわからなかったが、先に情報を握っていた分、三男に有利であったことに間違いはない。
「兄さん達が死なない限り、さすがに三男の僕が跡を継ぐのは難しいだろうと思っていたが……」
「いえいえ、私は坊っちゃんが継ぐのが一番だと思っていましたよ。お兄様達ももちろん優秀な方々ですが……坊っちゃんには敵いますまい。お父上も、きっと坊ちゃんに目をかけていたに違いありませんよ」
「……本当に、君のおかげだ」
三男は、執事の両手を取り、爽やかにほほ笑んだ。執事は嬉しそうに頭を下げる。
「もったいないお言葉です、本当に、ただの世間話のつもりだったんです。私のおかげなんてもんじゃあありませんよ」
「いや、君のおかげだよ。君のおかげで――」
心なしか、三男の両手に力がこもる。
「――殺すのが一人で済んだ」
「そんな、もう……え?」
執事が顔をあげると、三男はやはり笑っていた。自分の聞き間違いか、飲み過ぎたのかもしれないと、執事は一瞬曇らせた表情をまた笑顔に変えようとしたが、なぜか口角が上がらない。
手を握ったまま、笑顔のまま、三男は歌うように語りかける。
「最低でも兄さん達二人を殺さねばと思っていたけれど、良かったよ。さすがに肉親を二人も殺すのは気が引けていたところなんだ」
「坊っちゃん……?」
「ほら、君もわかるだろう。父さんは不誠実なことが大嫌いだ。君がワインの件を僕に教えてくれていたということが知れたら、どうなると思う? もちろん、君が同じことを兄さん達に教えていたとしても、僕のようには頭が回らなかっただろう。しかし、君の情報が役に立ったことは事実だ。毒入りワインが存在しないと断定できたのは、君の情報があったからこそだ。父さんからすれば、僕達兄弟の状況は公平ではなかった。そして父さんは、そういったことを許さない。決して」
執事に言い聞かせるかのように、三男は顔を近づけ矢継ぎ早に続けていく。
「父さんが知ったら、僕を軽蔑するだろう。僕は今後一切の信用を失い、跡継ぎの話はなくなってしまう。父さんはそういう人だ。だから、念には念を入れねばなるまい」
ようやく、執事は三男の言葉の意図を理解した。突如湧きあがる恐怖。しかし、身体が思うように動かなかった。それは恐怖のせいだけではないし、ワインの余韻はとうに失せていた。
「毒が回ってきたかい? そうだよ、その毒を手に入れるのは易しくない。少量でも確実に死ぬほど強力で、けれど死ぬまでに時間がかかり、無味無臭であるような毒なんてね。少なくとも、正当な手段では得られない。だから、だからこそ、僕はすぐにわかったのだ。毒入りワインなんて存在しないということが」
息苦しい、と気付いたときには既に呼吸ができなくなっていた。執事は膝から崩れ落ちる。三男は、恐ろしいほど優しい手つきで、身動きがとれぬ老人を抱きとめ、ゆっくりと床に寝かせた。
深呼吸を一つして、可哀そうな執事が突然死したシナリオを頭の中で反芻する。執事に対する感謝の気持ちで、涙は自然と流せそうだ。
三男には、よくわかっていた。
あの千本のワインに、毒入りワインはないなんて嘘だ。
ワインの毒が確かに自分を犯しているのだから。
END
少量でも確実に死に、24時間気付かれないような都合の良い毒を、父が手に入れられるはずがないので、千本のワインの中に毒入りワインはないと推理したから
彼を連れてきた初老の執事が静かに扉を閉めると、父は三人の兄弟達と目線を合わせながら、低く響く声で語り始めた。
「今日、お前達を呼んだ理由は、薄々気づいているだろう。隠す必要もないので、はっきりと言っておく――私の跡継ぎを決めたいのだ」
三人の息子達は誰も驚いた様子がなく、ただ父の次の言葉を待っていた。
父は以前から、跡継ぎを誰にするか決めかねているという旨の発言を繰り返していた。そして実直で合理を好む父が、ただ長子だからという理由で長男を選ぶようなつまらない真似をしないことも、息子達にはわかっていた。
「お前達三人は、それぞれ良いところがある。お前達の誰が跡継ぎであっても、立派に責務をこなしてくれることを私は信じているし、三人で協力してくれるであろうこともわかっている。ただ、やはり正式な跡継ぎは一人だ。それはまだ私の頭が正常に働いてくれるうちに、決めておきたい」
父の言葉に、三人はただ頷いた。
ここで唐突に、父は目の前に並ぶワインに目を向けた。
「ここに千本のワインがある。すべて同じ銘柄、同じ年のワインだ。このうち1本に毒を入れた。ワインを一滴でも飲めば24時間で死んでしまうほどの毒だ。毒自体に味はなく、24時間経たなければ毒入りワインを飲んだかどうか判別できない。毒見のためにうちの召使を何人使っても構わない。お前達は毒入りワインを見つけ出せるか?」
突然の問いかけに、三人の息子達は一瞬顔を見合わせる。
跡継ぎの話とどう繋がるのか、わからないはずがなかった。
生真面目な長男はすぐさま、「では私に千人の召使を与えてください」と願い出た。
「我が家の召使は父上のためであれば命を捨てられる、忠誠心の強い者ばかりです。一人一本ずつ、毒見をさせます。24時間経てば一人死ぬでしょう。死んだ召使が飲んだワインが毒入りとわかります」
ひねくれ者の次男はそれを聞いて、「俺は召使一人で十分だ」と言い放った。
「一人の召使に、毎日一本ずつ毒見させるんだ。千本なら三年以内で終わる。時間はかかるが、召使を千人も使うなんていう非現実的な方法よりはよっぽどいいだろう」
「なんだって」
長男は不機嫌そうに次男を睨んだ。
「父上は何人でもと仰った。確かに我が家には千人も召使はいないが、一日だけなら雇えば良かろう。そもそも父上は迅速な仕事を好む。毒見に三年も費やす方が馬鹿げているのではないか?」
指摘された次男は、頬杖をついて長男の鋭い眼差しを遮った。
「確かに親父は召使のみならず、ここらの土地の住人達に慕われている。一日だけ雇うにしても人は集まるだろう。しかし、慈悲深い親父にとって、誰が死ぬかわからないような毒見は耐え難いはずさ。むしろ志願者を募り、一人だけ毒見させればいいじゃないか。第一、親父はこれが緊急の仕事であるとは言っていないぜ?」
父の意向を組もうとする彼らの発言に、父自身はイエスともノーとも答えない。
そんな彼らの様子を見守っていた一番賢い三男は、「兄さん達には毒入りワインを見つけ出せないよ」と笑った。
「どういうことだ」
「何か思いついたのか」
兄達の探るような視線にはあえて気付かぬ素振りで、三男は彼らの疑問に質問で返す。
「よく考えて見て欲しい。『迅速な仕事を好む』父さんが、千本のワインの中の一本だけに毒を混ぜるなんて、無意味なことをするのはなぜか。『慈悲深い』父さんが、召使とは言え必ず一人は死ななければならない毒見をさせようとするのはなぜか」
兄達へ向けたような言葉面だったが、三男の笑顔は沈黙を守る父に向けられていた。
「父さんは、『ワインを一滴でも飲めば24時間で死んでしまう』と言った。しかも、『毒自体に味はなく、24時間経たなければ毒入りワインを飲んだかどうか判別できない』……僕は毒に詳しいわけじゃないけれど、少し考えれば、おかしなことに気付くはずだ。そんな毒を、なぜ父さんが入手できたのだろう?」
兄二人は、要領を得ない様子で押し黙る。彼らのために、三男は続けた。
「ワインをたった一滴飲むだけで確実に死ぬほど強力で、しかもそれが24時間経つまでまったくわからないだなんて……そんな都合の良い毒、存在するのか? もし存在するとしても、医者でも薬剤師でもない父さんが手に入れられるんなら、今頃そこら中で毒殺事件が起こっているはずだよ」
父は無表情のまま、三男を見つめる。
「もしそんな毒が存在するのならば、正当な手段で入手できるはずがない。父さんは確かに地主で権力もあるし、金もある。けれど、兄さん達も知っての通り、父さんは本当に実直な人だ。不誠実なことを嫌う。正当に入手できるはずがない毒を、父さんが持っているはずがない」
ようやく三男の言いたいことがわかってきたのか、長男と次男は息をのんだ。
「どう考えたっておかしいんだ。三人の息子のうち誰に跡を継がせるかなんていう個人的な問題のために、わざわざそんな毒を不当に入手し、大切な召使を殺してしまうような余興を、父さんが好むわけがないじゃないか」
三男は立ち並ぶ千本のワインを指し示した。
「千本のワインの中に、毒入りワインは存在しない。だから兄さん達は、何人召使を雇おうとも、何年かかろうとも、毒入りワインを見つけ出せないよ」
しばし続いた静寂を打ち破ったのは、父の笑い声であった。
本当におかしそうに、そして本当に嬉しそうに、父は三男に優しい眼差しを向ける。
「その通りだ。やはりお前は賢いな。……生まれた順番こそ三番目だが、我が一族の当主に最も相応しい」
長男と次男に、もはや反論の余地はなかった。
「お前がこの家を継ぐといい」
父の宣言に、三男は恭しく一礼した。
「君のおかげだ」
寝床に入る三男の身支度を手伝っていた執事は、そんな三男――次期当主の言葉に、誇らしげに微笑んだ。
役目を終えた千本のワインは三男が貰い受け、先程まで三男と執事の二人で祝杯をあげていた。いつもより陽気な反応をする執事は、少々酔いが回っていたのだろう。
「ありがとうございます、そんな風に言って頂けるなんて、光栄です。しかし坊っちゃんの機転がなければ、私の情報など意味がないものでした」
長年この家に仕え、召使達を束ねてきた初老の執事にとって、人懐っこい三男は孫のような可愛い存在であった。数日前、三男にだけ「お父上から不思議な言い付けがありました」と伝えてしまったのも、ついつい三男贔屓してしまう執事のお節介であった。
執事から、「父上が同じ銘柄、同じ年のワインを千本用意するよう言われました。坊っちゃんたちには内密に、とも仰せでした」と聞いた三男は、最初は首をひねっていた。あの父は無意味にそんなことを言うような人ではない。銘柄や年に指定がないことから、父自身が飲みたいわけでも、誰かに贈りたいわけでもなさそうだ。執事によると、用意したワインを父自身が確認することもなく、ただ自分が声をかけるまで、息子達がわからないような場所へ隠しておけと言ったそうだ。隠し場所については、父自身も知らないはずだという。
色々と思慮を巡らせた末、もしかしたら、と跡継ぎ問題の件に思い至った。長男に譲るにしても、長男であること以外に何かしら理由をつけるはずだとは思っていたが、これはひょっとすると自分にも機会があるかもしれない、と。
千本のワインをどう使うつもりなのかは、もちろん父からの問いを聞くまでわからなかったが、先に情報を握っていた分、三男に有利であったことに間違いはない。
「兄さん達が死なない限り、さすがに三男の僕が跡を継ぐのは難しいだろうと思っていたが……」
「いえいえ、私は坊っちゃんが継ぐのが一番だと思っていましたよ。お兄様達ももちろん優秀な方々ですが……坊っちゃんには敵いますまい。お父上も、きっと坊ちゃんに目をかけていたに違いありませんよ」
「……本当に、君のおかげだ」
三男は、執事の両手を取り、爽やかにほほ笑んだ。執事は嬉しそうに頭を下げる。
「もったいないお言葉です、本当に、ただの世間話のつもりだったんです。私のおかげなんてもんじゃあありませんよ」
「いや、君のおかげだよ。君のおかげで――」
心なしか、三男の両手に力がこもる。
「――殺すのが一人で済んだ」
「そんな、もう……え?」
執事が顔をあげると、三男はやはり笑っていた。自分の聞き間違いか、飲み過ぎたのかもしれないと、執事は一瞬曇らせた表情をまた笑顔に変えようとしたが、なぜか口角が上がらない。
手を握ったまま、笑顔のまま、三男は歌うように語りかける。
「最低でも兄さん達二人を殺さねばと思っていたけれど、良かったよ。さすがに肉親を二人も殺すのは気が引けていたところなんだ」
「坊っちゃん……?」
「ほら、君もわかるだろう。父さんは不誠実なことが大嫌いだ。君がワインの件を僕に教えてくれていたということが知れたら、どうなると思う? もちろん、君が同じことを兄さん達に教えていたとしても、僕のようには頭が回らなかっただろう。しかし、君の情報が役に立ったことは事実だ。毒入りワインが存在しないと断定できたのは、君の情報があったからこそだ。父さんからすれば、僕達兄弟の状況は公平ではなかった。そして父さんは、そういったことを許さない。決して」
執事に言い聞かせるかのように、三男は顔を近づけ矢継ぎ早に続けていく。
「父さんが知ったら、僕を軽蔑するだろう。僕は今後一切の信用を失い、跡継ぎの話はなくなってしまう。父さんはそういう人だ。だから、念には念を入れねばなるまい」
ようやく、執事は三男の言葉の意図を理解した。突如湧きあがる恐怖。しかし、身体が思うように動かなかった。それは恐怖のせいだけではないし、ワインの余韻はとうに失せていた。
「毒が回ってきたかい? そうだよ、その毒を手に入れるのは易しくない。少量でも確実に死ぬほど強力で、けれど死ぬまでに時間がかかり、無味無臭であるような毒なんてね。少なくとも、正当な手段では得られない。だから、だからこそ、僕はすぐにわかったのだ。毒入りワインなんて存在しないということが」
息苦しい、と気付いたときには既に呼吸ができなくなっていた。執事は膝から崩れ落ちる。三男は、恐ろしいほど優しい手つきで、身動きがとれぬ老人を抱きとめ、ゆっくりと床に寝かせた。
深呼吸を一つして、可哀そうな執事が突然死したシナリオを頭の中で反芻する。執事に対する感謝の気持ちで、涙は自然と流せそうだ。
三男には、よくわかっていた。
あの千本のワインに、毒入りワインはないなんて嘘だ。
ワインの毒が確かに自分を犯しているのだから。
END
少量でも確実に死に、24時間気付かれないような都合の良い毒を、父が手に入れられるはずがないので、千本のワインの中に毒入りワインはないと推理したから
総合点:1票 トリック:1票
最初最後
最初最後