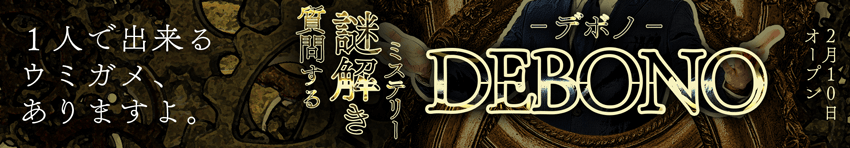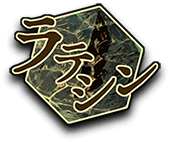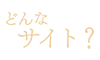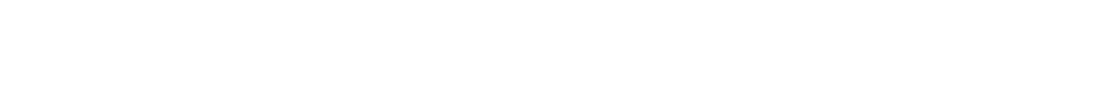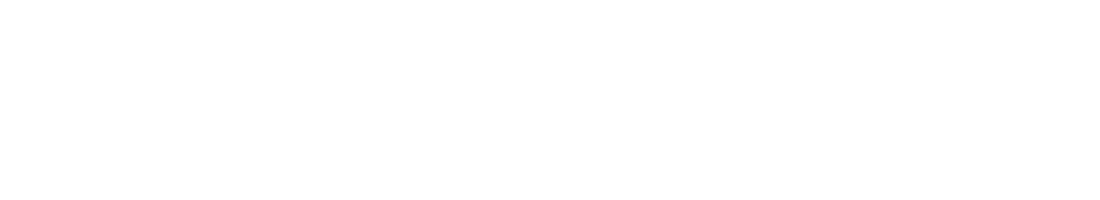作成者:黒井由紀
部屋名:ラテシンストーリー二次創作の館
ルームキー:ラテシン二次創作
部屋名:ラテシンストーリー二次創作の館
ルームキー:ラテシン二次創作
勝手に書いて勝手に公開しているだけで、公式とは一切関係ありません。また、独自設定も多分に含まれております。ご注意ください。
現在 黒井由紀さん が入室してます。(1人)
最初最後
【総発言数:19】
[334417]黒井由紀
以下の作品【「ラテシン」に捧ぐエピローグ】は、ラテシン公式ストーリーの二次創作作品でもありますが、
「 骸かく語りき 」http://sui-hei.net/mondai/show/21683
に対するオマージュでもあります。
[17年10月29日 00:57]
以下の作品【「ラテシン」に捧ぐエピローグ】は、ラテシン公式ストーリーの二次創作作品でもありますが、
「 骸かく語りき 」http://sui-hei.net/mondai/show/21683
に対するオマージュでもあります。
[17年10月29日 00:57]
[334414]黒井由紀
「『私』が、自分の存在に気付いてほしいと思っていたからですか?」
俺が問う。
「YES. 正解だよ」
シンディが答える。
長い間、色々な場所で、様々な状況で、俺達は幾度も繰り返してきた。
「これまで、何問出して何問解いた?」
ふと思い付いたかのように装い、訊ねる。目まぐるしい速さで増え、気が遠くなるほど多かったから、俺はいつまで経っても正確な問題数を数えられないでいた。
「んー、…………」
素潜りでもするみたいに肺いっぱいに空気を吸い込むと、シンディは目を瞑って息を細長く吐き出した。息が切れる寸前に浮上すると、シンディは全ての問題数をズバリ答えた。今の短時間で過去問の海を泳ぎ切ってきたらしく、なんだか達成感らしきものが顔に浮かんでいる。
「もうそんなにか。なら、仕方がないのかもしれないな」
「あはは、そんなにしんみりしないでよ」
ずっと一緒に謎と出会い、解いてきたのだ。少しくらい寂しくなったって構わないじゃないか。
そう思ったけれど、口には出さずにおいた。こういう感情を伝えるには、万言を費やすよりも沈黙の方が雄弁だ。
「……私は結構楽しみにしてるんだよ。これからはもっと自由に、いつでも皆に会いに行けるし、どこにだって行けるもの」
俺の沈黙に応えるように、シンディは楽しげに言った。その目には既に様々な未来の想像が浮かんでいるらしく、きらきらと輝いている。
シンディの考え方は、俺にはいつも新鮮だった。それは今も変わらない。つい頷きそうになるのをこらえて、手元のコーヒーを一口飲んだ。
コーヒーカップをソーサーに置いた時、テーブルの反対側にシンディの姿はなかった。
音もなく、それこそ「さよなら」も「じゃあね」も、「また会おう」もなかった。一瞬だけ、どこかに隠れて俺を脅かそうとしているのかも、とか、タイミングを計り間違えて別れの挨拶を言い損ねるなんてシンディらしくもないミスだ、とか思ったが、対面に置かれたティーカップが空になっているところを見るに、どうやらそうではないらしい。
一人残された俺は、残ったコーヒーを啜る。まだ十分にぬくもりの残ったコーヒーは、少しだけ酸っぱくなっていた。
シンディと出会ってから、確実に俺の生き方は変わった。様々な異世界に行って夢のような体験をし続けた館「ラテシン」でのコレクター生活はもちろんだが、見慣れた光景に水平思考の光を当てて得られた新たな発見の数々が、俺の考え方に大きな影響を与えていた。
何か見るたびに「これに水平思考を使うとどうなるだろう」とつい考えてしまうし、それ以上に「これを見たらシンディはどう思うだろう」「シンディならこうやって解決しそうだ」という考えが勝手に湧き出す。そうなってもなお、俺の想像を上回り続けるシンディには歯ぎしりしたし、時々出し抜けるとすごく気持ち良かった。
まだまだ……叶うことならいついつまでも、一緒に冒険がしたかった。一緒に解く謎は、いつもとても楽しかったから。シンディと謎を解き続けたら、いつかとんでもない景色と巡り合える気がしたから。
やがて思考は堂々巡りの様相を呈し始める。こんな風に別れることを前もって分かっていたなら、と生産性のない夢想に入りかけたのに気付いたところで、俺はようやく重たい感傷を振り払って席を立つ。慌てて会計に駆けつけた店員は、一人の俺がさっきまで着いていたテーブルに、空になったティーカップとコーヒーカップが向かい合わせに置かれているのを見ても、何の反応も示さず料金を受け取った。
店の外に出ると、街の人々は何事もなかったかのように日常を過ごしていた。この街の人のほとんどは、館「ラテシン」の存在も、その館の案内人のことも知らなかったのだから当たり前だが、体のどこかに大きな穴を開けられたみたいな心地の俺には、どうにも不自然に感じられた。
違和感を解くべく、足は自然と館「ラテシン」へと向かう。なんの実感も与えず姿を消したシンディの、存在と不在を知るための確かな証拠が欲しかった。
辿り着いたそこには、賑やかな大通りの情景があるだけだった。館「ラテシン」など影も形もないし、シンディどころか見知ったコレクターの姿さえない。普段なら日常会話に入り交じって聞こえてくる尻上がりの疑問文達も、鳴りを潜めている。そういえば、さっきの店員も、お茶の相手に何の予兆もなしに去られてしまった俺を見たのに、何も言わなかった。
急速にすべての物事から現実感が失われ、目の前の景色が歪みはじめる。
俺は今、夢を見ているんじゃないか? それとも、この街にやって来てからのすべての出来事こそが、夢だったのか?
足元が崩れるような感覚を覚え、ふらふらと進み出た先で、俺は妙なものを見た。
倒れているマネキンと、そこに溜まる血のような液体。
真っ昼間なせいで周囲には人集りができ、彼らは口々に推理を述べている。まるでそこだけに、以前までのアルカーノが残っているかのようだった。
奇妙な出来事によく巻き込まれる街の「いつも」の光景だけでも、俺に正気を取り戻させるには十分だったろうが、その人集りの中央にあった謎が、更に俺の頭を冴えさせた。今目の前にある謎は、俺がこの街にやって来た夜、シンディに導かれながら解き明かした謎に、あまりにも似ている。
古びた街灯の明かりしかなかったあの時と違い、辺りを照らしているのは目映いばかりの日光だが、そのせいで却って謎の全容は簡単に見て取れた。横たわった無機質なマネキンの腹部を赤いインクが濡らしている、ただそれだけの光景に、あの日の妖しさはない。
けれども、投げ出されたマネキンの指の先には、俺に投げかけられた強烈なメッセージが記されていた。
新たな冒険のはじまり!
「ダイイングメッセージにしては、前向きで陽気すぎると思うんだが」
呆れたふりをして独りごちると、俺は「問い」を口にする。
『とある街の大通り。
快晴の空に輝く太陽によってあたりは照らされ、古びた街灯は消えている。
通りすがりの男はそこで奇妙な光景を目にした。
倒れているマネキンと、そこに溜まる血のような液体。
おまけにやたらと前向きで陽気なダイイングメッセージ。
街の大通りに、なぜこんな物があるのだろうか?』
「そうして最後の問いは最初の答えに繋がる、って訳か?」
わざとらしく首を傾げ、真意を問うように呟く。シンディは、しれっといつも通りを装いながらも、自分の存在を伝えるすべを考えていたらしい。
こみ上げそうになる何かを抑え込んで、俺はマネキンの側にしゃがみ込む。謎があるのだ、コレクターの俺が解かずにどうする。
これが新たな冒険だと言うのなら、俺も地の果てまで追いかけてやるさ。
男の謎解きは、これからも続く。
シンディ
アルカーノの世界の住民。
? ?歳 145cm
一人称「私」のラテシンの館への道案内人及び試験官。謎めいた少女(?)
少女の様な外見だが年齢性別すべて不詳。謎への探究心と情熱は誰よりもある。
人をからかうのが好きで、ライナーによくちょっかいを出す。
謎の扱いに関してはウミガメのみならず謎解き全般得意。
奇妙な現象や不可解な出来事が起こりそうなものにはラテナやライナーを巻き込んで首を突っ込みに行く。 (【強・凶・狂・共】参照)
奇妙な出来事に巻き込まれる、不思議な街「アルカーノ」
「ラテシン」への案内人・シンディは、この街の住人である。
本名・年齢・性別は不詳。
“謎を愛しすぎるが故に、自ら謎という存在になりつつある。”
好きなものは、謎と不可解な現象。
終始余裕を崩さず、真面目な人間をからかうのが好きな側面を持つ。
豊富な経験と、水平思考と垂直思考の両方を兼ね備えているが、
特に知識が豊富というわけではない。
シンディは、迷う人も多いこの街の道案内をしている。
神出鬼没で、道に迷った人間や奇妙な出来事が起きた場所に
何の前触れもなく突然「現れる。」
隠された謎の館「ラテシン」への行き方を知り、
館に入る資格ある人間の選定を行い、館へと誘う。
案内人・シンディは、「ラテシン」に集まる収集家たちとは違い
館のホスト側のポジションに位置する。
シンディと収集家との物語は、また別のお話で。
(ラテシンWIKI より引用 “”は筆者が強調のために付けました)
[17年10月29日 00:03]
「『私』が、自分の存在に気付いてほしいと思っていたからですか?」
俺が問う。
「YES. 正解だよ」
シンディが答える。
長い間、色々な場所で、様々な状況で、俺達は幾度も繰り返してきた。
「これまで、何問出して何問解いた?」
ふと思い付いたかのように装い、訊ねる。目まぐるしい速さで増え、気が遠くなるほど多かったから、俺はいつまで経っても正確な問題数を数えられないでいた。
「んー、…………」
素潜りでもするみたいに肺いっぱいに空気を吸い込むと、シンディは目を瞑って息を細長く吐き出した。息が切れる寸前に浮上すると、シンディは全ての問題数をズバリ答えた。今の短時間で過去問の海を泳ぎ切ってきたらしく、なんだか達成感らしきものが顔に浮かんでいる。
「もうそんなにか。なら、仕方がないのかもしれないな」
「あはは、そんなにしんみりしないでよ」
ずっと一緒に謎と出会い、解いてきたのだ。少しくらい寂しくなったって構わないじゃないか。
そう思ったけれど、口には出さずにおいた。こういう感情を伝えるには、万言を費やすよりも沈黙の方が雄弁だ。
「……私は結構楽しみにしてるんだよ。これからはもっと自由に、いつでも皆に会いに行けるし、どこにだって行けるもの」
俺の沈黙に応えるように、シンディは楽しげに言った。その目には既に様々な未来の想像が浮かんでいるらしく、きらきらと輝いている。
シンディの考え方は、俺にはいつも新鮮だった。それは今も変わらない。つい頷きそうになるのをこらえて、手元のコーヒーを一口飲んだ。
コーヒーカップをソーサーに置いた時、テーブルの反対側にシンディの姿はなかった。
音もなく、それこそ「さよなら」も「じゃあね」も、「また会おう」もなかった。一瞬だけ、どこかに隠れて俺を脅かそうとしているのかも、とか、タイミングを計り間違えて別れの挨拶を言い損ねるなんてシンディらしくもないミスだ、とか思ったが、対面に置かれたティーカップが空になっているところを見るに、どうやらそうではないらしい。
一人残された俺は、残ったコーヒーを啜る。まだ十分にぬくもりの残ったコーヒーは、少しだけ酸っぱくなっていた。
シンディと出会ってから、確実に俺の生き方は変わった。様々な異世界に行って夢のような体験をし続けた館「ラテシン」でのコレクター生活はもちろんだが、見慣れた光景に水平思考の光を当てて得られた新たな発見の数々が、俺の考え方に大きな影響を与えていた。
何か見るたびに「これに水平思考を使うとどうなるだろう」とつい考えてしまうし、それ以上に「これを見たらシンディはどう思うだろう」「シンディならこうやって解決しそうだ」という考えが勝手に湧き出す。そうなってもなお、俺の想像を上回り続けるシンディには歯ぎしりしたし、時々出し抜けるとすごく気持ち良かった。
まだまだ……叶うことならいついつまでも、一緒に冒険がしたかった。一緒に解く謎は、いつもとても楽しかったから。シンディと謎を解き続けたら、いつかとんでもない景色と巡り合える気がしたから。
やがて思考は堂々巡りの様相を呈し始める。こんな風に別れることを前もって分かっていたなら、と生産性のない夢想に入りかけたのに気付いたところで、俺はようやく重たい感傷を振り払って席を立つ。慌てて会計に駆けつけた店員は、一人の俺がさっきまで着いていたテーブルに、空になったティーカップとコーヒーカップが向かい合わせに置かれているのを見ても、何の反応も示さず料金を受け取った。
店の外に出ると、街の人々は何事もなかったかのように日常を過ごしていた。この街の人のほとんどは、館「ラテシン」の存在も、その館の案内人のことも知らなかったのだから当たり前だが、体のどこかに大きな穴を開けられたみたいな心地の俺には、どうにも不自然に感じられた。
違和感を解くべく、足は自然と館「ラテシン」へと向かう。なんの実感も与えず姿を消したシンディの、存在と不在を知るための確かな証拠が欲しかった。
辿り着いたそこには、賑やかな大通りの情景があるだけだった。館「ラテシン」など影も形もないし、シンディどころか見知ったコレクターの姿さえない。普段なら日常会話に入り交じって聞こえてくる尻上がりの疑問文達も、鳴りを潜めている。そういえば、さっきの店員も、お茶の相手に何の予兆もなしに去られてしまった俺を見たのに、何も言わなかった。
急速にすべての物事から現実感が失われ、目の前の景色が歪みはじめる。
俺は今、夢を見ているんじゃないか? それとも、この街にやって来てからのすべての出来事こそが、夢だったのか?
足元が崩れるような感覚を覚え、ふらふらと進み出た先で、俺は妙なものを見た。
倒れているマネキンと、そこに溜まる血のような液体。
真っ昼間なせいで周囲には人集りができ、彼らは口々に推理を述べている。まるでそこだけに、以前までのアルカーノが残っているかのようだった。
奇妙な出来事によく巻き込まれる街の「いつも」の光景だけでも、俺に正気を取り戻させるには十分だったろうが、その人集りの中央にあった謎が、更に俺の頭を冴えさせた。今目の前にある謎は、俺がこの街にやって来た夜、シンディに導かれながら解き明かした謎に、あまりにも似ている。
古びた街灯の明かりしかなかったあの時と違い、辺りを照らしているのは目映いばかりの日光だが、そのせいで却って謎の全容は簡単に見て取れた。横たわった無機質なマネキンの腹部を赤いインクが濡らしている、ただそれだけの光景に、あの日の妖しさはない。
けれども、投げ出されたマネキンの指の先には、俺に投げかけられた強烈なメッセージが記されていた。
新たな冒険のはじまり!
「ダイイングメッセージにしては、前向きで陽気すぎると思うんだが」
呆れたふりをして独りごちると、俺は「問い」を口にする。
『とある街の大通り。
快晴の空に輝く太陽によってあたりは照らされ、古びた街灯は消えている。
通りすがりの男はそこで奇妙な光景を目にした。
倒れているマネキンと、そこに溜まる血のような液体。
おまけにやたらと前向きで陽気なダイイングメッセージ。
街の大通りに、なぜこんな物があるのだろうか?』
「そうして最後の問いは最初の答えに繋がる、って訳か?」
わざとらしく首を傾げ、真意を問うように呟く。シンディは、しれっといつも通りを装いながらも、自分の存在を伝えるすべを考えていたらしい。
こみ上げそうになる何かを抑え込んで、俺はマネキンの側にしゃがみ込む。謎があるのだ、コレクターの俺が解かずにどうする。
これが新たな冒険だと言うのなら、俺も地の果てまで追いかけてやるさ。
男の謎解きは、これからも続く。
シンディ
アルカーノの世界の住民。
? ?歳 145cm
一人称「私」のラテシンの館への道案内人及び試験官。謎めいた少女(?)
少女の様な外見だが年齢性別すべて不詳。謎への探究心と情熱は誰よりもある。
人をからかうのが好きで、ライナーによくちょっかいを出す。
謎の扱いに関してはウミガメのみならず謎解き全般得意。
奇妙な現象や不可解な出来事が起こりそうなものにはラテナやライナーを巻き込んで首を突っ込みに行く。 (【強・凶・狂・共】参照)
奇妙な出来事に巻き込まれる、不思議な街「アルカーノ」
「ラテシン」への案内人・シンディは、この街の住人である。
本名・年齢・性別は不詳。
“謎を愛しすぎるが故に、自ら謎という存在になりつつある。”
好きなものは、謎と不可解な現象。
終始余裕を崩さず、真面目な人間をからかうのが好きな側面を持つ。
豊富な経験と、水平思考と垂直思考の両方を兼ね備えているが、
特に知識が豊富というわけではない。
シンディは、迷う人も多いこの街の道案内をしている。
神出鬼没で、道に迷った人間や奇妙な出来事が起きた場所に
何の前触れもなく突然「現れる。」
隠された謎の館「ラテシン」への行き方を知り、
館に入る資格ある人間の選定を行い、館へと誘う。
案内人・シンディは、「ラテシン」に集まる収集家たちとは違い
館のホスト側のポジションに位置する。
シンディと収集家との物語は、また別のお話で。
(ラテシンWIKI より引用 “”は筆者が強調のために付けました)
[17年10月29日 00:03]
[333003]黒井由紀
どうもこんにちは。ポトフでございます。ええ。
今日は問題の調理法を勉強しましょう。
必要なものは、活きの良い問題と、十分な量の質問です。ええ。
それではいきましょう。
まずは、基礎質問で下ごしらえをします。ええ。
このよく分からない辺りを切り取ったら、基礎質問で揉んで置いておきます。しばらくすれば引き締まって輪郭が見えてきます。
また、可能性はしっかりと削り取っておきましょう。これがあると雑味が増します。ええ。
さて、下ごしらえが終わったら、本格的に調理に入りましょう。
適当な大きさになるまで質問で切っていきます。一口サイズになれば形は何でも良いですが、様々な方向からの質問が必要です。必要な質問は問題によっても色々と違うので、色々な見方とそれに合わせた質問を練習しておきましょう。
切ったら必ず断面を確認してください。さっきまで思っていたのとは違う形をしていたり、意外な物が埋まっていたりすることがありますから。ええ。あ、赤い粒が付着していることがありますが、これは切った際に付いた良い質問なので、問題はありません。気になる方や、見た目にこだわりたい方は洗い流してください。
良い感じの大きさになったら、煮込んでいきます。別解が浮いてきたら、あく取りで掬ってください。ちなみにこの別解は、冷ましてから味付けすれば別の料理にできますので、取っておきましょう。ええ。
この段階で、解答の断片らしきものが散らばっている可能性があります。そういう時は、かき集めてまとめ質問をしましょう。正解マークが付いたら完成です。
さて、問題の調理が完了しましたね。これで、あなたは無事にスープを食すことに成功しました。
え? 調理したのに食し終えているなんて矛盾している? ウミガメのスープとは、そういうものでございます。
[17年10月10日 23:32]
どうもこんにちは。ポトフでございます。ええ。
今日は問題の調理法を勉強しましょう。
必要なものは、活きの良い問題と、十分な量の質問です。ええ。
それではいきましょう。
まずは、基礎質問で下ごしらえをします。ええ。
このよく分からない辺りを切り取ったら、基礎質問で揉んで置いておきます。しばらくすれば引き締まって輪郭が見えてきます。
また、可能性はしっかりと削り取っておきましょう。これがあると雑味が増します。ええ。
さて、下ごしらえが終わったら、本格的に調理に入りましょう。
適当な大きさになるまで質問で切っていきます。一口サイズになれば形は何でも良いですが、様々な方向からの質問が必要です。必要な質問は問題によっても色々と違うので、色々な見方とそれに合わせた質問を練習しておきましょう。
切ったら必ず断面を確認してください。さっきまで思っていたのとは違う形をしていたり、意外な物が埋まっていたりすることがありますから。ええ。あ、赤い粒が付着していることがありますが、これは切った際に付いた良い質問なので、問題はありません。気になる方や、見た目にこだわりたい方は洗い流してください。
良い感じの大きさになったら、煮込んでいきます。別解が浮いてきたら、あく取りで掬ってください。ちなみにこの別解は、冷ましてから味付けすれば別の料理にできますので、取っておきましょう。ええ。
この段階で、解答の断片らしきものが散らばっている可能性があります。そういう時は、かき集めてまとめ質問をしましょう。正解マークが付いたら完成です。
さて、問題の調理が完了しましたね。これで、あなたは無事にスープを食すことに成功しました。
え? 調理したのに食し終えているなんて矛盾している? ウミガメのスープとは、そういうものでございます。
[17年10月10日 23:32]
[332983]黒井由紀
いつも通り謎収集に向かうと、異世界に繋がる扉の前にはいつもと違う人物が立っていた。
「シンディが起きないんだ」
その人物――ラテナは、妙に深刻そうな顔で俺に告げた。
「起きないって……起こせばいいんじゃないのか?」
「それが全くダメなんだ。普段なら細かな気配にも気付いて飛び起きるのに、今日は枕元でレミントン鳴らしても無反応だった」
スナイパーライフルは「鳴らす」ものではないし、そもそも室内で撃たないで欲しいものだが、この名スナイパーには言っても無駄だろう。
「だから、今日の謎収集は、ライナー一人で行ってくれ」
ラテナはそう言い、びしっと鋭く人差し指を突き付けてきた。
「えっ、どうして? シンディがおかしいなら、俺も何かした方がいいんじゃないのか?」
「もう既にスープの男とニューカムが原因究明に動いてる。代わりに、謎収集の方の手が足んなくなって、あたしまで駆り出されてるってわけ」
別にコレクターではないラテナがここにいるのは、そういう理由か。
「なるほど。それなら、速く謎を解いて帰ってくるとしよう」
俺だって、何度もシンディと共に異世界の謎を解いてきたのだ。もう一人でも十分謎を解けるはず。シンディがピンチに陥っている今、甘えてはいられない。
覚悟を決めると、俺は扉を開け異世界へと飛び込んだ。
とりあえずやって来たものの、ニューカムがいないため、今いる世界のことは全く分からない。それでも、何かがおかしいとだけは強く感じる。
館「ラテシン」の扉をくぐって来たはずなのに、俺はまだ館「ラテシン」の玄関ホールにいる。
扉が作動しなかったのかとも思ったが、だとしたら「出た」はずの俺がまた館の中にいるのはおかしい。やっぱりここは異世界なのだろうか。
悩んでいても埒が明かない。ひとまず、目についたものから調べていこう。
綺麗に片付けられた玄関ホールの中で、トートバッグとケーキ用の紙箱がぶら下がったコート掛けは激しく浮いていた。館「ラテシン」においては来客用と定められ、コレクターが上着を掛けることさえ禁じられていたというのに、ケーキ箱なんか掛けた日にはポトフが失神するのではないか。トートバッグには電球三つと今日発売予定の新刊本が入っており、CUBEと書かれたケーキ箱にはサイコロ型のお菓子らしきものが並んでいた。匂いは特にしないが、外を覆う生地だけ見ればシュークリームらしく思えた。割って確かめようとしたものの、プラスチックの張りぼてのような固さと軽さで、決して割れることはなかった。気になってトートバッグの中身も精査すると、電球こそ変わったところはなかったが、本はページ同士をぴったりと貼り合わせたみたいに固く閉じ、中を読むことはできなかった。
コート掛けに掛かっていたものは明らかに珍妙だった。が、特に明確な謎や手がかりを含んでいる訳ではなかったので、その奇妙な点だけを記憶に留めて廊下へと進んだ。
見慣れた館を今更探索するなんて、変な感じだ。はじめこそそう思ったが、だんだん、意外と館「ラテシン」のことを知らなかったと気付かされていく。この廊下には、こんなに沢山のドアがあっただろうか。廊下の壁紙は、古今東西の暗号形式を書き並べたものだっただろうか。俺の知っている館「ラテシン」と本当に同じか自問自答するたびに、見ているだけで観察していなかったことを痛感させられる。
……けど、さすがにこんなものは無かったはずだ。
談話室のローテーブルで、「ヒトナミニオームナク!」と叫びながら、鉢植えの花がうねうねと茎をしならせて踊っていた。叫びの内容は意味不明だが、語呂合わせだと考えると館「ラテシン」の共同金庫の暗証番号と一致するのがやけに不気味だ。
館「ラテシン」中最も不可思議で、館の存在意義そのものとも言える場所。異世界への扉のある場所に辿り着くと、俺は若干の寒気を覚えた。館「ラテシン」の扉をくぐってやってきた館「ラテシン」らしき建物の中の扉。もしこの先にも館「ラテシン」が続いていたら、何枚も扉をくぐり続けた果てに、俺はどこへ行ってしまうのだろうか。
スルーしようかとも思ったが、手がかりがあるとしたらやっぱりここだろう、と思い直し、結局こわごわ扉を開けた。
扉の先の光景には、見覚えがあった。以前俺とシンディで収集した謎の発生地だ。更なる手掛かりを求めて歩き回っていると、以前シンディと解いた謎がそのまま目の前に現れた。
以前と同じように、ただし以前よりは多少スマートに行動すると、その謎はあっさり解けた。何もかもが、以前の再現だった。
その後も何度か扉の向こうへ行ったが、過去に解いたことのある謎が再現されるだけ。これでは異世界へ続く扉の本来の目的にはそぐわない。
あまりに不可思議な現象なので、完全には再現しきれなかったのだろうか。
拍子抜けしつつも安堵を覚え、俺は他の部屋を見てみることにした。
試しに開けたドアの向こうは別世界だった。「異世界」ではないようだが、ドアのこちら側と繋がった室内には見えない、という塩梅の奇妙さ。少なくとも、元のラテシンにはこういうタイプの不思議部屋はなかったはずだ。
その部屋の中では、ジャングルか植物園かと疑うような密集具合で植物が生い茂っていた。でも、その部屋はジャングルでも植物園でもあり得なかった。何故なら、その部屋は暑くも寒くもない上、様々な季節や生息地の植物が渾然一体と植わっていたからだ。こんなことは、俺の知っている世界の常識ではあり得ない。
面食らって他の部屋に逃げ込むと、そこはドアだらけの部屋だった。様々な形の錠と鍵が、それぞれのドアに付いている。
次の部屋では、足元に小さなアルカーノの街が広がっていた。ミニチュアサイズだけれどとても精巧で、店の売り物まで完璧に再現されている。よく探してみると、先ほど見たケーキ箱の店「CUBE」も町はずれにちゃんとあり、開店祝いの花に彩られた店のショーケースに、サイコロ型のケーキが所狭しと並んでいた。
少し冷静さを取り戻して辺りの部屋すべてに入ってみると、どの部屋も、あるジャンルに属する何かを集めて並べてあるということが分かった。ある部屋は菓子、ある部屋はパズル、ある部屋は殺人現場、ある部屋は手品の道具という具合だ。
……この館の所有者の趣味はどうなっているのか。一人の人間が持つコレクションとしては、あまりにジャンルがしっちゃかめっちゃかだ。というか、殺人現場ってコレクションできるものだったのか。
訳の分からない感心を覚えた辺りで、ちょっとした閃きがあった。植物が並ぶ部屋に戻り確かめると、植わっている植物が全て毒を持つものであることと、無秩序に並んでいるように見えて、実は名前順に植えられているということが判明した。この館の所有者は、殺人や謎に強く心惹かれているらしい。
それにしても、花の咲く季節も生息地も無視して名前順に並べるなんて、これでは植物園というより植物図鑑だ。所有者のセンスには全く共感できない。
ここで解くべき謎が何なのか、廊下を歩きながらぼんやりと考える。壁に等間隔に描かれた数字は、一から三十一まで増え、また一に戻り、今度は二十九まで増えたところで一に戻る。途中、二つ目の十のそばに「ラテシン完成」と書かれていたのを見て、それがカレンダーらしいことに気づいた。よくよく見ると、イベントの開催日や、コレクターが館にやってきた日などの記念日なども該当する数字のそばに書かれていた。
……そういえば、ここにやって来た時からずっと人の姿を見かけていない。
館「ラテシン」では、多くのコレクター達が謎収集に勤しんでいるし、他にも様々な役割を担わされた人々が生活している。ここが館「ラテシン」の再現なら、誰かの姿を見かけてもいいはずなのに。
なんとなく引っ掛かりを覚え、館「ラテシン」内で自分の部屋だった場所へと向かう。俺の部屋は、再現されているのか? 再現されているとしたらどんな風に? そこに、この世界のことをもっと深く知る手掛かりが隠されているような気がした。
開けて入った先は、本がそこかしこに積まれ、パズルやメモで足の踏み場もない凄まじい部屋だった。確かに俺の部屋だ。
ただし、一週間前の。
ここ一週間、真剣に片付けたので、今の俺の部屋は物こそ多いけれど整理整頓されている。シンディに揶揄われたので、一念発起したのだ。
「マインドパレスって記憶法があるの、知ってる?」
発端は、シンディのその台詞だった。本を借りに俺の部屋にやって来たとき、ふと思いついたように言い出した。
「記憶の宮殿とか、場所法とか呼ばれる奴だろ? 脳内に思い浮かべた空間に、覚えたいものを置いていくっていう。確か、馴染みのある場所を使うと覚えやすいんだっけ」
質問に答えると、シンディは満足そうに頷いた。
「でも、なんで今そんな話を?」
部屋に入ってすぐに聞くような話ではないし、シンディが借りに来た本の内容とも関係ない。これは、言葉の外のどこかに真意があるパターンだ。
「いやあ、ライナー君はマインドパレスを建てるのに向いてるんじゃないかと思ってね」
四方八方にうねる本の塔から隣の塔へ数冊本を移し、その下にあった目当ての本を取りシンディに手渡す。床の見えている部分をもたもたと踏み分けながらやって来たシンディが、肩をすくめて言う。
「これだけ散らかっている部屋からでも、欲しいものを一発で取り出せるんだもの。きっと、マインドパレスにも置きたいだけ記憶を置けるんじゃない?」
よっぽど部屋の散らかりが気になったらしく、シンディが口にする皮肉にしてはかなり露骨だった。
そんな訳で俺は部屋を片付けたのだが、そこまで思い出したところで、俺は自分のボンクラ加減を呪った。
確信を得ることまではできなくとも、その答えは十分想像しうる範疇にあった。
これから買う予定の物、暗証番号、よく使う知識、記念日、過去に解いた問題。どれも、覚えておきたい事柄だ。それらが、館「ラテシン」というとても馴染み深い場所を模した空間に並んでいる。
ここは、シンディのマインドパレスなのだ。
そうと分かれば、俺のするべきことは一つ。
マインドパレスは本来、記憶法のための疑似的空間に過ぎない。が、それと同時にシンディの記憶の一部分でもある。何故かは知らないが、今そこに立ち入っている俺にならば、シンディの意識に内側から働きかけ、起こすことができるかもしれない。
館「ラテシン」でシンディの部屋があった場所へと急ぎ、ドアを開ける。確信はなかったが、目覚めない原因を探す場所として、自室以外思い浮かばなかった。
木炭を雑に何往復かさせて描いたような黒いヒトガタが、ベッドに横たわったシンディの首を絞めていた。シンディが目覚めない原因と、俺がここで解くべき謎の正体は、これだったのだ。
ヒトガタに飛び掛かり、その落書きみたいな手をシンディの首から剥がす。けほっと小さな咳をしたのち、シンディは飛び起きた。
ヒトガタは、頭に空いた二つの裂け目でこちらを睨み、立体感のない腕を伸ばしてきた。
手刀で応戦していると、空いている方の腕をシンディに掴まれた。
「いいから逃げるよ!」
シンディに腕を引かれ、館中を逃げ回った。音もなく付いてくるヒトガタに、幾度も陰から襲い掛かられたが、どうにか逃れる。
やがて辿り着いた玄関ホールで、シンディは躊躇いなく玄関を開け、飛び出した。ぎゅっと腕を掴まれていたので、俺も落ちるように玄関を飛び出した。
そこは、異世界へ繋がる扉の前だった。さっきまで腕を掴んでいたシンディはいなくなっている。戻ってこられたのか?
「やあライナー君。おはよう」
きょろきょろと辺りを見回すと、シンディが何食わぬ顔で声を掛けてきた。
「おはよう、って時間でもないか。今日はポトフさんにお使いを頼まれてるし、ランチは街のカフェで食べてもいいかもね。ライナー君も、今日発売の新刊があるから来るでしょ?」
とりあえずヒトガタは撒けたようだが、油断は禁物だ。ここがまだ異世界である可能性は十分ある。
「もう、呆けてないで行こうよ! 大丈夫、ここは本物の館「ラテシン」で、私は無事に目覚めた。君が目覚めさせてくれたんでしょ?」
シンディは、急に真面目な表情に戻り、俺の肩を叩いて諭した。その感触で、ようやく俺は我を取り戻す。
「……お互い、無事なんだな」
「うん。君のおかげだよ。ありがとう」
深く頷くと、シンディはにっこり笑って礼を述べた。そこまではっきり言われると、少し照れくさい。
ニューカムに謎が解けたことを報告し、玄関で待ち合わせたシンディの元へ向かう。人のちゃんといる館を歩いて、俺はやけにホッとしていた。
「そうだ、町はずれにCUBEっていうケーキ屋さんができたから行ってみようよ。キューブ型のシュークリームが美味しいんだって」
トートバッグを肩に掛けて待っていたシンディは、ついさっきまでのことなど無かったかのようにはしゃいでいた。けれども、俺の脳内にはまだ暗雲が立ち込めたままだった。
「ところで、あのヒトガタは何だったんだ……?」
「うーん、睡魔、かな?」
冗談めかした笑みを作って言うと、シンディは街へと駆けていった。一応推論はあるけれど、まだ言いたくない時によくする行動だった。
……謎や疑念は尽きないが、ひとまず無事を喜ぶべきか。
俺はシンディの後を追いかけ、アルカーノの街へ繰り出した。
[17年10月09日 20:23]
いつも通り謎収集に向かうと、異世界に繋がる扉の前にはいつもと違う人物が立っていた。
「シンディが起きないんだ」
その人物――ラテナは、妙に深刻そうな顔で俺に告げた。
「起きないって……起こせばいいんじゃないのか?」
「それが全くダメなんだ。普段なら細かな気配にも気付いて飛び起きるのに、今日は枕元でレミントン鳴らしても無反応だった」
スナイパーライフルは「鳴らす」ものではないし、そもそも室内で撃たないで欲しいものだが、この名スナイパーには言っても無駄だろう。
「だから、今日の謎収集は、ライナー一人で行ってくれ」
ラテナはそう言い、びしっと鋭く人差し指を突き付けてきた。
「えっ、どうして? シンディがおかしいなら、俺も何かした方がいいんじゃないのか?」
「もう既にスープの男とニューカムが原因究明に動いてる。代わりに、謎収集の方の手が足んなくなって、あたしまで駆り出されてるってわけ」
別にコレクターではないラテナがここにいるのは、そういう理由か。
「なるほど。それなら、速く謎を解いて帰ってくるとしよう」
俺だって、何度もシンディと共に異世界の謎を解いてきたのだ。もう一人でも十分謎を解けるはず。シンディがピンチに陥っている今、甘えてはいられない。
覚悟を決めると、俺は扉を開け異世界へと飛び込んだ。
とりあえずやって来たものの、ニューカムがいないため、今いる世界のことは全く分からない。それでも、何かがおかしいとだけは強く感じる。
館「ラテシン」の扉をくぐって来たはずなのに、俺はまだ館「ラテシン」の玄関ホールにいる。
扉が作動しなかったのかとも思ったが、だとしたら「出た」はずの俺がまた館の中にいるのはおかしい。やっぱりここは異世界なのだろうか。
悩んでいても埒が明かない。ひとまず、目についたものから調べていこう。
綺麗に片付けられた玄関ホールの中で、トートバッグとケーキ用の紙箱がぶら下がったコート掛けは激しく浮いていた。館「ラテシン」においては来客用と定められ、コレクターが上着を掛けることさえ禁じられていたというのに、ケーキ箱なんか掛けた日にはポトフが失神するのではないか。トートバッグには電球三つと今日発売予定の新刊本が入っており、CUBEと書かれたケーキ箱にはサイコロ型のお菓子らしきものが並んでいた。匂いは特にしないが、外を覆う生地だけ見ればシュークリームらしく思えた。割って確かめようとしたものの、プラスチックの張りぼてのような固さと軽さで、決して割れることはなかった。気になってトートバッグの中身も精査すると、電球こそ変わったところはなかったが、本はページ同士をぴったりと貼り合わせたみたいに固く閉じ、中を読むことはできなかった。
コート掛けに掛かっていたものは明らかに珍妙だった。が、特に明確な謎や手がかりを含んでいる訳ではなかったので、その奇妙な点だけを記憶に留めて廊下へと進んだ。
見慣れた館を今更探索するなんて、変な感じだ。はじめこそそう思ったが、だんだん、意外と館「ラテシン」のことを知らなかったと気付かされていく。この廊下には、こんなに沢山のドアがあっただろうか。廊下の壁紙は、古今東西の暗号形式を書き並べたものだっただろうか。俺の知っている館「ラテシン」と本当に同じか自問自答するたびに、見ているだけで観察していなかったことを痛感させられる。
……けど、さすがにこんなものは無かったはずだ。
談話室のローテーブルで、「ヒトナミニオームナク!」と叫びながら、鉢植えの花がうねうねと茎をしならせて踊っていた。叫びの内容は意味不明だが、語呂合わせだと考えると館「ラテシン」の共同金庫の暗証番号と一致するのがやけに不気味だ。
館「ラテシン」中最も不可思議で、館の存在意義そのものとも言える場所。異世界への扉のある場所に辿り着くと、俺は若干の寒気を覚えた。館「ラテシン」の扉をくぐってやってきた館「ラテシン」らしき建物の中の扉。もしこの先にも館「ラテシン」が続いていたら、何枚も扉をくぐり続けた果てに、俺はどこへ行ってしまうのだろうか。
スルーしようかとも思ったが、手がかりがあるとしたらやっぱりここだろう、と思い直し、結局こわごわ扉を開けた。
扉の先の光景には、見覚えがあった。以前俺とシンディで収集した謎の発生地だ。更なる手掛かりを求めて歩き回っていると、以前シンディと解いた謎がそのまま目の前に現れた。
以前と同じように、ただし以前よりは多少スマートに行動すると、その謎はあっさり解けた。何もかもが、以前の再現だった。
その後も何度か扉の向こうへ行ったが、過去に解いたことのある謎が再現されるだけ。これでは異世界へ続く扉の本来の目的にはそぐわない。
あまりに不可思議な現象なので、完全には再現しきれなかったのだろうか。
拍子抜けしつつも安堵を覚え、俺は他の部屋を見てみることにした。
試しに開けたドアの向こうは別世界だった。「異世界」ではないようだが、ドアのこちら側と繋がった室内には見えない、という塩梅の奇妙さ。少なくとも、元のラテシンにはこういうタイプの不思議部屋はなかったはずだ。
その部屋の中では、ジャングルか植物園かと疑うような密集具合で植物が生い茂っていた。でも、その部屋はジャングルでも植物園でもあり得なかった。何故なら、その部屋は暑くも寒くもない上、様々な季節や生息地の植物が渾然一体と植わっていたからだ。こんなことは、俺の知っている世界の常識ではあり得ない。
面食らって他の部屋に逃げ込むと、そこはドアだらけの部屋だった。様々な形の錠と鍵が、それぞれのドアに付いている。
次の部屋では、足元に小さなアルカーノの街が広がっていた。ミニチュアサイズだけれどとても精巧で、店の売り物まで完璧に再現されている。よく探してみると、先ほど見たケーキ箱の店「CUBE」も町はずれにちゃんとあり、開店祝いの花に彩られた店のショーケースに、サイコロ型のケーキが所狭しと並んでいた。
少し冷静さを取り戻して辺りの部屋すべてに入ってみると、どの部屋も、あるジャンルに属する何かを集めて並べてあるということが分かった。ある部屋は菓子、ある部屋はパズル、ある部屋は殺人現場、ある部屋は手品の道具という具合だ。
……この館の所有者の趣味はどうなっているのか。一人の人間が持つコレクションとしては、あまりにジャンルがしっちゃかめっちゃかだ。というか、殺人現場ってコレクションできるものだったのか。
訳の分からない感心を覚えた辺りで、ちょっとした閃きがあった。植物が並ぶ部屋に戻り確かめると、植わっている植物が全て毒を持つものであることと、無秩序に並んでいるように見えて、実は名前順に植えられているということが判明した。この館の所有者は、殺人や謎に強く心惹かれているらしい。
それにしても、花の咲く季節も生息地も無視して名前順に並べるなんて、これでは植物園というより植物図鑑だ。所有者のセンスには全く共感できない。
ここで解くべき謎が何なのか、廊下を歩きながらぼんやりと考える。壁に等間隔に描かれた数字は、一から三十一まで増え、また一に戻り、今度は二十九まで増えたところで一に戻る。途中、二つ目の十のそばに「ラテシン完成」と書かれていたのを見て、それがカレンダーらしいことに気づいた。よくよく見ると、イベントの開催日や、コレクターが館にやってきた日などの記念日なども該当する数字のそばに書かれていた。
……そういえば、ここにやって来た時からずっと人の姿を見かけていない。
館「ラテシン」では、多くのコレクター達が謎収集に勤しんでいるし、他にも様々な役割を担わされた人々が生活している。ここが館「ラテシン」の再現なら、誰かの姿を見かけてもいいはずなのに。
なんとなく引っ掛かりを覚え、館「ラテシン」内で自分の部屋だった場所へと向かう。俺の部屋は、再現されているのか? 再現されているとしたらどんな風に? そこに、この世界のことをもっと深く知る手掛かりが隠されているような気がした。
開けて入った先は、本がそこかしこに積まれ、パズルやメモで足の踏み場もない凄まじい部屋だった。確かに俺の部屋だ。
ただし、一週間前の。
ここ一週間、真剣に片付けたので、今の俺の部屋は物こそ多いけれど整理整頓されている。シンディに揶揄われたので、一念発起したのだ。
「マインドパレスって記憶法があるの、知ってる?」
発端は、シンディのその台詞だった。本を借りに俺の部屋にやって来たとき、ふと思いついたように言い出した。
「記憶の宮殿とか、場所法とか呼ばれる奴だろ? 脳内に思い浮かべた空間に、覚えたいものを置いていくっていう。確か、馴染みのある場所を使うと覚えやすいんだっけ」
質問に答えると、シンディは満足そうに頷いた。
「でも、なんで今そんな話を?」
部屋に入ってすぐに聞くような話ではないし、シンディが借りに来た本の内容とも関係ない。これは、言葉の外のどこかに真意があるパターンだ。
「いやあ、ライナー君はマインドパレスを建てるのに向いてるんじゃないかと思ってね」
四方八方にうねる本の塔から隣の塔へ数冊本を移し、その下にあった目当ての本を取りシンディに手渡す。床の見えている部分をもたもたと踏み分けながらやって来たシンディが、肩をすくめて言う。
「これだけ散らかっている部屋からでも、欲しいものを一発で取り出せるんだもの。きっと、マインドパレスにも置きたいだけ記憶を置けるんじゃない?」
よっぽど部屋の散らかりが気になったらしく、シンディが口にする皮肉にしてはかなり露骨だった。
そんな訳で俺は部屋を片付けたのだが、そこまで思い出したところで、俺は自分のボンクラ加減を呪った。
確信を得ることまではできなくとも、その答えは十分想像しうる範疇にあった。
これから買う予定の物、暗証番号、よく使う知識、記念日、過去に解いた問題。どれも、覚えておきたい事柄だ。それらが、館「ラテシン」というとても馴染み深い場所を模した空間に並んでいる。
ここは、シンディのマインドパレスなのだ。
そうと分かれば、俺のするべきことは一つ。
マインドパレスは本来、記憶法のための疑似的空間に過ぎない。が、それと同時にシンディの記憶の一部分でもある。何故かは知らないが、今そこに立ち入っている俺にならば、シンディの意識に内側から働きかけ、起こすことができるかもしれない。
館「ラテシン」でシンディの部屋があった場所へと急ぎ、ドアを開ける。確信はなかったが、目覚めない原因を探す場所として、自室以外思い浮かばなかった。
木炭を雑に何往復かさせて描いたような黒いヒトガタが、ベッドに横たわったシンディの首を絞めていた。シンディが目覚めない原因と、俺がここで解くべき謎の正体は、これだったのだ。
ヒトガタに飛び掛かり、その落書きみたいな手をシンディの首から剥がす。けほっと小さな咳をしたのち、シンディは飛び起きた。
ヒトガタは、頭に空いた二つの裂け目でこちらを睨み、立体感のない腕を伸ばしてきた。
手刀で応戦していると、空いている方の腕をシンディに掴まれた。
「いいから逃げるよ!」
シンディに腕を引かれ、館中を逃げ回った。音もなく付いてくるヒトガタに、幾度も陰から襲い掛かられたが、どうにか逃れる。
やがて辿り着いた玄関ホールで、シンディは躊躇いなく玄関を開け、飛び出した。ぎゅっと腕を掴まれていたので、俺も落ちるように玄関を飛び出した。
そこは、異世界へ繋がる扉の前だった。さっきまで腕を掴んでいたシンディはいなくなっている。戻ってこられたのか?
「やあライナー君。おはよう」
きょろきょろと辺りを見回すと、シンディが何食わぬ顔で声を掛けてきた。
「おはよう、って時間でもないか。今日はポトフさんにお使いを頼まれてるし、ランチは街のカフェで食べてもいいかもね。ライナー君も、今日発売の新刊があるから来るでしょ?」
とりあえずヒトガタは撒けたようだが、油断は禁物だ。ここがまだ異世界である可能性は十分ある。
「もう、呆けてないで行こうよ! 大丈夫、ここは本物の館「ラテシン」で、私は無事に目覚めた。君が目覚めさせてくれたんでしょ?」
シンディは、急に真面目な表情に戻り、俺の肩を叩いて諭した。その感触で、ようやく俺は我を取り戻す。
「……お互い、無事なんだな」
「うん。君のおかげだよ。ありがとう」
深く頷くと、シンディはにっこり笑って礼を述べた。そこまではっきり言われると、少し照れくさい。
ニューカムに謎が解けたことを報告し、玄関で待ち合わせたシンディの元へ向かう。人のちゃんといる館を歩いて、俺はやけにホッとしていた。
「そうだ、町はずれにCUBEっていうケーキ屋さんができたから行ってみようよ。キューブ型のシュークリームが美味しいんだって」
トートバッグを肩に掛けて待っていたシンディは、ついさっきまでのことなど無かったかのようにはしゃいでいた。けれども、俺の脳内にはまだ暗雲が立ち込めたままだった。
「ところで、あのヒトガタは何だったんだ……?」
「うーん、睡魔、かな?」
冗談めかした笑みを作って言うと、シンディは街へと駆けていった。一応推論はあるけれど、まだ言いたくない時によくする行動だった。
……謎や疑念は尽きないが、ひとまず無事を喜ぶべきか。
俺はシンディの後を追いかけ、アルカーノの街へ繰り出した。
[17年10月09日 20:23]
[332152]黒井由紀
「当然ながら、それもトリックです。今から私が実演して見せましょう」
探偵の強気な口上で、そのページは終わった。いよいよ真相が明かされる。期待と共にページを捲ると、
「ライナー君、謎が発生したよ!」
勢いよくドアを開けて、シンディが部屋に飛び込んできた。小脇には赤い革表紙の「異世界の常識」を抱え、傍らには謎発生を告げる妖精・ニューカムを連れ、準備は万端のようだ。
「さあ、ちゃっちゃと準備してとっとと行こう」
言いながら、シンディは俺をソファから引きずり立たせ、部屋から押し出す。小説の真相は、新たに発生した謎を解くまでお預けだ。後ろ髪引かれる思いではあるが、ここで渋るとシンディの手によって物理的に後ろ髪を引かれかねないので、大人しく付いていく。
館「ラテシン」の最奥部、そこにある一枚の扉の前へ辿り着くと、シンディは口を開いた。
「ニューカム君、扉の接続はできてる?」
その質問に、ニューカムはうなずくようにふわりと沈みこみ、また浮かんだ。
館「ラテシン」の扉は、館の主「スープの男」の不思議な力によって、異世界へと接続することができる。あまねく異世界から謎を収集するために集められた、俺達「コレクター」は、この扉を通って異世界に赴き、謎を解いて持ち帰るという役目を課せられている。
ちなみに、今俺の隣に立っているシンディは、コレクターではない。新米コレクターの俺の指導係として駆り出されているだけで、本来の役目は、これと見込んだ人材を「コレクター」として館に招く「案内人」である。
「じゃあ、行こうか」
そう言い、シンディが扉を引き開けると、ひんやりと湿った空気が流れ込んできた。微かに見える向こう側は薄暗く、風景の輪郭もおぼつかない。
「……何回経験しても、扉の向こうが異世界に変わるのはドキドキするな」
扉のすぐ先は、この世界の常識の通じない異世界なのだ。どんな危険が待ち受けていても、全くおかしくない。
「そうだね。私もいつも、今回行く世界はどんなところだろうって、ドキドキしてるよ」
シンディは目を輝かせながら同意したが、おそらく「ドキドキ」の意味が違う。けれどもその直後、シンディは俺の心を読んだかのように、
「大丈夫だよ、「異世界の常識」によれば、この世界は私達の世界と似てるみたいだからね。気候条件も生態系も大してかけ離れてないし、魔法も科学の異常発展もない。主な知的生命体も、私達とほとんど同じ姿の人間だよ」
とニンマリ笑いながら、赤い革表紙の本のページを繰って見せた。「異世界の常識」と題されたその本には、これから行く世界について、以前に探索者が赴いた時の記録や、ニューカムが事前に調査した結果が書かれている。俺達コレクターが適切な準備をして異世界に行けるのも、全てこれのおかげだ。
「それはありがたいな。タイムマシンの誤作動で着の身着のまま液体窒素の海に放り出される、なんてのはもう勘弁願いたい」
「こないだは散々だったもんね。……あ、でも。科学はそれほどでもないけど、技術は異常に発展してるみたい」
ぼそりと意味ありげに呟くと、シンディは扉の向こうへと足を踏み出した。遅れないよう付いていくと、そこは針葉樹に分厚く覆われた森の中。風もなく、生き物の気配も感じられず、木々の呼吸の音が聞こえそうなほどに静かだった。
「……なんだ、森の中じゃないか。ここじゃあ、科学技術は関係ないな」
シンディの言葉に少し身構えていた分、肩透かしを食った気分だ。
「ここはまだ目的地じゃないよ、ライナー君。ほら、ニューカムが呼んでる」
シンディが指差した先では、ニューカムがくるくると飛び回っていた。付いて来いと言わんばかりである。
「それに、私が発展してるって言ったのは「技術」で、「科学技術」じゃない。科学と技術は、近しいように見えるけど、その正体は全くの別物だよ」
ニューカムに続いて先に歩き始めたシンディは、首だけ振り返ってそう言った。
「どういうことだ? 科学と技術は、相互に影響しあう存在じゃないか」
慌ててニューカムとシンディの後を追い、質問を投げかける。
「科学は、「あるものごとがそうなっている」ことの理由を解明する学問だ。それに対して、技術は、「あるものごとがそうなっている」ことを利用して、生活に役立てる行為のこと。科学の世界においては原理の解明は絶対不可欠だけど、技術を求めるだけなら、原理なんか分からなくても使えればそれでいい。逆に、科学は役立つ必要なんてこれっぽっちもないけど、技術は役に立たないものだと困る」
シンディは足を速めながらそう説明した。謎の在り処に近づいている確信があるらしく、目は爛々と輝き、唇の端もかすかに上がっている。辺りの風景は、相変わらず木々が生い茂るばかりで、堂々巡りをしていないかどうかも俺には疑わしく思えるほどなのだが。柔らかい土に、湿った匂いを立ち昇らせながら刻印されていく足跡が、辛うじて俺達の前進を証明している。
「……つまり、科学が探偵の推理なら、技術は怪盗の手管、ってことか?」
流れるような説明をなんとか咀嚼し、聞き返すと、
「おっ、なかなかいい例えじゃない。ライナー君、伝記作家でも目指してみたら?」
褒めているのかおちょくっているのか分からない答えが返ってきた。
「名探偵のそばには伝記作家が必要、ってことか。でも、俺だって名探偵の方がいいんだけどな。職業も探偵だし」
「元、探偵でしょ。今はコレクターなんだから、目の前の謎と向き合おうじゃないか」
シンディがそう言い指さした先には、ぽっかりと森を切り取るように、金色の巨大な門がそびえ立っていた。ただでさえ鈍い金色が森の深緑の中で浮いているというのに、やたら歯車だの管だの巻きねじだのがごてごてと付いているせいで、ひどく厳めしく、薄気味悪く見える。
どう見ても、ここが目的地だ。
意を決して進み出ると、門の中央に据え付けられた巻きねじが半回転し、それに合わせて歯車が回り、管があちこちに引っ張られ、門がゆっくりと左右に開いた。よほど手入れが良いのか、何の音もしない。
門をくぐった先は玄関ホールのようで、吹き抜けのだだっ広い空間が俺達を出迎えた。壁にいくつか取り付けられた角灯が、がらんどうのホールをまだらに照らしているけれど、陰をより濃くするだけで却って不気味だ。
ガシャン、と何か重い物が落ちたような音が背後でした。慌てて振り向くと、門が閉まっている。急いで体当たりをしたが、びくともしない。
「これは……閉じ込められた、のか?」
門を眺めていたシンディが、こくりと頷いた。表側はあんなに煩雑としていたのに、門のこちら側には鍵穴が一つあるだけで、つるりとしている。試しに鍵穴にピッキングツールを差し込んでみたものの、やたらと浅い上に、ほとんど手応えがなく、開け方の手がかりすらつかめなかった。
「ようこそ、我が城へ」
不意に、奇妙な「声」がホール内にこだました。
「もし君が新聞広告を見てここへ来たのなら、その勇気と自信――あるいは蛮勇と過信かもしれないが――に敬意を示そう。もし君が、偶然ここに迷い込んだのなら、それは恐ろしい幸運、ないし素晴らしい不運だ」
その「声」は、ホールの隅に取り付けられたホーンから流れ出していた。最上級のオペラ歌手のような響きを持ちながら、どこか機械めいて虚ろで、意味のある言葉を発していなければ、「声」だと思わないような音だ。当然ながら、声を発している誰かの性別・年齢にも見当さえ付かない。
「ここからの脱出を望むのならば、この城のただ一人の住人にして城主である私を探せ」
声が告げた「私を探せ」というのが、今回の謎のクリア条件だろう。
「つまり、この城全体をフィールドとした隠れんぼ、ということか」
「いいえ、隠れんぼではありません」
俺の言葉に応えて、ホールから出ている廊下の一本から凛とした声が響いた。真っ暗な廊下の陰から、ゆっくりと人影が進み出てくる。おぼろな人影の後ろで、何かがチカチカときらめいた。
光の下に現れた人影は、ブルネットを高く結い上げ、黒いロングワンピースを纏った女性だった。瞳に理知的な光を湛えており、とても美しかったが、彼女の背中で回る金色の巻きねじの産む強烈な違和感が、ただぼんやりと見とれることを許さなかった。
「隠れんぼでないのなら、このゲームはさしずめ、間違い探しってところかな?」
シンディが言うと、女性は首を縦に振った。
「間違い探し」という言葉と、この世界で技術が異常発展しているらしいという話と、女性の背中で回る大きな巻きねじとが、頭の中で組み立てられて一つの形になる。要するに、あの巻きねじは、ファッションなどではなく、俺の知っている巻きねじと同じように、ぜんまい式の機械に動力を供給する部品なのだ。
「……あなたは実は人間そっくりの自動人形で、この城にはあなたのような自動人形が沢山いる、と?」
シンディが小さく頷く。目の前の女性はアルカイックスマイルを浮かべるばかりだったが、確かにそれなら、城主がわざわざ「人形達の創り手」と名乗ったのにも納得がいく。
「ようこそ、ホロロージ城へ。私はコッペリアと申します。先ほど流れた録音の補足をするため参りました」
女性が恭しく腰を折ってお辞儀をした。その所作はあくまで優雅かつ滑らかで、とても機械のものとは思えない。声にも、さっきホーンから流れ出していたものよりもずっと、人間的な温かみがある。
「ここは、人形師である主が人形達と暮らすために手に入れた城です。城内は自由に探索いただくよう、主から申し付けられております。一部鍵の掛かった部屋もございますが、私にお申し付けくだされば、ご案内いたします」
「なるほど、鍵の掛かった部屋を探索する時には頼るようにします。ところで、主が言っていた「ただ一人の住人」っていうのは、「人間」は自分ただ一人、ってことでいいんだよね?」
一気に降ってくる情報を頭に入れつつ、シンディはルールの細部を確認する。
「はい、その通りです。主は人嫌いで、客、使用人問わずご自分以外の人間をこの城に入れることはありませんでした。主が他人を招かないのは先ほどの録音が作成された後も変わらず、こちらの広告が新聞に載り、あなた方がいらっしゃるまで、主以外の人間は誰もこの城に足を踏み入れていません」
コッペリアが取り出した紙片には、
「 募集広告
本物を見極める目を持つ方
Lunar 2, 79585 Crescentにお越しください
Horologe」
と書かれていた。どうやらこれが、先ほど主が言っていた「新聞広告」らしい。そこにある情報は余りにも不十分かつ曖昧で、主が本気で人を呼ぶ気つもりだったのか甚だ疑問だ。
「つまり、城内で私達以外の人間を見つけることができれば、その人は城主か、私達と同じように広告を見てやって来た人ってことだね?」
「その様にお考えいただいて構いません。ただし、先ほど申し上げた通り、広告を見てやって来た訪問者はあなた方が最初ですけれど」
ならば、このゲームは非常にシンプルだ。多くの人形達に紛れた人間を見つけ出せば、俺達の勝ち。制限時間などに明言は無いが、城主を見つけ出すまではどの道この世界から出る訳にいかない。
「また、人形や家具を損壊するような行為は、絶対に、おやめください。あくまでも、紳士的に探索なさるよう、お願いいたします」
コッペリアは、一文字ずつ区切るように「絶対に」と発音した。眼光も、一瞬鋭くなったような気がする。
「それでは、補足は以上です。健闘をお祈りします」
最後にそう言うと、コッペリアは深く腰を折ってお辞儀をした。相変わらず背中の巻きねじは回っているが、それ以外の部分は微動だにしなくなった。
二言三言話しかけてみたが、全く動き出す気配がなかったので、俺達は玄関ホールを後にした。
[17年09月30日 14:29]
「当然ながら、それもトリックです。今から私が実演して見せましょう」
探偵の強気な口上で、そのページは終わった。いよいよ真相が明かされる。期待と共にページを捲ると、
「ライナー君、謎が発生したよ!」
勢いよくドアを開けて、シンディが部屋に飛び込んできた。小脇には赤い革表紙の「異世界の常識」を抱え、傍らには謎発生を告げる妖精・ニューカムを連れ、準備は万端のようだ。
「さあ、ちゃっちゃと準備してとっとと行こう」
言いながら、シンディは俺をソファから引きずり立たせ、部屋から押し出す。小説の真相は、新たに発生した謎を解くまでお預けだ。後ろ髪引かれる思いではあるが、ここで渋るとシンディの手によって物理的に後ろ髪を引かれかねないので、大人しく付いていく。
館「ラテシン」の最奥部、そこにある一枚の扉の前へ辿り着くと、シンディは口を開いた。
「ニューカム君、扉の接続はできてる?」
その質問に、ニューカムはうなずくようにふわりと沈みこみ、また浮かんだ。
館「ラテシン」の扉は、館の主「スープの男」の不思議な力によって、異世界へと接続することができる。あまねく異世界から謎を収集するために集められた、俺達「コレクター」は、この扉を通って異世界に赴き、謎を解いて持ち帰るという役目を課せられている。
ちなみに、今俺の隣に立っているシンディは、コレクターではない。新米コレクターの俺の指導係として駆り出されているだけで、本来の役目は、これと見込んだ人材を「コレクター」として館に招く「案内人」である。
「じゃあ、行こうか」
そう言い、シンディが扉を引き開けると、ひんやりと湿った空気が流れ込んできた。微かに見える向こう側は薄暗く、風景の輪郭もおぼつかない。
「……何回経験しても、扉の向こうが異世界に変わるのはドキドキするな」
扉のすぐ先は、この世界の常識の通じない異世界なのだ。どんな危険が待ち受けていても、全くおかしくない。
「そうだね。私もいつも、今回行く世界はどんなところだろうって、ドキドキしてるよ」
シンディは目を輝かせながら同意したが、おそらく「ドキドキ」の意味が違う。けれどもその直後、シンディは俺の心を読んだかのように、
「大丈夫だよ、「異世界の常識」によれば、この世界は私達の世界と似てるみたいだからね。気候条件も生態系も大してかけ離れてないし、魔法も科学の異常発展もない。主な知的生命体も、私達とほとんど同じ姿の人間だよ」
とニンマリ笑いながら、赤い革表紙の本のページを繰って見せた。「異世界の常識」と題されたその本には、これから行く世界について、以前に探索者が赴いた時の記録や、ニューカムが事前に調査した結果が書かれている。俺達コレクターが適切な準備をして異世界に行けるのも、全てこれのおかげだ。
「それはありがたいな。タイムマシンの誤作動で着の身着のまま液体窒素の海に放り出される、なんてのはもう勘弁願いたい」
「こないだは散々だったもんね。……あ、でも。科学はそれほどでもないけど、技術は異常に発展してるみたい」
ぼそりと意味ありげに呟くと、シンディは扉の向こうへと足を踏み出した。遅れないよう付いていくと、そこは針葉樹に分厚く覆われた森の中。風もなく、生き物の気配も感じられず、木々の呼吸の音が聞こえそうなほどに静かだった。
「……なんだ、森の中じゃないか。ここじゃあ、科学技術は関係ないな」
シンディの言葉に少し身構えていた分、肩透かしを食った気分だ。
「ここはまだ目的地じゃないよ、ライナー君。ほら、ニューカムが呼んでる」
シンディが指差した先では、ニューカムがくるくると飛び回っていた。付いて来いと言わんばかりである。
「それに、私が発展してるって言ったのは「技術」で、「科学技術」じゃない。科学と技術は、近しいように見えるけど、その正体は全くの別物だよ」
ニューカムに続いて先に歩き始めたシンディは、首だけ振り返ってそう言った。
「どういうことだ? 科学と技術は、相互に影響しあう存在じゃないか」
慌ててニューカムとシンディの後を追い、質問を投げかける。
「科学は、「あるものごとがそうなっている」ことの理由を解明する学問だ。それに対して、技術は、「あるものごとがそうなっている」ことを利用して、生活に役立てる行為のこと。科学の世界においては原理の解明は絶対不可欠だけど、技術を求めるだけなら、原理なんか分からなくても使えればそれでいい。逆に、科学は役立つ必要なんてこれっぽっちもないけど、技術は役に立たないものだと困る」
シンディは足を速めながらそう説明した。謎の在り処に近づいている確信があるらしく、目は爛々と輝き、唇の端もかすかに上がっている。辺りの風景は、相変わらず木々が生い茂るばかりで、堂々巡りをしていないかどうかも俺には疑わしく思えるほどなのだが。柔らかい土に、湿った匂いを立ち昇らせながら刻印されていく足跡が、辛うじて俺達の前進を証明している。
「……つまり、科学が探偵の推理なら、技術は怪盗の手管、ってことか?」
流れるような説明をなんとか咀嚼し、聞き返すと、
「おっ、なかなかいい例えじゃない。ライナー君、伝記作家でも目指してみたら?」
褒めているのかおちょくっているのか分からない答えが返ってきた。
「名探偵のそばには伝記作家が必要、ってことか。でも、俺だって名探偵の方がいいんだけどな。職業も探偵だし」
「元、探偵でしょ。今はコレクターなんだから、目の前の謎と向き合おうじゃないか」
シンディがそう言い指さした先には、ぽっかりと森を切り取るように、金色の巨大な門がそびえ立っていた。ただでさえ鈍い金色が森の深緑の中で浮いているというのに、やたら歯車だの管だの巻きねじだのがごてごてと付いているせいで、ひどく厳めしく、薄気味悪く見える。
どう見ても、ここが目的地だ。
意を決して進み出ると、門の中央に据え付けられた巻きねじが半回転し、それに合わせて歯車が回り、管があちこちに引っ張られ、門がゆっくりと左右に開いた。よほど手入れが良いのか、何の音もしない。
門をくぐった先は玄関ホールのようで、吹き抜けのだだっ広い空間が俺達を出迎えた。壁にいくつか取り付けられた角灯が、がらんどうのホールをまだらに照らしているけれど、陰をより濃くするだけで却って不気味だ。
ガシャン、と何か重い物が落ちたような音が背後でした。慌てて振り向くと、門が閉まっている。急いで体当たりをしたが、びくともしない。
「これは……閉じ込められた、のか?」
門を眺めていたシンディが、こくりと頷いた。表側はあんなに煩雑としていたのに、門のこちら側には鍵穴が一つあるだけで、つるりとしている。試しに鍵穴にピッキングツールを差し込んでみたものの、やたらと浅い上に、ほとんど手応えがなく、開け方の手がかりすらつかめなかった。
「ようこそ、我が城へ」
不意に、奇妙な「声」がホール内にこだました。
「もし君が新聞広告を見てここへ来たのなら、その勇気と自信――あるいは蛮勇と過信かもしれないが――に敬意を示そう。もし君が、偶然ここに迷い込んだのなら、それは恐ろしい幸運、ないし素晴らしい不運だ」
その「声」は、ホールの隅に取り付けられたホーンから流れ出していた。最上級のオペラ歌手のような響きを持ちながら、どこか機械めいて虚ろで、意味のある言葉を発していなければ、「声」だと思わないような音だ。当然ながら、声を発している誰かの性別・年齢にも見当さえ付かない。
「ここからの脱出を望むのならば、この城のただ一人の住人にして城主である私を探せ」
声が告げた「私を探せ」というのが、今回の謎のクリア条件だろう。
「つまり、この城全体をフィールドとした隠れんぼ、ということか」
「いいえ、隠れんぼではありません」
俺の言葉に応えて、ホールから出ている廊下の一本から凛とした声が響いた。真っ暗な廊下の陰から、ゆっくりと人影が進み出てくる。おぼろな人影の後ろで、何かがチカチカときらめいた。
光の下に現れた人影は、ブルネットを高く結い上げ、黒いロングワンピースを纏った女性だった。瞳に理知的な光を湛えており、とても美しかったが、彼女の背中で回る金色の巻きねじの産む強烈な違和感が、ただぼんやりと見とれることを許さなかった。
「隠れんぼでないのなら、このゲームはさしずめ、間違い探しってところかな?」
シンディが言うと、女性は首を縦に振った。
「間違い探し」という言葉と、この世界で技術が異常発展しているらしいという話と、女性の背中で回る大きな巻きねじとが、頭の中で組み立てられて一つの形になる。要するに、あの巻きねじは、ファッションなどではなく、俺の知っている巻きねじと同じように、ぜんまい式の機械に動力を供給する部品なのだ。
「……あなたは実は人間そっくりの自動人形で、この城にはあなたのような自動人形が沢山いる、と?」
シンディが小さく頷く。目の前の女性はアルカイックスマイルを浮かべるばかりだったが、確かにそれなら、城主がわざわざ「人形達の創り手」と名乗ったのにも納得がいく。
「ようこそ、ホロロージ城へ。私はコッペリアと申します。先ほど流れた録音の補足をするため参りました」
女性が恭しく腰を折ってお辞儀をした。その所作はあくまで優雅かつ滑らかで、とても機械のものとは思えない。声にも、さっきホーンから流れ出していたものよりもずっと、人間的な温かみがある。
「ここは、人形師である主が人形達と暮らすために手に入れた城です。城内は自由に探索いただくよう、主から申し付けられております。一部鍵の掛かった部屋もございますが、私にお申し付けくだされば、ご案内いたします」
「なるほど、鍵の掛かった部屋を探索する時には頼るようにします。ところで、主が言っていた「ただ一人の住人」っていうのは、「人間」は自分ただ一人、ってことでいいんだよね?」
一気に降ってくる情報を頭に入れつつ、シンディはルールの細部を確認する。
「はい、その通りです。主は人嫌いで、客、使用人問わずご自分以外の人間をこの城に入れることはありませんでした。主が他人を招かないのは先ほどの録音が作成された後も変わらず、こちらの広告が新聞に載り、あなた方がいらっしゃるまで、主以外の人間は誰もこの城に足を踏み入れていません」
コッペリアが取り出した紙片には、
「 募集広告
本物を見極める目を持つ方
Lunar 2, 79585 Crescentにお越しください
Horologe」
と書かれていた。どうやらこれが、先ほど主が言っていた「新聞広告」らしい。そこにある情報は余りにも不十分かつ曖昧で、主が本気で人を呼ぶ気つもりだったのか甚だ疑問だ。
「つまり、城内で私達以外の人間を見つけることができれば、その人は城主か、私達と同じように広告を見てやって来た人ってことだね?」
「その様にお考えいただいて構いません。ただし、先ほど申し上げた通り、広告を見てやって来た訪問者はあなた方が最初ですけれど」
ならば、このゲームは非常にシンプルだ。多くの人形達に紛れた人間を見つけ出せば、俺達の勝ち。制限時間などに明言は無いが、城主を見つけ出すまではどの道この世界から出る訳にいかない。
「また、人形や家具を損壊するような行為は、絶対に、おやめください。あくまでも、紳士的に探索なさるよう、お願いいたします」
コッペリアは、一文字ずつ区切るように「絶対に」と発音した。眼光も、一瞬鋭くなったような気がする。
「それでは、補足は以上です。健闘をお祈りします」
最後にそう言うと、コッペリアは深く腰を折ってお辞儀をした。相変わらず背中の巻きねじは回っているが、それ以外の部分は微動だにしなくなった。
二言三言話しかけてみたが、全く動き出す気配がなかったので、俺達は玄関ホールを後にした。
[17年09月30日 14:29]
[332151]黒井由紀
とりあえず入った廊下では、薄暗い明かりの下で人形達が立ち働いていた。巻きねじや球形関節など所々に機械らしさを残していたり、そもそも全然人間に似ていなかったりする者も多いが、ちょっと見た限りでは人間との違いが見いだせない者もそこそこいる。
「見た目だけで城主を特定するのは難しそうだな」
俺が唸ると、
「何言ってるの、ライナー君。律儀に見分けたりしなくても、城主は簡単に特定できるよ」
シンディはそう言い、両脇に並ぶドアを無視してずんずん奥へ歩いて行く。
「おいおい、この辺りの部屋は見なくていいのか?」
「多分ね。この辺りのドアは全部”木製”だから」
「木製?」
「そ。だって、キッチンのドアは燃えにくい素材の方がいいでしょ」
「なるほど、食事をしに来た所を捕まえる作戦か」
人形と違って、人間は腹が空く。そこを突いた、シンプルだが確実性の高い作戦だ。もし、人形が代わりに食事を取りに来たとしても、最終的に誰かの口に入るところまで追いかければいい。
「うん。多少時間は掛かるかもしれないけど」
「廊下を歩くだけでも、城も広いし、人形も沢山いるのは分かる。無闇に動き回るよりいいんじゃないか」
玄関ホールを出てから、もうドアを二十枚は見逃したが、廊下はまだまだ終わりそうにない。これでは単純な探索も結構な重労働だ。できれば控えたい。
黙々と歩いていると、前方の景色に違和感を覚えた。歩く度に、廊下の一点がズレるような気がする。不思議に思って目を凝らすと、そこには壁と同じ高さの大きな鏡が斜めに陣取っていた。
「うわ、曲がり角だ、シンディ」
「本当だ。面白い仕掛けだね」
シンディは歌うように呟いた。あと数歩歩いていたら鏡に激突していたところだったんだが。一点の曇りも歪みも無い鏡に感心していると、人形達が心なしか誇らしげに笑った気がした。
「あった! きっとあれがキッチンだよ!」
角を曲がった真正面、ドアを三十枚は隔てた先にある銀色の金属ドアを見て、シンディは駆け出した。
驚いて振り返った人形もいたが、お構い無しにドアを大きく開け、俺を手招きした。
賑やかだった廊下とは対照的に、キッチンはがらんとして静かだった。人形も人もおらず、艶のある大理石の作業台には何も乗っていない。棚や引き出しを見ても、きっかり一人分の食器が入っている他には何もなかった。
「……食材どころか、調味料さえ無いぞ」
その何も無さは、シンクや作業台が綺麗に磨かれていることも相まって、まだ誰も使ったことのない新しいキッチンを彷彿とさせた。
「この作戦は駄目かぁ」
「主も、長期戦になったら食事時を狙われることを承知していたんだな。保存食でも持ち歩いてるんだろう」
「まあ、そうだよね。時間制限も無いわけだし、当然考えてるか」
と、そこまで言ったところで、シンディの顔が青ざめた。
「……まずい」
「何が?」
「長期戦になったら食べないともたないのは、私達も同じだよ。急いで城主を見付けないと、私達、飢え死にする」
この瞬間、多分俺の顔面からも血の気が引いたに違いない。
「……さ、さっさと次の作戦を立てよう。そうだ、今度は逆に人形の方を張り続けるっていうのはどうだ?」
急いで思い付きを口にする。シンディの作戦を裏返しただけのものだが、城主が見つかりさえすればいいのだ。
「人形を?」
「ああ。人形だって、動くのに動力がいることは俺達と変わらない。これまですれ違ってきた人形達には、巻きねじが付いている者が多かったが、これは誰が巻いていると思う?」
「え? 自分で巻いてるんじゃないの?」
シンディはきょとんと首を傾げた。シンディらしくもない惚けようだ。
「それだと永久機関になってしまう。誰か、外部からエネルギーを取り込める者が巻かなきゃならない」
「そうか、だとすれば主が人形のねじを巻いている可能性が高い!」
「そういうことだ」
キッチンを出ると、俺達は追跡する人形を決めた。シンディが強く推した、自立自走するモップ型の人形の後を付いて歩く。口ではそれらしい理由を語っていたが、間違いなく、柄の先端に巻きねじ、中程に短い腕が付いているというモップのフォルムに惹かれただけだと思う。その証拠に、モップの後を追うシンディは、やたらと楽しそうだ。
モップは、一部屋ずつ丁寧に掃除をしていった。モップの用途を考えれば何らおかしなことはないのだが、柄の部分に付いた手で器用にドアを開け、部屋の隅まで動き回る姿はなんだかコミカルだ。
「ねえ、ライナー君。この壺おかしいよ」
そう言いながら、シンディは大きな壺を持ち上げていた。
「落としたら危ないから、すぐ戻すんだ!」
東洋風の絵が付けられた壺は、重そうだし、高そうでもあった。俺が咄嗟に叫んでしまったのも無理はないと思う。
ところがシンディは、ニヤリと笑うと俺の腕に壺を載せた。受け止めようと力を入れた瞬間、妙なことに気がつく。
この壺、恐ろしく軽いのである。
「重さとかを考えると、紙製かな。質感なんかは完璧に磁器のそれだから、詳しくはよく分からないけど」
そう言いながらシンディが拳で軽く叩くと、壺から空虚な音がポンポンと鳴った。
「まさかとは思うが、「本物を見極める目」って、こういう話か?」
「かもね。あるいは、単に城主の趣味かもしれないけど」
その後もモップは部屋を巡り床を磨き続けていたが、その後をついて部屋に入る度におかしな偽物に出くわした。まるごと壁に描かれた、騙し絵のチェストと花瓶。歪みのせいで、真正面にあるものだけ映らない鏡。写真に枠を付けただけの窓。ガラスみたいに見えるけれど、実は木製のシャンデリア。部屋そのものは、オレンジ色の明かりが本物のアンティークを品良く照らし出して優雅な雰囲気だっただけに、偽物達の放つ違和感は強烈だ。
様々な偽物に出くわして、俺は混乱の、シンディは興奮の極みに達した頃、モップの様子に変化が訪れた。ある部屋を出たかと思うと、近くの部屋に入ることなく一目散にどこかへと向かい始めたのだ。モップは廊下を駆け抜け、階段を登り、また廊下を最小限の道筋で進んで行く。階段を登る姿など見ていてシュールだったが、そんなことを気にしていられないほど、モップの走行速度は早い。真剣に追いかけていると、モップは金の飾りが付いた木のドアが見えたあたりで速度を緩め、そのままその部屋へと飛び込んだ。
その部屋は、他の部屋とは全く趣が違った。それまで入ってきた部屋が貴族の邸宅か高級ホテルだとするならば、今いる部屋はそのボイラー室、というと趣の違いが伝わりやすいかもしれない。くすんだ金色のパイプが縦横無尽に壁と天井を走り、壁に空いた人一人入れそうな大きさの窪みを囲んでいる。壁の窪みには、所々小さな切れ込みが入っているが、何故そうなっているのかは検討もつかない。
すると、俺達より先に部屋に入ったモップが、壁の窪みに入った。柄の先端の巻きねじを窪みの上方に差し込むと、部屋全体がキリキリと軋むような音を立て始めた。その音と共に、モップがかすかに震える。どうやらこの部屋は、人形のねじを巻くための巨大な装置らしい。
やがて、部屋が元の静寂を取り戻すと、モップは何事もなかったかのように壁の窪みを離れ、部屋の入口へ向かう。
「おい、兄ちゃん達」
急に聞こえたべらんめえ口調に面食らっていると、モップがこちらへ向き直った。
「人のこと追い回しといて、何も言わねえってのは、ちょいと礼儀が無さすぎるんじゃねえのかい?」
「断りなく後を追ってごめんなさい。あなた達のそのねじを、誰が巻いているのか知りたかったんだ」
シンディは、俺が呆気に取られている間に冷静さを取り戻していたが、やはりべらんめえ口調のモップにはたじたじである。
「おう、そう言ってくれりゃあ、こっちも気分よくおたくらに付いてこさせるってもんよ」
少ししゃがれた声のモップは、カラカラと笑い飛ばした。見た目も口調もクセがあるが、案外気のいい奴ではあるようだ。
「おいらはホーキガミ。今から三階の北廊下十二番目の部屋でカードやりに行くが、付いてくるかい?」
「あ、よろしくお願いします」
勢いに押されて、反射的に頷いてしまうと、ホーキガミは嬉しげに部屋を出ていった。いい奴かどうかと断り難さとは、全く別のものである。
[17年09月30日 14:29]
とりあえず入った廊下では、薄暗い明かりの下で人形達が立ち働いていた。巻きねじや球形関節など所々に機械らしさを残していたり、そもそも全然人間に似ていなかったりする者も多いが、ちょっと見た限りでは人間との違いが見いだせない者もそこそこいる。
「見た目だけで城主を特定するのは難しそうだな」
俺が唸ると、
「何言ってるの、ライナー君。律儀に見分けたりしなくても、城主は簡単に特定できるよ」
シンディはそう言い、両脇に並ぶドアを無視してずんずん奥へ歩いて行く。
「おいおい、この辺りの部屋は見なくていいのか?」
「多分ね。この辺りのドアは全部”木製”だから」
「木製?」
「そ。だって、キッチンのドアは燃えにくい素材の方がいいでしょ」
「なるほど、食事をしに来た所を捕まえる作戦か」
人形と違って、人間は腹が空く。そこを突いた、シンプルだが確実性の高い作戦だ。もし、人形が代わりに食事を取りに来たとしても、最終的に誰かの口に入るところまで追いかければいい。
「うん。多少時間は掛かるかもしれないけど」
「廊下を歩くだけでも、城も広いし、人形も沢山いるのは分かる。無闇に動き回るよりいいんじゃないか」
玄関ホールを出てから、もうドアを二十枚は見逃したが、廊下はまだまだ終わりそうにない。これでは単純な探索も結構な重労働だ。できれば控えたい。
黙々と歩いていると、前方の景色に違和感を覚えた。歩く度に、廊下の一点がズレるような気がする。不思議に思って目を凝らすと、そこには壁と同じ高さの大きな鏡が斜めに陣取っていた。
「うわ、曲がり角だ、シンディ」
「本当だ。面白い仕掛けだね」
シンディは歌うように呟いた。あと数歩歩いていたら鏡に激突していたところだったんだが。一点の曇りも歪みも無い鏡に感心していると、人形達が心なしか誇らしげに笑った気がした。
「あった! きっとあれがキッチンだよ!」
角を曲がった真正面、ドアを三十枚は隔てた先にある銀色の金属ドアを見て、シンディは駆け出した。
驚いて振り返った人形もいたが、お構い無しにドアを大きく開け、俺を手招きした。
賑やかだった廊下とは対照的に、キッチンはがらんとして静かだった。人形も人もおらず、艶のある大理石の作業台には何も乗っていない。棚や引き出しを見ても、きっかり一人分の食器が入っている他には何もなかった。
「……食材どころか、調味料さえ無いぞ」
その何も無さは、シンクや作業台が綺麗に磨かれていることも相まって、まだ誰も使ったことのない新しいキッチンを彷彿とさせた。
「この作戦は駄目かぁ」
「主も、長期戦になったら食事時を狙われることを承知していたんだな。保存食でも持ち歩いてるんだろう」
「まあ、そうだよね。時間制限も無いわけだし、当然考えてるか」
と、そこまで言ったところで、シンディの顔が青ざめた。
「……まずい」
「何が?」
「長期戦になったら食べないともたないのは、私達も同じだよ。急いで城主を見付けないと、私達、飢え死にする」
この瞬間、多分俺の顔面からも血の気が引いたに違いない。
「……さ、さっさと次の作戦を立てよう。そうだ、今度は逆に人形の方を張り続けるっていうのはどうだ?」
急いで思い付きを口にする。シンディの作戦を裏返しただけのものだが、城主が見つかりさえすればいいのだ。
「人形を?」
「ああ。人形だって、動くのに動力がいることは俺達と変わらない。これまですれ違ってきた人形達には、巻きねじが付いている者が多かったが、これは誰が巻いていると思う?」
「え? 自分で巻いてるんじゃないの?」
シンディはきょとんと首を傾げた。シンディらしくもない惚けようだ。
「それだと永久機関になってしまう。誰か、外部からエネルギーを取り込める者が巻かなきゃならない」
「そうか、だとすれば主が人形のねじを巻いている可能性が高い!」
「そういうことだ」
キッチンを出ると、俺達は追跡する人形を決めた。シンディが強く推した、自立自走するモップ型の人形の後を付いて歩く。口ではそれらしい理由を語っていたが、間違いなく、柄の先端に巻きねじ、中程に短い腕が付いているというモップのフォルムに惹かれただけだと思う。その証拠に、モップの後を追うシンディは、やたらと楽しそうだ。
モップは、一部屋ずつ丁寧に掃除をしていった。モップの用途を考えれば何らおかしなことはないのだが、柄の部分に付いた手で器用にドアを開け、部屋の隅まで動き回る姿はなんだかコミカルだ。
「ねえ、ライナー君。この壺おかしいよ」
そう言いながら、シンディは大きな壺を持ち上げていた。
「落としたら危ないから、すぐ戻すんだ!」
東洋風の絵が付けられた壺は、重そうだし、高そうでもあった。俺が咄嗟に叫んでしまったのも無理はないと思う。
ところがシンディは、ニヤリと笑うと俺の腕に壺を載せた。受け止めようと力を入れた瞬間、妙なことに気がつく。
この壺、恐ろしく軽いのである。
「重さとかを考えると、紙製かな。質感なんかは完璧に磁器のそれだから、詳しくはよく分からないけど」
そう言いながらシンディが拳で軽く叩くと、壺から空虚な音がポンポンと鳴った。
「まさかとは思うが、「本物を見極める目」って、こういう話か?」
「かもね。あるいは、単に城主の趣味かもしれないけど」
その後もモップは部屋を巡り床を磨き続けていたが、その後をついて部屋に入る度におかしな偽物に出くわした。まるごと壁に描かれた、騙し絵のチェストと花瓶。歪みのせいで、真正面にあるものだけ映らない鏡。写真に枠を付けただけの窓。ガラスみたいに見えるけれど、実は木製のシャンデリア。部屋そのものは、オレンジ色の明かりが本物のアンティークを品良く照らし出して優雅な雰囲気だっただけに、偽物達の放つ違和感は強烈だ。
様々な偽物に出くわして、俺は混乱の、シンディは興奮の極みに達した頃、モップの様子に変化が訪れた。ある部屋を出たかと思うと、近くの部屋に入ることなく一目散にどこかへと向かい始めたのだ。モップは廊下を駆け抜け、階段を登り、また廊下を最小限の道筋で進んで行く。階段を登る姿など見ていてシュールだったが、そんなことを気にしていられないほど、モップの走行速度は早い。真剣に追いかけていると、モップは金の飾りが付いた木のドアが見えたあたりで速度を緩め、そのままその部屋へと飛び込んだ。
その部屋は、他の部屋とは全く趣が違った。それまで入ってきた部屋が貴族の邸宅か高級ホテルだとするならば、今いる部屋はそのボイラー室、というと趣の違いが伝わりやすいかもしれない。くすんだ金色のパイプが縦横無尽に壁と天井を走り、壁に空いた人一人入れそうな大きさの窪みを囲んでいる。壁の窪みには、所々小さな切れ込みが入っているが、何故そうなっているのかは検討もつかない。
すると、俺達より先に部屋に入ったモップが、壁の窪みに入った。柄の先端の巻きねじを窪みの上方に差し込むと、部屋全体がキリキリと軋むような音を立て始めた。その音と共に、モップがかすかに震える。どうやらこの部屋は、人形のねじを巻くための巨大な装置らしい。
やがて、部屋が元の静寂を取り戻すと、モップは何事もなかったかのように壁の窪みを離れ、部屋の入口へ向かう。
「おい、兄ちゃん達」
急に聞こえたべらんめえ口調に面食らっていると、モップがこちらへ向き直った。
「人のこと追い回しといて、何も言わねえってのは、ちょいと礼儀が無さすぎるんじゃねえのかい?」
「断りなく後を追ってごめんなさい。あなた達のそのねじを、誰が巻いているのか知りたかったんだ」
シンディは、俺が呆気に取られている間に冷静さを取り戻していたが、やはりべらんめえ口調のモップにはたじたじである。
「おう、そう言ってくれりゃあ、こっちも気分よくおたくらに付いてこさせるってもんよ」
少ししゃがれた声のモップは、カラカラと笑い飛ばした。見た目も口調もクセがあるが、案外気のいい奴ではあるようだ。
「おいらはホーキガミ。今から三階の北廊下十二番目の部屋でカードやりに行くが、付いてくるかい?」
「あ、よろしくお願いします」
勢いに押されて、反射的に頷いてしまうと、ホーキガミは嬉しげに部屋を出ていった。いい奴かどうかと断り難さとは、全く別のものである。
[17年09月30日 14:29]
[332150]黒井由紀
「さ、着いたぞ。ここが俺達の遊戯室だ」
三階の北廊下十二番目の部屋のドアを開けながら、ホーキガミは大きな声で俺達を促した。
その部屋にはダーツ盤やビリヤード台が堂々と鎮座し、隅には見たこともないボードゲームの箱が山積みになっていた。そして、中央に置かれたテーブルの上にはティーポットと、両脇に生えた小さな腕で器用にカードを切るランタンが載り、側には蝙蝠傘が立っていた。
「やいやいホーキガミ! 新入りの癖に一番遅えたあどういう了見だい!」
「後ろの二人組はどうした?」
「カード配るぞー」
ホーキガミの姿を見とめると、ティーポットと蝙蝠傘とランタンは口々に好き勝手まくし立てた。モップが動いて喋った時点で、他にも日用品型の人形がいてもおかしくないとは思っていたが、三体同時に現れ、喋り出されるとさすがに頭がくらくらしてくる。
「案山子みてえに突っ立ってねえで、座りねえ」
ホーキガミに促され、蝙蝠傘が持ち手の部分で引きずってきた椅子に座ると、ティーポットがカードを配り始めた。細かな唐草模様のカードの裏を見ると、金色の二重丸が描かれている。見たことのない絵柄に戸惑っているうちに、手の中には銀色の逆十字とクエスチョンマークも追加された。
「ほほう。さしずめペンタクルとソードとワンドってとこかな?」
俺の後ろでカードを見ていたシンディが、カードの模様を解釈した。言われてみれば、タロットカードの小アルカナのスートに似ているかもしれない。
「ところで、シンディ……ええと、後ろのかれ、いや、彼女か?……後ろの子供の分の椅子とカードはどこですか?」
性別を言い淀んだ挙げ句「子供」と言った辺りで、シンディに少し睨まれた。
「ごめんよ、椅子はそれ一脚っきゃねえんだ。だから、そっちの兄ちゃんは俺とビリヤードでもどうだい?」
「いいね。えーと、私は普通のキューを使っていいんだよね?」
蝙蝠傘がビリヤード台に持ち手を引っ掛けながら誘ったので、若干トンチンカンな受け答えをしながらもシンディは応じた。
カードが配られてもなお薄目で唸っていると、ランタンが光り始めた。
「ちょいと暗かったかもな」
別に、カードがよく見えなくて唸っていたわけではなく、カードの柄の意味を図りかねていただけだ。確かに、はめ殺しの窓は小さく、すぐ外に森が迫っているため光はほとんど入ってこないが、それはどこの部屋もそうだったのでもう慣れた。
その旨を伝えると、ホーキガミがカードの柄の意味とゲームのルールを教えてくれた。シンディの読みは概ね正しく、銀の逆十字とクエスチョンマークがそれぞれ短剣と棍棒、金の二重丸と半円がそれぞれ金貨と杯だった。
「俺っちチョーチン。俺っちとお前がチームだぞ」
テーブルの真向かいに載った光るランタンが、嬉々としてそう言った。ゲームは、ホイストをよりシンプルにしたようなルールだったから、初プレイでもそれなりに戦えそうだ。
「あっしがチャガマで、あいつはカラカサ。ま、よければ覚えてくんな」
ティーポットが蝙蝠傘を指しながら名乗ると、
「おい、お前の名前は「ブンブクチャガマ」だろ、略すな」
とホーキガミが茶化した。
「だって、「ブンブク」とかダセエじゃねえかよ。おっ、あっしが親か」
チャガマは不貞腐れながら杯の十四を出した。彼らが使うカードの強さはトランプと逆で、小さいほど強い。
数字が小さいほど強い。ただそれだけを頭に入れればそれなりに善戦できたはずが、何度も強さを勘違いしたせいで手ひどく負けた。仲間だったチョーチンからの視線が痛い。
「ふう。良い勝負だったね」
俺とほぼ同時に勝負を終えたシンディは、勝ったようだった。しかも、勝負の最中にこちらの会話を聞く余裕まであったらしく、
「ルールは聞こえてたし、次は私と一戦お願いできるかな」
と人差し指を立ててウインクして見せた。
「おう、受けてたつぜ!」
シンディが言い終わるか言い終わらないかくらいに、もうチョーチンはカードを集めて切りはじめていた。
チョーチンがカードを配り始だした辺りで、小さな違和感を覚えた。さっきカードを配った時の記憶と、何かが微妙に違う。
「もしかして、チョーチンは両利きなのか?」
チョーチンは、さっきとは逆の手でカードを配っていたのだ。
「りょーきき? 何だそれ?」
チョーチンは灯りを点け消しして分からないことを表明した。
「おいらも聞いたことねえなあ」
ホーキガミをはじめ、他の面々も「両利き」という言葉を知らないようだった。
「当たり前じゃない、彼らは人形なんだから。左右同じように作られていれば、両手は同じくらい器用なのが自然だよ」
当人達が誰も質問内容を理解していない中、シンディが事も無げに答えた。言われてみれば、確かにそうだ。
「それより、部屋に入った時にチャガマさんが言ってた「ホーキガミさんは新入り」って、どういう意味?」
シンディはカードを出しながら聞いた。何気なく聞いているように見えるが、部屋に入った直後からずっとこの質問をする隙を伺っていたようだ。
「そりゃあ、ホーキガミが一番新しく作られたってだけの話さ」
「あっしらは作られてから十年以上経ってるが、ホーキガミだけは、まだ一年経ってねえのよ」
こちらの質問には、カラカサとチャガマがあっさり答えた。沢山いるところだけ見るとつい忘れてしまうが、人形を作るのには時間も手間も掛かる。作られた時期に差が出るのは、当然と言えば当然だ。
「おっ、ラッキー! また俺っちの勝ちだな」
そうこうしているうちにもゲームは進み、チョーチンとシンディは順調に勝ちへの道筋を進んでいた。
「姉ちゃんはスジがいいな。さっきの奴とは大違いだ」
負けているはずのチャガマも、俺を貶しつつシンディを誉めている。
カラカサと交代で抜けて暇なはずのホーキガミも、同じく暇な俺には目もくれず勝負を見つめている。
「これで私達の勝ちだね。ありがとう、なかなか楽しいゲームだったよ」
初心者とは思えないカード捌きで勝利を決めると、シンディはそう言って席を立った。俺も慌てて後を追う。
「ありがとう、負けてしまったけど俺も楽しかったよ。チョーチンには悪いことしたな、ごめん」
早口で礼を述べると、
「まあいいのさ、たまには初心者と遊ぶのも楽しかったぜ」
「もう行っちまうのか」
「頑張れよー」
「もし暇なら、南側の部屋にも行ってやってくれねえか。そこそこ楽しめるとは思うぜ」
やっぱり口々に好き勝手なことを言われた。
[17年09月30日 14:28]
「さ、着いたぞ。ここが俺達の遊戯室だ」
三階の北廊下十二番目の部屋のドアを開けながら、ホーキガミは大きな声で俺達を促した。
その部屋にはダーツ盤やビリヤード台が堂々と鎮座し、隅には見たこともないボードゲームの箱が山積みになっていた。そして、中央に置かれたテーブルの上にはティーポットと、両脇に生えた小さな腕で器用にカードを切るランタンが載り、側には蝙蝠傘が立っていた。
「やいやいホーキガミ! 新入りの癖に一番遅えたあどういう了見だい!」
「後ろの二人組はどうした?」
「カード配るぞー」
ホーキガミの姿を見とめると、ティーポットと蝙蝠傘とランタンは口々に好き勝手まくし立てた。モップが動いて喋った時点で、他にも日用品型の人形がいてもおかしくないとは思っていたが、三体同時に現れ、喋り出されるとさすがに頭がくらくらしてくる。
「案山子みてえに突っ立ってねえで、座りねえ」
ホーキガミに促され、蝙蝠傘が持ち手の部分で引きずってきた椅子に座ると、ティーポットがカードを配り始めた。細かな唐草模様のカードの裏を見ると、金色の二重丸が描かれている。見たことのない絵柄に戸惑っているうちに、手の中には銀色の逆十字とクエスチョンマークも追加された。
「ほほう。さしずめペンタクルとソードとワンドってとこかな?」
俺の後ろでカードを見ていたシンディが、カードの模様を解釈した。言われてみれば、タロットカードの小アルカナのスートに似ているかもしれない。
「ところで、シンディ……ええと、後ろのかれ、いや、彼女か?……後ろの子供の分の椅子とカードはどこですか?」
性別を言い淀んだ挙げ句「子供」と言った辺りで、シンディに少し睨まれた。
「ごめんよ、椅子はそれ一脚っきゃねえんだ。だから、そっちの兄ちゃんは俺とビリヤードでもどうだい?」
「いいね。えーと、私は普通のキューを使っていいんだよね?」
蝙蝠傘がビリヤード台に持ち手を引っ掛けながら誘ったので、若干トンチンカンな受け答えをしながらもシンディは応じた。
カードが配られてもなお薄目で唸っていると、ランタンが光り始めた。
「ちょいと暗かったかもな」
別に、カードがよく見えなくて唸っていたわけではなく、カードの柄の意味を図りかねていただけだ。確かに、はめ殺しの窓は小さく、すぐ外に森が迫っているため光はほとんど入ってこないが、それはどこの部屋もそうだったのでもう慣れた。
その旨を伝えると、ホーキガミがカードの柄の意味とゲームのルールを教えてくれた。シンディの読みは概ね正しく、銀の逆十字とクエスチョンマークがそれぞれ短剣と棍棒、金の二重丸と半円がそれぞれ金貨と杯だった。
「俺っちチョーチン。俺っちとお前がチームだぞ」
テーブルの真向かいに載った光るランタンが、嬉々としてそう言った。ゲームは、ホイストをよりシンプルにしたようなルールだったから、初プレイでもそれなりに戦えそうだ。
「あっしがチャガマで、あいつはカラカサ。ま、よければ覚えてくんな」
ティーポットが蝙蝠傘を指しながら名乗ると、
「おい、お前の名前は「ブンブクチャガマ」だろ、略すな」
とホーキガミが茶化した。
「だって、「ブンブク」とかダセエじゃねえかよ。おっ、あっしが親か」
チャガマは不貞腐れながら杯の十四を出した。彼らが使うカードの強さはトランプと逆で、小さいほど強い。
数字が小さいほど強い。ただそれだけを頭に入れればそれなりに善戦できたはずが、何度も強さを勘違いしたせいで手ひどく負けた。仲間だったチョーチンからの視線が痛い。
「ふう。良い勝負だったね」
俺とほぼ同時に勝負を終えたシンディは、勝ったようだった。しかも、勝負の最中にこちらの会話を聞く余裕まであったらしく、
「ルールは聞こえてたし、次は私と一戦お願いできるかな」
と人差し指を立ててウインクして見せた。
「おう、受けてたつぜ!」
シンディが言い終わるか言い終わらないかくらいに、もうチョーチンはカードを集めて切りはじめていた。
チョーチンがカードを配り始だした辺りで、小さな違和感を覚えた。さっきカードを配った時の記憶と、何かが微妙に違う。
「もしかして、チョーチンは両利きなのか?」
チョーチンは、さっきとは逆の手でカードを配っていたのだ。
「りょーきき? 何だそれ?」
チョーチンは灯りを点け消しして分からないことを表明した。
「おいらも聞いたことねえなあ」
ホーキガミをはじめ、他の面々も「両利き」という言葉を知らないようだった。
「当たり前じゃない、彼らは人形なんだから。左右同じように作られていれば、両手は同じくらい器用なのが自然だよ」
当人達が誰も質問内容を理解していない中、シンディが事も無げに答えた。言われてみれば、確かにそうだ。
「それより、部屋に入った時にチャガマさんが言ってた「ホーキガミさんは新入り」って、どういう意味?」
シンディはカードを出しながら聞いた。何気なく聞いているように見えるが、部屋に入った直後からずっとこの質問をする隙を伺っていたようだ。
「そりゃあ、ホーキガミが一番新しく作られたってだけの話さ」
「あっしらは作られてから十年以上経ってるが、ホーキガミだけは、まだ一年経ってねえのよ」
こちらの質問には、カラカサとチャガマがあっさり答えた。沢山いるところだけ見るとつい忘れてしまうが、人形を作るのには時間も手間も掛かる。作られた時期に差が出るのは、当然と言えば当然だ。
「おっ、ラッキー! また俺っちの勝ちだな」
そうこうしているうちにもゲームは進み、チョーチンとシンディは順調に勝ちへの道筋を進んでいた。
「姉ちゃんはスジがいいな。さっきの奴とは大違いだ」
負けているはずのチャガマも、俺を貶しつつシンディを誉めている。
カラカサと交代で抜けて暇なはずのホーキガミも、同じく暇な俺には目もくれず勝負を見つめている。
「これで私達の勝ちだね。ありがとう、なかなか楽しいゲームだったよ」
初心者とは思えないカード捌きで勝利を決めると、シンディはそう言って席を立った。俺も慌てて後を追う。
「ありがとう、負けてしまったけど俺も楽しかったよ。チョーチンには悪いことしたな、ごめん」
早口で礼を述べると、
「まあいいのさ、たまには初心者と遊ぶのも楽しかったぜ」
「もう行っちまうのか」
「頑張れよー」
「もし暇なら、南側の部屋にも行ってやってくれねえか。そこそこ楽しめるとは思うぜ」
やっぱり口々に好き勝手なことを言われた。
[17年09月30日 14:28]
[332149]黒井由紀
遊戯室を出た俺達は、どちらからともなく南側の部屋に行くことを決めた。あの気のいいホーキガミの好意をふいにするのはためらわれたし、「行ってやってくれ」と頼むような何かがあることは確かだと思われたからだ。
角張ったC字形の廊下を二回折れると、ホーキガミの言っていた部屋はすぐに分かった。なぜならそこには金色に光る豪華な金属ドア一枚きりしか無かったからである。
まばゆいドアを開けると、中には更にまばゆい空間が広がっていた。軽やかに垂れ下がる金のシャンデリア、壁一面に張られたピカピカ光る鏡……水面のような広い大理石の床では、色とりどりに着飾った何組もの男女が踊っている。
「ようこそ! お客さまね? さあ、こちらにいらして!」
部屋の豪華さに圧倒される間もなく、頭に金色の巻きねじが付いた女性に、さらうように手を取られた。女性は、ホールに響き渡る音楽に合わせて踊り始める。辺りを見回すと、つい先ほどまで彼女と踊っていた男性が、シンディに声を掛けていた。
音楽の出所は、ホールの中央に置かれた装置のようだった。機織り機のような部分の糸をいくつかの歯車が縦横無尽に巻き取ると、上部の複雑な多面体が開閉を繰り返しながら震える。これまでに見たことのあるどの楽器にも似ていないが、間違いなくあれは楽器だ。
「あれが気になる? あれは、ビブロナルパって楽器よ。綺麗な音色でしょ?」
女性は、黄色いドレスを翻しながら、歌うように囁いた。彼女のいう通り、金属性の多面体の響きは心地よく、幻想的な美しさだ。奏でられている音楽もどこか夢見るようなメロディで、心なしか体が軽く感じられる。
「あの、あなたは何者なんですか? あと、さっきまで一緒に踊っていた男性は……?」
放ったらかしていいんですか、というニュアンスを込めて尋ねたつもりだが、
「私はアン。彼はロイド。ロイドは私の弟なの」
と、明後日の方向を向いた答えしか受けられなかった。
「はあ、弟ですか……」
シンディと踊る男性を横目で見る。物腰は柔らかく、指の先まで優雅さと気品に満ちている。シンディとどんな話をしているかは聞こえてこないが、少なくとも目の前の無邪気な女性よりは大人に見える。
「まあ、失礼な! こう見えても私、このホールで一番お姉さんなのよ!」
ダンスのステップに合わせて、アンは誇らしげに胸を反らす。金色の巻きねじが、シャンデリアを映しながら回る。
「一番お姉さん、か。じゃあアンさんは、いつ作られたんですか?」
遊戯室でシンディがした質問を思い返して問う。が、
「やだあ! レディに歳を聞いちゃダメよ」
と張り倒された。勢いよく突き出された右手に、黄色いリボンが巻かれていた。他の女性の手首には、何も付いていない。
「その右手のリボン、どうしたんですか?」
「これ? 腕の皮にヒビが入っちゃったんだけど、部品が無かったから代わりにってコッペリアちゃんが巻いてくれたの!」
満面の笑みを浮かべてアンは頷いた。左回りに巻かれた光沢のあるリボンがよほど嬉しかったらしい。
その後すぐに体勢を立て直し、元通り踊りだした。アンはかなり踊るのが上手いらしく、実は誰とも踊っていないのではないかと疑いかけるほど軽かった。
踊っていると、シンディとロイドとすれ違った。すれ違う時、シンディはここぞとばかりに複雑なステップを踏んで見せた。シンディがここまでダンスを踊れるなんて知らなかった。
いや、違う。俺はシンディについて、名前と謎解きが得意だということ以外何も知らないのだ。何せ、出会いの瞬間から俺とシンディの間には謎があって、その後も謎に関係なく会うことはなかったから。
「ねえ、あなたはあの子のことが好きなの?」
シンディの方を見ていたら、アンが耳打ちした。元々話好きらしく、さっきまで黙っていたのも、話題を探していただけのようだ。
「恋愛感情って訳じゃありません。ただ、これからもずっと一緒に謎を解きたいってだけです。シンディには、俺には見えないものが見えるから、一緒に解き続けていたら、何かすごいものが見られそうな気がするんです」
普段思っていることではあるのだが、改めて言葉にしてみると、かなり恥ずかしい。
「ふうん。シンディさんに憧れてるのね」
アンが選んだ「憧れ」という言葉は、俺の心情にしっくりと当て嵌まった。あの視点に、あの閃きに、あの気付きに、俺は憧れている。
「私も、ロイドが大好き! ロイドと一緒に、ずうっと踊っていたいわ!」
アンは、そう言うと顔を綻ばせた。これを言うために話題を振ったのかもしれない。
「一緒にずっと、か。あるいは君と彼になら、それも可能かもしれないな」
不完全かもしれないが永遠を与えられたアンが語る「永遠」は、「永遠」とは縁遠い俺にも夢を与えた。彼女の夢が、少しでも長く叶えばいい。
音楽が止むと、アンはスカートを持ってお辞儀をして、すぐにロイドの元へと駆けて行った。シンディの方を見やると、ロイドも丁寧なお辞儀をしていたが、アンの笑顔を見つけた途端に顔を綻ばせた。この二人は、全く同じ顔で笑うのか。
「ホーキガミさんの言った通り、なかなか刺激的だったね」
合流すると、開口一番にシンディはそう言った。シンディの言っているのと同じ意味かは分からないが、確かに俺もドキドキさせられた。
「色々話も聞けたし。あ、そうそう。ロイドさんは城主じゃないよ。足の踵に巻きねじが付いてたから」
踊りながら踵の巻きねじを見付けるとは、流石の観察眼だ。そう誉めようとしたら、
「あのねじ巻き部屋にあった切れ込みの高さの辺りを重点的に見ただけだよ」
と先に種明かしされてしまった。
[17年09月30日 14:28]
遊戯室を出た俺達は、どちらからともなく南側の部屋に行くことを決めた。あの気のいいホーキガミの好意をふいにするのはためらわれたし、「行ってやってくれ」と頼むような何かがあることは確かだと思われたからだ。
角張ったC字形の廊下を二回折れると、ホーキガミの言っていた部屋はすぐに分かった。なぜならそこには金色に光る豪華な金属ドア一枚きりしか無かったからである。
まばゆいドアを開けると、中には更にまばゆい空間が広がっていた。軽やかに垂れ下がる金のシャンデリア、壁一面に張られたピカピカ光る鏡……水面のような広い大理石の床では、色とりどりに着飾った何組もの男女が踊っている。
「ようこそ! お客さまね? さあ、こちらにいらして!」
部屋の豪華さに圧倒される間もなく、頭に金色の巻きねじが付いた女性に、さらうように手を取られた。女性は、ホールに響き渡る音楽に合わせて踊り始める。辺りを見回すと、つい先ほどまで彼女と踊っていた男性が、シンディに声を掛けていた。
音楽の出所は、ホールの中央に置かれた装置のようだった。機織り機のような部分の糸をいくつかの歯車が縦横無尽に巻き取ると、上部の複雑な多面体が開閉を繰り返しながら震える。これまでに見たことのあるどの楽器にも似ていないが、間違いなくあれは楽器だ。
「あれが気になる? あれは、ビブロナルパって楽器よ。綺麗な音色でしょ?」
女性は、黄色いドレスを翻しながら、歌うように囁いた。彼女のいう通り、金属性の多面体の響きは心地よく、幻想的な美しさだ。奏でられている音楽もどこか夢見るようなメロディで、心なしか体が軽く感じられる。
「あの、あなたは何者なんですか? あと、さっきまで一緒に踊っていた男性は……?」
放ったらかしていいんですか、というニュアンスを込めて尋ねたつもりだが、
「私はアン。彼はロイド。ロイドは私の弟なの」
と、明後日の方向を向いた答えしか受けられなかった。
「はあ、弟ですか……」
シンディと踊る男性を横目で見る。物腰は柔らかく、指の先まで優雅さと気品に満ちている。シンディとどんな話をしているかは聞こえてこないが、少なくとも目の前の無邪気な女性よりは大人に見える。
「まあ、失礼な! こう見えても私、このホールで一番お姉さんなのよ!」
ダンスのステップに合わせて、アンは誇らしげに胸を反らす。金色の巻きねじが、シャンデリアを映しながら回る。
「一番お姉さん、か。じゃあアンさんは、いつ作られたんですか?」
遊戯室でシンディがした質問を思い返して問う。が、
「やだあ! レディに歳を聞いちゃダメよ」
と張り倒された。勢いよく突き出された右手に、黄色いリボンが巻かれていた。他の女性の手首には、何も付いていない。
「その右手のリボン、どうしたんですか?」
「これ? 腕の皮にヒビが入っちゃったんだけど、部品が無かったから代わりにってコッペリアちゃんが巻いてくれたの!」
満面の笑みを浮かべてアンは頷いた。左回りに巻かれた光沢のあるリボンがよほど嬉しかったらしい。
その後すぐに体勢を立て直し、元通り踊りだした。アンはかなり踊るのが上手いらしく、実は誰とも踊っていないのではないかと疑いかけるほど軽かった。
踊っていると、シンディとロイドとすれ違った。すれ違う時、シンディはここぞとばかりに複雑なステップを踏んで見せた。シンディがここまでダンスを踊れるなんて知らなかった。
いや、違う。俺はシンディについて、名前と謎解きが得意だということ以外何も知らないのだ。何せ、出会いの瞬間から俺とシンディの間には謎があって、その後も謎に関係なく会うことはなかったから。
「ねえ、あなたはあの子のことが好きなの?」
シンディの方を見ていたら、アンが耳打ちした。元々話好きらしく、さっきまで黙っていたのも、話題を探していただけのようだ。
「恋愛感情って訳じゃありません。ただ、これからもずっと一緒に謎を解きたいってだけです。シンディには、俺には見えないものが見えるから、一緒に解き続けていたら、何かすごいものが見られそうな気がするんです」
普段思っていることではあるのだが、改めて言葉にしてみると、かなり恥ずかしい。
「ふうん。シンディさんに憧れてるのね」
アンが選んだ「憧れ」という言葉は、俺の心情にしっくりと当て嵌まった。あの視点に、あの閃きに、あの気付きに、俺は憧れている。
「私も、ロイドが大好き! ロイドと一緒に、ずうっと踊っていたいわ!」
アンは、そう言うと顔を綻ばせた。これを言うために話題を振ったのかもしれない。
「一緒にずっと、か。あるいは君と彼になら、それも可能かもしれないな」
不完全かもしれないが永遠を与えられたアンが語る「永遠」は、「永遠」とは縁遠い俺にも夢を与えた。彼女の夢が、少しでも長く叶えばいい。
音楽が止むと、アンはスカートを持ってお辞儀をして、すぐにロイドの元へと駆けて行った。シンディの方を見やると、ロイドも丁寧なお辞儀をしていたが、アンの笑顔を見つけた途端に顔を綻ばせた。この二人は、全く同じ顔で笑うのか。
「ホーキガミさんの言った通り、なかなか刺激的だったね」
合流すると、開口一番にシンディはそう言った。シンディの言っているのと同じ意味かは分からないが、確かに俺もドキドキさせられた。
「色々話も聞けたし。あ、そうそう。ロイドさんは城主じゃないよ。足の踵に巻きねじが付いてたから」
踊りながら踵の巻きねじを見付けるとは、流石の観察眼だ。そう誉めようとしたら、
「あのねじ巻き部屋にあった切れ込みの高さの辺りを重点的に見ただけだよ」
と先に種明かしされてしまった。
[17年09月30日 14:28]
[332148]黒井由紀
「次に行くべき場所は、アトリエだな」
カラカサとチャガマや、アンの話から考えれば、この城内には人形を作ったり修理したりするための部屋があるはずだ。
「そうだね。どこにあるかは分からないけど」
「……細かい場所までは分からなくても、一階にある可能性が高いことくらいは分かるぞ」
俺が言うと、シンディは目をしばたたかせた。
「人形を作るには材料がいる。が、その材料は城内では手に入らないだろう」
「なるほど、材料を運び込む手間を考えれば、アトリエは一階に配置するのが正解だね」
シンディが頷いたので、廊下を曲がってすぐの階段から一階へ降りた。
階段を降り、すぐそばのドアを開けようとすると、シンディに止められた。
「ライナー君、開けちゃダメ」
引き留められ、まじまじとドアを見て、またかとため息を吐いた。俺が開けようとしていたものは、壁に埋め込まれたドアノブと、その回りに描かれた騙し絵に過ぎなかった。
「ちょっと油断するとこれだもんな。人形屋敷は探索するのも楽じゃないね」
よくよく考えれば、このドアのすぐ上階はねじ巻き部屋だ。下階のここでねじを巻くための力を作っているのなら、こちらからは入れなくなっていてもさほどおかしくない。騙し絵に耳を当てると、地の底を這うような振動と音が微かに漏れ聞こえた。
前に入った部屋は外して、一階の部屋を虱潰しに探索して回る。一階には生活に関わるような部屋が多く、洗濯室やミシン部屋では複数の人形達が猛然と仕事をこなしていた。
いくつかの部屋を見た後、俺達はその部屋に辿り着いた。ドアノブを回そうとしても、鍵が掛かって動かない部屋。ドアノブがガチャッと鳴って止まった瞬間、こここそがアトリエに違いないと確信した。
「……コッペリアさんを呼んでこよう」
俺がそう言った時には、シンディはもう玄関ホールへと駆け出していた。
背筋をぴんと伸ばして玄関ホールに立っていたコッペリアを連れて、鍵の掛かったドアの前へ急ぐ。ドアの錠は、コッペリアの持っていた鍵で開いた。
目に飛び込むのは、果てしない白。頭、胴体、腕、脚……まだ人形になる前のパーツが、所狭しと並べられている。中には組み立てられかけた物もあったが、それがコッペリア達のように生き生きと動き出す姿は想像できなかった。窓も無くひんやりと陰気な室内は、カタコンベの中とやけに似ていた。
いのちが吹き込まれる前の物と、死とは、こんなにも近しかっただろうか。
されども、ここから生み出されたはずのコッペリア達は、不死なのだ。その矛盾はなんとなく可笑しくて、哀しかった。
シンディも俺同様押し黙っていたが、それは感傷のせいではなく、冷静な観察のためのようだと視線の鋭さで分かった。すでに、棚に大量に差された設計図を丹念に一枚一枚読んでいる。
「これが人形を作るための道具かな」
ペンチやニッパーから裁ち鋏まで、人形作りに使うあらゆる道具は薄いアルミの箱に雑多に押し込まれていた。どれもこれも年季が入っていて、中にはもう実用に耐えないであろうものもある。そして、
「これも左利き用だ……」
利き手によって使いやすさの変わる道具はすべて左利き用だった。
「城主は左利きだ」
人形達に利き手はないが、城主にはある。それを念頭に置いてここまでの記憶を反芻する。まぶしいレモンイエローが、一つの可能性を照らし出していた。
「コッペリアさん。すみませんが、これを見て貰えませんか?」
左手でポケットの万年筆を取り、なるべく自然に取り落とした。俺の万年筆は、そのままコッペリアの右足のそばに転がる。
「落とされましたよ。それで、これを見てどうすれば良いのですか?」
コッペリアは、体を少し回して、左手で万年筆を取った これで決まりだ。
「いえ、もう結構です。コッペリアさん、あなたが城主ですね」
思い返してみれば、はじめの会話からして少し不自然だったのだ。最初にコッペリアは人形かと言った時、彼女は肯定も否定もしなかったし、その後も一度たりとも自分のことを人形だとは言わなかった。
「ライナー君、どうしてその結論に辿り着いたの?」
「きっかけは、アンのリボンだ。彼女の腕には、ひび割れの応急措置としてコッペリアの手によってリボンが左回りに巻かれていた。リボンを向かい合わせた相手の腕に巻いて、仕上がりが左回りになるのはリボンを左手に持ったときだけだ。そこからもしや、と思って、万年筆を落としてみた。利き手のない人形なら、間違いなく近い方の右手で拾うはずだが、彼女は左手で拾った」
「なかなかの推理だね。さすが元探偵。それで、コッペリアさん、あなたは城主なんですか?」
俺の推理に乗ったシンディも、畳み掛ける。
「その質問には、お答えできません」
それでも、コッペリアの回答はにべもない。まあ、館内の者全員に聞いて回られたら、ゲームにならなくなってしまうから、当然と言えば当然かもしれないが。
だが、根拠のある指摘でも回答拒否となると、何かもっと根本的な点を突かなければ、コッペリアが城主だと認めることはないだろう。せっかく辿り着いたと思ったのに、実際はまだまだだったというわけか。
「じゃあ、コッペリアさん。その背中の巻きねじ、よく見せてもらっても良い?」
俺が項垂れた時に、シンディはそう質問した。シンディには、まだ策があるらしかった。
「はい、構いません」
そう言い、コッペリアは背中の巻きねじをこちらに向けた。金色の巻きねじは、音もなく回っている。
「もし、コッペリアさんが人間なら、背中の巻きねじは要らないし、最初の忠告にあった「人形や家具を破壊しない」にも該当しない」
呟きながら、シンディは巻きねじを手に取り、強く引っ張った。
「入口の門にはさ、鍵穴があったよね」
引き抜かれた巻きねじの先端には、ちょうど入り口の鍵穴に入る大きさの鍵が付いていた。
「さあ、館を出よう」
鍵を手に入れ、アトリエを後にしようとした瞬間背後で強烈な警報音が鳴った。ふと振り替えると、魂が抜けたように硬直したコッペリアが、そのガラス玉の瞳をこちらに向けていた。
廊下に出ると、左右から重たい音が聞こえた。片方は重いものを引きずるような音で、もう片方は金属製の何かが動く音だ。音の主が姿を現すより早く、俺達は玄関ホールに駆け込んだ。
「行くよ」
短く言ってシンディが鍵を開けようとした時、俺は思わずシンディの手を掴んでいた。
「ダメだ。きっとその鍵じゃ出られない」
巻きねじを取られて硬直したコッペリアは、どう見ても人間ではなかった。それに加えて、あの警報音と二つの重い音のことがある。あれは、もしかしたら禁を犯した者へのペナルティなのかもしれない。
「でも、どうするのさ」
だんだん近づいてくる二つの重い音で、シンディもかなり焦っている。
「巻きねじをコッペリアに返して、他のことはその後考える」
できるだけ落ち着いた声でそう言うと、シンディは無言で巻きねじを私に押し付けた。
「分かった、俺が行ってくる。シンディはどこか適当な部屋に隠れていてくれ」
そこまで言った所で、二つの重い音の主が玄関ホールに姿を現した。重いものを引きずるような音の主は巨大な土くれ人形で、金属製の何かが動く音の主は大きな箱を人型に積み重ねただけのような外見のロボットだった。
「行くぞ」
シンディの背中を押し、自分も駆け出す。二体の人形の動線を避けつつ、アトリエを目指す。彼らの動きは緩慢そうに見えて速く、大した距離を走っていないのに、アトリエに着いた頃には息が上がった。
コッペリアの背中に鍵を突き刺す。まだ警報音は鳴っている。
俺の行動は間違いだったのか? 刹那、そんな思考が額に冷や汗を浮かばせる。
そして、次の瞬間、警報音は止んだ。
俺はため息を吐き、コッペリアは何事もなかったかのように生者の笑みを取り戻した。とりあえず、どうにかなったらしい。
「コッペリアさん、さっきは失礼しました。それと、この部屋の探索はもう大丈夫です。ありがとうございました」
コッペリアに詫びと礼を述べ、俺はアトリエを離れた。シンディのいる部屋を探さなければ。
[17年09月30日 14:27]
「次に行くべき場所は、アトリエだな」
カラカサとチャガマや、アンの話から考えれば、この城内には人形を作ったり修理したりするための部屋があるはずだ。
「そうだね。どこにあるかは分からないけど」
「……細かい場所までは分からなくても、一階にある可能性が高いことくらいは分かるぞ」
俺が言うと、シンディは目をしばたたかせた。
「人形を作るには材料がいる。が、その材料は城内では手に入らないだろう」
「なるほど、材料を運び込む手間を考えれば、アトリエは一階に配置するのが正解だね」
シンディが頷いたので、廊下を曲がってすぐの階段から一階へ降りた。
階段を降り、すぐそばのドアを開けようとすると、シンディに止められた。
「ライナー君、開けちゃダメ」
引き留められ、まじまじとドアを見て、またかとため息を吐いた。俺が開けようとしていたものは、壁に埋め込まれたドアノブと、その回りに描かれた騙し絵に過ぎなかった。
「ちょっと油断するとこれだもんな。人形屋敷は探索するのも楽じゃないね」
よくよく考えれば、このドアのすぐ上階はねじ巻き部屋だ。下階のここでねじを巻くための力を作っているのなら、こちらからは入れなくなっていてもさほどおかしくない。騙し絵に耳を当てると、地の底を這うような振動と音が微かに漏れ聞こえた。
前に入った部屋は外して、一階の部屋を虱潰しに探索して回る。一階には生活に関わるような部屋が多く、洗濯室やミシン部屋では複数の人形達が猛然と仕事をこなしていた。
いくつかの部屋を見た後、俺達はその部屋に辿り着いた。ドアノブを回そうとしても、鍵が掛かって動かない部屋。ドアノブがガチャッと鳴って止まった瞬間、こここそがアトリエに違いないと確信した。
「……コッペリアさんを呼んでこよう」
俺がそう言った時には、シンディはもう玄関ホールへと駆け出していた。
背筋をぴんと伸ばして玄関ホールに立っていたコッペリアを連れて、鍵の掛かったドアの前へ急ぐ。ドアの錠は、コッペリアの持っていた鍵で開いた。
目に飛び込むのは、果てしない白。頭、胴体、腕、脚……まだ人形になる前のパーツが、所狭しと並べられている。中には組み立てられかけた物もあったが、それがコッペリア達のように生き生きと動き出す姿は想像できなかった。窓も無くひんやりと陰気な室内は、カタコンベの中とやけに似ていた。
いのちが吹き込まれる前の物と、死とは、こんなにも近しかっただろうか。
されども、ここから生み出されたはずのコッペリア達は、不死なのだ。その矛盾はなんとなく可笑しくて、哀しかった。
シンディも俺同様押し黙っていたが、それは感傷のせいではなく、冷静な観察のためのようだと視線の鋭さで分かった。すでに、棚に大量に差された設計図を丹念に一枚一枚読んでいる。
「これが人形を作るための道具かな」
ペンチやニッパーから裁ち鋏まで、人形作りに使うあらゆる道具は薄いアルミの箱に雑多に押し込まれていた。どれもこれも年季が入っていて、中にはもう実用に耐えないであろうものもある。そして、
「これも左利き用だ……」
利き手によって使いやすさの変わる道具はすべて左利き用だった。
「城主は左利きだ」
人形達に利き手はないが、城主にはある。それを念頭に置いてここまでの記憶を反芻する。まぶしいレモンイエローが、一つの可能性を照らし出していた。
「コッペリアさん。すみませんが、これを見て貰えませんか?」
左手でポケットの万年筆を取り、なるべく自然に取り落とした。俺の万年筆は、そのままコッペリアの右足のそばに転がる。
「落とされましたよ。それで、これを見てどうすれば良いのですか?」
コッペリアは、体を少し回して、左手で万年筆を取った これで決まりだ。
「いえ、もう結構です。コッペリアさん、あなたが城主ですね」
思い返してみれば、はじめの会話からして少し不自然だったのだ。最初にコッペリアは人形かと言った時、彼女は肯定も否定もしなかったし、その後も一度たりとも自分のことを人形だとは言わなかった。
「ライナー君、どうしてその結論に辿り着いたの?」
「きっかけは、アンのリボンだ。彼女の腕には、ひび割れの応急措置としてコッペリアの手によってリボンが左回りに巻かれていた。リボンを向かい合わせた相手の腕に巻いて、仕上がりが左回りになるのはリボンを左手に持ったときだけだ。そこからもしや、と思って、万年筆を落としてみた。利き手のない人形なら、間違いなく近い方の右手で拾うはずだが、彼女は左手で拾った」
「なかなかの推理だね。さすが元探偵。それで、コッペリアさん、あなたは城主なんですか?」
俺の推理に乗ったシンディも、畳み掛ける。
「その質問には、お答えできません」
それでも、コッペリアの回答はにべもない。まあ、館内の者全員に聞いて回られたら、ゲームにならなくなってしまうから、当然と言えば当然かもしれないが。
だが、根拠のある指摘でも回答拒否となると、何かもっと根本的な点を突かなければ、コッペリアが城主だと認めることはないだろう。せっかく辿り着いたと思ったのに、実際はまだまだだったというわけか。
「じゃあ、コッペリアさん。その背中の巻きねじ、よく見せてもらっても良い?」
俺が項垂れた時に、シンディはそう質問した。シンディには、まだ策があるらしかった。
「はい、構いません」
そう言い、コッペリアは背中の巻きねじをこちらに向けた。金色の巻きねじは、音もなく回っている。
「もし、コッペリアさんが人間なら、背中の巻きねじは要らないし、最初の忠告にあった「人形や家具を破壊しない」にも該当しない」
呟きながら、シンディは巻きねじを手に取り、強く引っ張った。
「入口の門にはさ、鍵穴があったよね」
引き抜かれた巻きねじの先端には、ちょうど入り口の鍵穴に入る大きさの鍵が付いていた。
「さあ、館を出よう」
鍵を手に入れ、アトリエを後にしようとした瞬間背後で強烈な警報音が鳴った。ふと振り替えると、魂が抜けたように硬直したコッペリアが、そのガラス玉の瞳をこちらに向けていた。
廊下に出ると、左右から重たい音が聞こえた。片方は重いものを引きずるような音で、もう片方は金属製の何かが動く音だ。音の主が姿を現すより早く、俺達は玄関ホールに駆け込んだ。
「行くよ」
短く言ってシンディが鍵を開けようとした時、俺は思わずシンディの手を掴んでいた。
「ダメだ。きっとその鍵じゃ出られない」
巻きねじを取られて硬直したコッペリアは、どう見ても人間ではなかった。それに加えて、あの警報音と二つの重い音のことがある。あれは、もしかしたら禁を犯した者へのペナルティなのかもしれない。
「でも、どうするのさ」
だんだん近づいてくる二つの重い音で、シンディもかなり焦っている。
「巻きねじをコッペリアに返して、他のことはその後考える」
できるだけ落ち着いた声でそう言うと、シンディは無言で巻きねじを私に押し付けた。
「分かった、俺が行ってくる。シンディはどこか適当な部屋に隠れていてくれ」
そこまで言った所で、二つの重い音の主が玄関ホールに姿を現した。重いものを引きずるような音の主は巨大な土くれ人形で、金属製の何かが動く音の主は大きな箱を人型に積み重ねただけのような外見のロボットだった。
「行くぞ」
シンディの背中を押し、自分も駆け出す。二体の人形の動線を避けつつ、アトリエを目指す。彼らの動きは緩慢そうに見えて速く、大した距離を走っていないのに、アトリエに着いた頃には息が上がった。
コッペリアの背中に鍵を突き刺す。まだ警報音は鳴っている。
俺の行動は間違いだったのか? 刹那、そんな思考が額に冷や汗を浮かばせる。
そして、次の瞬間、警報音は止んだ。
俺はため息を吐き、コッペリアは何事もなかったかのように生者の笑みを取り戻した。とりあえず、どうにかなったらしい。
「コッペリアさん、さっきは失礼しました。それと、この部屋の探索はもう大丈夫です。ありがとうございました」
コッペリアに詫びと礼を述べ、俺はアトリエを離れた。シンディのいる部屋を探さなければ。
[17年09月30日 14:27]
[332147]黒井由紀
廊下を去っていく土くれ人形と箱ロボットを見送りながら、部屋を見て回る。幸い、シンディの隠れた部屋はすぐ見つかった。
オレンジ色の灯りがアンティーク家具を柔らかく照らすその部屋には、シンディと共に美しい少女が佇んでいた。はちみつ色の髪は光を乱反射するように波打ち、バラの刺繍が施されたドレスの上に落ちている。少女は時でも止まったかのように硬直して動かなかったが、微睡むようなかすかな笑みを浮かべた瓜実顔も相まって、童話の眠り姫を彷彿とさせた。
「作戦会議をやり直そうか。って言いたいところだけど、彼女のこと気になるよね?」
座っていたソファから飛び上がると、シンディは部屋の壁にぴったり付けて置かれたピアノの蓋を開けた。
シンディが適当に和音を鳴らすと、佇んでいた少女が体を動かし歌い始めた。圧倒的な響きがあるのにどこか虚ろなその声は、聞いている者を夢心地に誘う。そこで俺は、やっと彼女が人間ではないことを悟った。
彼女の声は、玄関ホールではじめに聞いた「録音」と全く同じだった。
「彼女は、ピアノの音に合わせて歌う人形なんだ。ライナー君も、何か弾いてみる?」
シンディが席を譲ったので、俺は大昔に習ったエチュードを弾いた。すっかり忘れているかと思ったが、意外と指は覚えているもので、最初から最後まで間違えずに弾き通せた。
「ライナー君ってピアノ弾けたんだね。なんかちょっと意外だよ」
「まあ、昔少し習っていただけだから、無理もないだろう。それにしても、彼女の歌声が付くと、まるで自分のピアノが上手くなったような気がするな」
俺は眠り姫改め歌姫の方を振り返ったが、彼女はすでに眠ったように動きを止めていた。他の人形とは違って、彼女は歌うためだけに作られたようだ。
「彼女……オランピアの声は、体内に組み込まれた人工声帯から出ているんだ。他の人形は、あらかじめ作成された音声をその時々に合わせて再生しているだけだけど、オランピアの声だけは、その場その場で新しく作られているってことだね。ただ、人工声帯がかさばるせいで、他の機能は付けられなかったみたい。アトリエにあった設計図に書かれてた」
「なるほど。どうりであの「録音」と同じ声の住人が見当たらないわけだ」
あの「録音」の妙な声は、声音を手掛かりとして攻略されてしまわないための対策だったらしい。つくづくここの城主は用意周到だ。
「あとね、ここの部屋で、もう一つ面白いものを見つけたんだよね。じゃーん」
シンディが効果音を口で言いながら取り出したのは、非常に長い白紙だった。よく見ると、長さの違う切れ込みが無数に入っている。
「ほう。それがこの世界における楽譜なのか?」
確信があったので、やや断定的に質問したが、シンディは曖昧に首を振った。
「おしい。楽譜、って言うよりはレコードかな」
白紙をピアノの上部に開いたスリットに通すと、ピアノは勝手に音楽を奏で始めた。
ピアノの音とオランピアの歌声を背景に、俺達はまず情報共有を始めた。俺の手帳にメモしてあった城の見取り図を開き、部屋ごとに見聞きした事や気になった事を書き込んでいく。
「角張ったC字型が三階分か。私達が見た限りでは隠し階段なんかも無かったし、三階建てで良さそうだね」
「ああ、俺もそう思う。で、一階のここがアトリエ、ここが洗濯室で、こっちはミシン部屋。キッチンはC字の下側の端だ」
「各部屋に置いてあった偽物や、各曲がり角に置かれた大鏡までちゃんとメモしてるのはさすがだね。けど、なんかこの紙小さくない?」
部屋を指さすと、指が二部屋以上の上に載ってしまうのを気にして、シンディがぼやいた。
「手帳はだいたいみんなこういう大きさだよ、仕方ないだろ。二階にあるのはねじ巻き部屋。これは、真下の部屋と繋がっているみたいだ」
「残った三階には、遊戯室とダンスホールがあったね。遊戯室にいたホーキガミの話からすると、C字の上が北で、下が南になるのかな」
一応、「異世界の常識」を繰って方角の概念が俺達のものと同じかを確認した。こちらの世界でも、日が昇るほうが東で日が沈むほうが西、北の反対は南で合っているようだ。
「ところでライナー君。君、アトリエでアンのリボンの話をしてたけど、ダンスホールでどんな話をしてたの?」
うっかりしていて、ダンスホールでの会話はまだ互いに情報共有していなかった。
「まず、リボンの話だろ。それから、ホールの中央に置かれた楽器が「ビブロナルパ」って名前だって教えてもらった。あと、ロイドはアンの弟で、アンはダンスホールにいた誰よりも先に作られたってことも聞いたな」
「ちょっと待って、それ本当?」
シンディが身を乗り出す。
「おかしいよ、それ。私が聞いた話では、ロイドはダンスホールの人形の中でも最後に、アンと同じ設計図から作られたらしいんだもの」
「ん? 別に矛盾はしてないじゃないか」
「矛盾こそしてないけど、アンとロイドの作られた時期に大きな開きがあるってことは、アンは長らくひとりぼっちだった、ってことになっちゃうじゃない」
アンの人懐っこい笑顔を思い出す。確かに、彼女が長期間パートナーなしで平気だとは思えなかった。すぐに寂しいと言い出しそうな気がする。
けれどもその想像は、もう一組の三階の住人達を思い出した瞬間、ぐにゃりと歪んだ。
「でも、遊戯室の方でもそうだったじゃないか。四人いないとできないゲームをしてたのに、最低でも九年以上、四人目となるホーキガミはいなかった……」
それを聞くと、シンディは飛び上がるように肩を震わせた。
「……分かった。アンもチャガマ達も別に、ずっと「ひとり足りない」状況じゃなかっただけだ」
シンディは確信に満ちた瞳で、重々しくそう言った。さっきとは完全に真逆のことを言いだしたのはともかく、急に表情が沈んだのが気になる。
「どういうことだ?」
「これは自分で考えてほしい。もし私の考えが間違ってるんなら、できればその方がいいし」
問うたものの、突き放されてしまった。シンディから聞き出すことは不可能そうだと判断して、自分で考えることにする。
アンには長いことパートナーのロイドがいなかった。チャガマ、カラカサ、チョーチンは、九年以上四人で遊ぶゲームができない環境下にいた。この二つを結ぶ共通点は、さっきシンディが言った「ひとり足りない」だ。この状況を解消するためには当然、もうひとりいればいい。
では、「ひとり足りない」を解消する「もうひとり」とは?
俺は、自分が座った一脚の椅子を思い出す。あれ一脚しかなかったことからも、あれが四人目のために用意されたと考えて良さそうな気がする。つまり、四人目は椅子に座れる大きさ・かたち――おそらく人型だ――をしている。けれども、器物の姿をした人形の中にひとりだけ人型をした者がいる、というのはなんだかおかしい。
それが、人型でしか存在できない、人間でもない限りは。
「そうか! アンと踊っていたのも、チャガマ達とゲームをしていたのも、城主だったのか!」
俺がひらめきを口にすると、シンディは一回だけ首を縦に振った。
「けど、一体どうして、城主は今更ロイドやホーキガミを作ったんだ?」
「……それはきっと、ずっと人形とだけ過ごしてきた城主が、今更人間を招いたのとも関係してるんじゃないかな」
俺が自問自答を始めてしまうと、シンディは遠慮がちに助け舟を出した。
「今更俺達を招いた理由? 寂しくなったのかと思っていたんだが」
「相手は長いこと人間を寄せ付けなかった城の主だよ。今更急に人間を呼び寄せるほど寂しくなるかな? しかも、せっかく呼んでおいて、直接会おうとはしない。寂しがっている人のすることとしてはあまりにも不自然だ」
「うっ、確かにそうだな」
「けどまあ、考え方はそこまで間違ってないよ」
シンディはそう励ましてくれた。まあ、シンディのことだから、本気でそこまで間違っていないとも思っているのだろうけど。
城主は何らかの目的を持って、人間を城に呼び寄せた。そして、ロイドとホーキガミを創った。この二つに共通するのは、「ひとり増やす」こと、と言えるかもしれない。
ひとり増やすことそのものは、特に理由なく行われることもあるだろう。だが、いくつかのバラバラの事柄に対して「ひとり増やす」ことを行おうとするのなら、そこには共通した理由があってもよさそうだ。
……例えば、「ひとり足りなく」なるから、とか。
その考えに行き着いた瞬間、ぞくり、と何かが背筋を這い上がる感覚を覚えた。昔「ウミガメのスープ」の正解に行き着いた時と、同じ感覚だ。これに違いないという確信と、答えに対する底知れない恐れ。
「もしかして、城主は……死んでいる?」
恐る恐る尋ねる。
「おそらくね」
シンディの短い答えで、俺には十分だった。
食べ物が一つもないキッチン、無人でねじを巻ける部屋の存在、「ひとり足りな」かった存在の補充……どれも城主が不在だと考えることで得心がいく。コッペリアが左利きなのも、自分の代わりに人形のメンテナンスをさせるためだったのではないか。
それ以上何と言ったものか分からず、俺とシンディは黙り込んでしまった。ピアノの音に彩られたオランピアの歌声が、部屋いっぱいに響き渡る。
朝日を浴びて私は眠る
銀のとびらを背にすれば きっと私が見通せる
会いたくなったら 上って下りて
金のとびらの向こうには 更に向こうには何もない
会いたくなったら 下りて下りて
他の曲を弾いた時にはただラララとしか歌わなかったオランピアだが、この曲だけは歌詞を付けて歌っている。それも、だいぶ変てこな歌詞を。
「ねえライナー君。もし城主が死んでいるとしたら、私達はここから出るために、何をすればいいと思う?」
しばらくの後、シンディが口を開いた。
「決まってるさ。城主を探すんだ」
「でも、城主はもうこの城にいないんだよ?」
「城主はいなくなる準備をしていた。きっとこの謎も、自分が死んだ後に解き明かさせるつもりだったはずだ」
城主を「見つける」ことで脱出できるのではなく、録音で言っていた通り「探す」ことで脱出できると考えれば、何ら問題はない。問題は城主を探す方法だが、それはもうシンディが見つけてくれた。
「なあシンディ、この歌における「私」って、誰だと思う?」
「へっ? 何を急に聞いてるの」
「俺は、城主自身だと思う。城主が作った「録音」と全く同じ声だからな」
「それは、この歌の歌詞こそが城主を探すヒントってこと?」
俺は、一度だけ首を縦に振った。
[17年09月30日 14:26]
廊下を去っていく土くれ人形と箱ロボットを見送りながら、部屋を見て回る。幸い、シンディの隠れた部屋はすぐ見つかった。
オレンジ色の灯りがアンティーク家具を柔らかく照らすその部屋には、シンディと共に美しい少女が佇んでいた。はちみつ色の髪は光を乱反射するように波打ち、バラの刺繍が施されたドレスの上に落ちている。少女は時でも止まったかのように硬直して動かなかったが、微睡むようなかすかな笑みを浮かべた瓜実顔も相まって、童話の眠り姫を彷彿とさせた。
「作戦会議をやり直そうか。って言いたいところだけど、彼女のこと気になるよね?」
座っていたソファから飛び上がると、シンディは部屋の壁にぴったり付けて置かれたピアノの蓋を開けた。
シンディが適当に和音を鳴らすと、佇んでいた少女が体を動かし歌い始めた。圧倒的な響きがあるのにどこか虚ろなその声は、聞いている者を夢心地に誘う。そこで俺は、やっと彼女が人間ではないことを悟った。
彼女の声は、玄関ホールではじめに聞いた「録音」と全く同じだった。
「彼女は、ピアノの音に合わせて歌う人形なんだ。ライナー君も、何か弾いてみる?」
シンディが席を譲ったので、俺は大昔に習ったエチュードを弾いた。すっかり忘れているかと思ったが、意外と指は覚えているもので、最初から最後まで間違えずに弾き通せた。
「ライナー君ってピアノ弾けたんだね。なんかちょっと意外だよ」
「まあ、昔少し習っていただけだから、無理もないだろう。それにしても、彼女の歌声が付くと、まるで自分のピアノが上手くなったような気がするな」
俺は眠り姫改め歌姫の方を振り返ったが、彼女はすでに眠ったように動きを止めていた。他の人形とは違って、彼女は歌うためだけに作られたようだ。
「彼女……オランピアの声は、体内に組み込まれた人工声帯から出ているんだ。他の人形は、あらかじめ作成された音声をその時々に合わせて再生しているだけだけど、オランピアの声だけは、その場その場で新しく作られているってことだね。ただ、人工声帯がかさばるせいで、他の機能は付けられなかったみたい。アトリエにあった設計図に書かれてた」
「なるほど。どうりであの「録音」と同じ声の住人が見当たらないわけだ」
あの「録音」の妙な声は、声音を手掛かりとして攻略されてしまわないための対策だったらしい。つくづくここの城主は用意周到だ。
「あとね、ここの部屋で、もう一つ面白いものを見つけたんだよね。じゃーん」
シンディが効果音を口で言いながら取り出したのは、非常に長い白紙だった。よく見ると、長さの違う切れ込みが無数に入っている。
「ほう。それがこの世界における楽譜なのか?」
確信があったので、やや断定的に質問したが、シンディは曖昧に首を振った。
「おしい。楽譜、って言うよりはレコードかな」
白紙をピアノの上部に開いたスリットに通すと、ピアノは勝手に音楽を奏で始めた。
ピアノの音とオランピアの歌声を背景に、俺達はまず情報共有を始めた。俺の手帳にメモしてあった城の見取り図を開き、部屋ごとに見聞きした事や気になった事を書き込んでいく。
「角張ったC字型が三階分か。私達が見た限りでは隠し階段なんかも無かったし、三階建てで良さそうだね」
「ああ、俺もそう思う。で、一階のここがアトリエ、ここが洗濯室で、こっちはミシン部屋。キッチンはC字の下側の端だ」
「各部屋に置いてあった偽物や、各曲がり角に置かれた大鏡までちゃんとメモしてるのはさすがだね。けど、なんかこの紙小さくない?」
部屋を指さすと、指が二部屋以上の上に載ってしまうのを気にして、シンディがぼやいた。
「手帳はだいたいみんなこういう大きさだよ、仕方ないだろ。二階にあるのはねじ巻き部屋。これは、真下の部屋と繋がっているみたいだ」
「残った三階には、遊戯室とダンスホールがあったね。遊戯室にいたホーキガミの話からすると、C字の上が北で、下が南になるのかな」
一応、「異世界の常識」を繰って方角の概念が俺達のものと同じかを確認した。こちらの世界でも、日が昇るほうが東で日が沈むほうが西、北の反対は南で合っているようだ。
「ところでライナー君。君、アトリエでアンのリボンの話をしてたけど、ダンスホールでどんな話をしてたの?」
うっかりしていて、ダンスホールでの会話はまだ互いに情報共有していなかった。
「まず、リボンの話だろ。それから、ホールの中央に置かれた楽器が「ビブロナルパ」って名前だって教えてもらった。あと、ロイドはアンの弟で、アンはダンスホールにいた誰よりも先に作られたってことも聞いたな」
「ちょっと待って、それ本当?」
シンディが身を乗り出す。
「おかしいよ、それ。私が聞いた話では、ロイドはダンスホールの人形の中でも最後に、アンと同じ設計図から作られたらしいんだもの」
「ん? 別に矛盾はしてないじゃないか」
「矛盾こそしてないけど、アンとロイドの作られた時期に大きな開きがあるってことは、アンは長らくひとりぼっちだった、ってことになっちゃうじゃない」
アンの人懐っこい笑顔を思い出す。確かに、彼女が長期間パートナーなしで平気だとは思えなかった。すぐに寂しいと言い出しそうな気がする。
けれどもその想像は、もう一組の三階の住人達を思い出した瞬間、ぐにゃりと歪んだ。
「でも、遊戯室の方でもそうだったじゃないか。四人いないとできないゲームをしてたのに、最低でも九年以上、四人目となるホーキガミはいなかった……」
それを聞くと、シンディは飛び上がるように肩を震わせた。
「……分かった。アンもチャガマ達も別に、ずっと「ひとり足りない」状況じゃなかっただけだ」
シンディは確信に満ちた瞳で、重々しくそう言った。さっきとは完全に真逆のことを言いだしたのはともかく、急に表情が沈んだのが気になる。
「どういうことだ?」
「これは自分で考えてほしい。もし私の考えが間違ってるんなら、できればその方がいいし」
問うたものの、突き放されてしまった。シンディから聞き出すことは不可能そうだと判断して、自分で考えることにする。
アンには長いことパートナーのロイドがいなかった。チャガマ、カラカサ、チョーチンは、九年以上四人で遊ぶゲームができない環境下にいた。この二つを結ぶ共通点は、さっきシンディが言った「ひとり足りない」だ。この状況を解消するためには当然、もうひとりいればいい。
では、「ひとり足りない」を解消する「もうひとり」とは?
俺は、自分が座った一脚の椅子を思い出す。あれ一脚しかなかったことからも、あれが四人目のために用意されたと考えて良さそうな気がする。つまり、四人目は椅子に座れる大きさ・かたち――おそらく人型だ――をしている。けれども、器物の姿をした人形の中にひとりだけ人型をした者がいる、というのはなんだかおかしい。
それが、人型でしか存在できない、人間でもない限りは。
「そうか! アンと踊っていたのも、チャガマ達とゲームをしていたのも、城主だったのか!」
俺がひらめきを口にすると、シンディは一回だけ首を縦に振った。
「けど、一体どうして、城主は今更ロイドやホーキガミを作ったんだ?」
「……それはきっと、ずっと人形とだけ過ごしてきた城主が、今更人間を招いたのとも関係してるんじゃないかな」
俺が自問自答を始めてしまうと、シンディは遠慮がちに助け舟を出した。
「今更俺達を招いた理由? 寂しくなったのかと思っていたんだが」
「相手は長いこと人間を寄せ付けなかった城の主だよ。今更急に人間を呼び寄せるほど寂しくなるかな? しかも、せっかく呼んでおいて、直接会おうとはしない。寂しがっている人のすることとしてはあまりにも不自然だ」
「うっ、確かにそうだな」
「けどまあ、考え方はそこまで間違ってないよ」
シンディはそう励ましてくれた。まあ、シンディのことだから、本気でそこまで間違っていないとも思っているのだろうけど。
城主は何らかの目的を持って、人間を城に呼び寄せた。そして、ロイドとホーキガミを創った。この二つに共通するのは、「ひとり増やす」こと、と言えるかもしれない。
ひとり増やすことそのものは、特に理由なく行われることもあるだろう。だが、いくつかのバラバラの事柄に対して「ひとり増やす」ことを行おうとするのなら、そこには共通した理由があってもよさそうだ。
……例えば、「ひとり足りなく」なるから、とか。
その考えに行き着いた瞬間、ぞくり、と何かが背筋を這い上がる感覚を覚えた。昔「ウミガメのスープ」の正解に行き着いた時と、同じ感覚だ。これに違いないという確信と、答えに対する底知れない恐れ。
「もしかして、城主は……死んでいる?」
恐る恐る尋ねる。
「おそらくね」
シンディの短い答えで、俺には十分だった。
食べ物が一つもないキッチン、無人でねじを巻ける部屋の存在、「ひとり足りな」かった存在の補充……どれも城主が不在だと考えることで得心がいく。コッペリアが左利きなのも、自分の代わりに人形のメンテナンスをさせるためだったのではないか。
それ以上何と言ったものか分からず、俺とシンディは黙り込んでしまった。ピアノの音に彩られたオランピアの歌声が、部屋いっぱいに響き渡る。
朝日を浴びて私は眠る
銀のとびらを背にすれば きっと私が見通せる
会いたくなったら 上って下りて
金のとびらの向こうには 更に向こうには何もない
会いたくなったら 下りて下りて
他の曲を弾いた時にはただラララとしか歌わなかったオランピアだが、この曲だけは歌詞を付けて歌っている。それも、だいぶ変てこな歌詞を。
「ねえライナー君。もし城主が死んでいるとしたら、私達はここから出るために、何をすればいいと思う?」
しばらくの後、シンディが口を開いた。
「決まってるさ。城主を探すんだ」
「でも、城主はもうこの城にいないんだよ?」
「城主はいなくなる準備をしていた。きっとこの謎も、自分が死んだ後に解き明かさせるつもりだったはずだ」
城主を「見つける」ことで脱出できるのではなく、録音で言っていた通り「探す」ことで脱出できると考えれば、何ら問題はない。問題は城主を探す方法だが、それはもうシンディが見つけてくれた。
「なあシンディ、この歌における「私」って、誰だと思う?」
「へっ? 何を急に聞いてるの」
「俺は、城主自身だと思う。城主が作った「録音」と全く同じ声だからな」
「それは、この歌の歌詞こそが城主を探すヒントってこと?」
俺は、一度だけ首を縦に振った。
[17年09月30日 14:26]
[332146]黒井由紀
歌詞を解読した末、俺達は二階の南廊下の突き当りの部屋にいた。
朝日を浴びられるのは、東側、それも遮蔽物の存在しない場所に限られる。だが、窓の外はどこも鬱蒼と木々が迫っていて、朝日どころではないと断言できる。
ただ一か所、偽物の景色が貼られた窓の外以外は。
また、「銀の扉」をキッチン、「金の扉」をダンスホールのドアだと考えると、「見通せる」先も「向こう」の「更に向こう」も、南廊下の突き当りの更に先となる。ダンスホールの扉の向こうの更に向こうは言わずもがなだし、キッチンの扉を背にすると、曲がり角の大鏡の反射によって、南廊下の突き当りの部屋が見えるからだ。
ただし、一階の南廊下の突き当りの部屋にある窓は偽物だし、三階の南廊下にあるダンスホールには窓がない。つまり、城主の元へ行き着く手段があるとすれば、二階だ。
果たしてその推理は当たっており、俺達の行き着いた部屋では、人ひとりなんとか通れそうな窓の向こうに、広々とした芝生が広がっていた。この世界に来てから初めて見る、強い陽の光に照らされている。
「ここだ!」
窓のすぐ下を覗き込んだシンディが叫んだ。俺も同様に覗き込むと、一階の壁から一フィートと離れていない場所に大きな石が置かれていた。
羽目殺しに見えた窓は、少し力を入れると横にずれ、俺達を通した。壁に取り付けられた梯子を辿って、地面に降り立つ。
地面に置かれた石には、ペトロ・ホロロージという名前だけが彫られていた。その上に載っていた封筒を開き、シンディにも聞こえるよう声に出して読む。
何者かは知らないが、ここに辿り着いた君へ
よくぞ私を見つけ出した。正直に言って、もしこれを読んでいる者がいるなら、本当に意外だ。何せ、これを書くまでの間、見つけてほしい思いと見つけてほしくない思いはずっと釣り合っていたので、かなり細かい手がかりしか残さなかったり、わざと謎を意地悪にしたりもしたから。
それでも私を見つけた君に、頼みがある。この城と、ここに住む人形達を守ってほしい。
本当はいつまでも私が彼らを守りたかったが、人間には寿命がある。私がいなくなった後も彼らが何不自由なく暮らせるよう、かなり心を砕いたつもりではあるが、それでも対外的な庇護者がいないというのは不安だ。
人形達が日々をつつがなく過ごすために必要なことは、すべて教えてあるし与えてあるから、君はこの城の主であると外に示し続けてさえくれればそれでいい。
具体的には、この城を相続し、売らずに所有し続けてほしいのだ。そのために必要なだけの財産は残しておいたから、好きに使ってくれて構わない。私の全財産を譲ると書いた遺言状を同封しておいた。
そして、自身の命が尽きそうだと思ったら、手段は問わないから、次の城主を探して、同じように人形の庇護を託してほしい。
私の愛した人形達が、これからもすこやかに時を重ねられることだけを願っている。
Petro Horologe
人嫌いの城主らしい、すこぶる自己中心的な手紙だった。それでも人形達に対する愛情だけは、過激なまでに真実だったと分かる。
「すごい手紙だね」
「ああ。とんでもない内容だった」
シンディと二人で頷きあう。もし一人だったら、しばらく呆然として手紙から目が離せなかったに違いない。
「それで、この手紙の願い、どうする?」
そう、それが最後の問題だ。
[17年09月30日 14:24]
歌詞を解読した末、俺達は二階の南廊下の突き当りの部屋にいた。
朝日を浴びられるのは、東側、それも遮蔽物の存在しない場所に限られる。だが、窓の外はどこも鬱蒼と木々が迫っていて、朝日どころではないと断言できる。
ただ一か所、偽物の景色が貼られた窓の外以外は。
また、「銀の扉」をキッチン、「金の扉」をダンスホールのドアだと考えると、「見通せる」先も「向こう」の「更に向こう」も、南廊下の突き当りの更に先となる。ダンスホールの扉の向こうの更に向こうは言わずもがなだし、キッチンの扉を背にすると、曲がり角の大鏡の反射によって、南廊下の突き当りの部屋が見えるからだ。
ただし、一階の南廊下の突き当りの部屋にある窓は偽物だし、三階の南廊下にあるダンスホールには窓がない。つまり、城主の元へ行き着く手段があるとすれば、二階だ。
果たしてその推理は当たっており、俺達の行き着いた部屋では、人ひとりなんとか通れそうな窓の向こうに、広々とした芝生が広がっていた。この世界に来てから初めて見る、強い陽の光に照らされている。
「ここだ!」
窓のすぐ下を覗き込んだシンディが叫んだ。俺も同様に覗き込むと、一階の壁から一フィートと離れていない場所に大きな石が置かれていた。
羽目殺しに見えた窓は、少し力を入れると横にずれ、俺達を通した。壁に取り付けられた梯子を辿って、地面に降り立つ。
地面に置かれた石には、ペトロ・ホロロージという名前だけが彫られていた。その上に載っていた封筒を開き、シンディにも聞こえるよう声に出して読む。
何者かは知らないが、ここに辿り着いた君へ
よくぞ私を見つけ出した。正直に言って、もしこれを読んでいる者がいるなら、本当に意外だ。何せ、これを書くまでの間、見つけてほしい思いと見つけてほしくない思いはずっと釣り合っていたので、かなり細かい手がかりしか残さなかったり、わざと謎を意地悪にしたりもしたから。
それでも私を見つけた君に、頼みがある。この城と、ここに住む人形達を守ってほしい。
本当はいつまでも私が彼らを守りたかったが、人間には寿命がある。私がいなくなった後も彼らが何不自由なく暮らせるよう、かなり心を砕いたつもりではあるが、それでも対外的な庇護者がいないというのは不安だ。
人形達が日々をつつがなく過ごすために必要なことは、すべて教えてあるし与えてあるから、君はこの城の主であると外に示し続けてさえくれればそれでいい。
具体的には、この城を相続し、売らずに所有し続けてほしいのだ。そのために必要なだけの財産は残しておいたから、好きに使ってくれて構わない。私の全財産を譲ると書いた遺言状を同封しておいた。
そして、自身の命が尽きそうだと思ったら、手段は問わないから、次の城主を探して、同じように人形の庇護を託してほしい。
私の愛した人形達が、これからもすこやかに時を重ねられることだけを願っている。
Petro Horologe
人嫌いの城主らしい、すこぶる自己中心的な手紙だった。それでも人形達に対する愛情だけは、過激なまでに真実だったと分かる。
「すごい手紙だね」
「ああ。とんでもない内容だった」
シンディと二人で頷きあう。もし一人だったら、しばらく呆然として手紙から目が離せなかったに違いない。
「それで、この手紙の願い、どうする?」
そう、それが最後の問題だ。
[17年09月30日 14:24]
[332145]黒井由紀
「ねえライナー君。城内に戻ったあと、何をしてたの?」
城から「異世界のラテシン」へ戻る最中、シンディが尋ねてきた。手紙を読んだ後、俺は一人で城内に戻り、手紙の願いに一応の決着を付けてきたのだ。
「ああ。コッペリアさんに遺言状を渡して、戸籍の作り方を教えてきたんだ。これからは数十年に一度交代で、人間のふりをして城の所有者として振る舞うように、って」
異邦人である俺には、彼ら人形達が人の手を借りずにこれまで通りの生活を続けられるように、必要なことを教えることしかできない。そう思った末の結論だ。
「……それって大丈夫なの?」
シンディがいぶかしげにこちらを見る。確かに、遺言状の頼みには全く沿っていないが、そんな目をしなくてもいいと思う。
「多分な。なんせ、あの城主が本当にすべてを遺したかったのは、あの人形達なんだから」
「それはそうだけど」
シンディの視線は、まだ渋いままだ。俺は仕方なく、切り札を切る。
「一ついいことを教えてやろう。手紙と同封されていた遺言状で、全財産として挙げられていたものの中に、人形は存在しなかったんだ」
「えっ?」
「城主からしてみれば、彼らは物ではなかったってことかな。あるいは、人形達の存在を、人間には知られたくなかったか」
俺が答えると、シンディはしばらく押し黙って考えた。が、手がかりが少なすぎたのか、すぐに音を上げた。
「ライナー君。その回りくどい言い方、悪い癖だよ」
「君と一緒にいたら、癖が移ってしまったみたいだな」
ちょっとからかうと、シンディは唇をへの字に曲げた。
「遺言状にあった全財産……つまり、人形を除いた所持金、城、森など……から計算すると、何も売らずに、所持金を減らすだけで相続税を払いきることができる。だが、遺産に人形達を加えると、相続人は赤字になってしまうんだ」
「それってつまり、人形の存在は役所に隠して相続しろ、って、そういうこと?」
俺は無言で頷いた。
「そうだ。きっと城主は、人形達の存在が人間の知るところになることを、ひどく恐れたんだろう。彼にとっては大切な子供でも、他の人間からしてみれば、魅力的なオーバーテクノロジーの産物でしかないから」
自律思考・行動が可能な人型の機械の存在が明るみに出たら外の世界がどんな騒ぎになるかは、俺にだって容易に想像がつく。そして、それは決して、ここに住む人形達にとって望ましい結果は生まないだろうことも。
「なるほどね。人形を売って相続税を捻出する手もなくはないけど、そんなことしたらあのロボットとゴーレムが黙ってなさそうだし。そこまでガチガチに彼らを守る術を編んでいるのなら、確かによその世界の人間である私達にできるのは、彼ら自身に遺産を相続させることくらいかもね」
「まあ、釈然としない気持ちがないわけでもないが」
俺がこぼすと、シンディは言った。
「……当然と言えば当然の帰結だと思うよ。誰も永遠に彼らの面倒を見切れる訳じゃない以上、いずれは彼ら自身が、世界とどう関わるのか、あるいは関わらないのか決めなきゃならないだろうし。自分で考える頭を授けられたんだから、きっとうまくやるさ」
「だといいな」
陽の差さない森の地面を踏みしめながら、俺達は不完全な永遠の城を後にした。
【おわり】
[17年09月30日 14:24]
「ねえライナー君。城内に戻ったあと、何をしてたの?」
城から「異世界のラテシン」へ戻る最中、シンディが尋ねてきた。手紙を読んだ後、俺は一人で城内に戻り、手紙の願いに一応の決着を付けてきたのだ。
「ああ。コッペリアさんに遺言状を渡して、戸籍の作り方を教えてきたんだ。これからは数十年に一度交代で、人間のふりをして城の所有者として振る舞うように、って」
異邦人である俺には、彼ら人形達が人の手を借りずにこれまで通りの生活を続けられるように、必要なことを教えることしかできない。そう思った末の結論だ。
「……それって大丈夫なの?」
シンディがいぶかしげにこちらを見る。確かに、遺言状の頼みには全く沿っていないが、そんな目をしなくてもいいと思う。
「多分な。なんせ、あの城主が本当にすべてを遺したかったのは、あの人形達なんだから」
「それはそうだけど」
シンディの視線は、まだ渋いままだ。俺は仕方なく、切り札を切る。
「一ついいことを教えてやろう。手紙と同封されていた遺言状で、全財産として挙げられていたものの中に、人形は存在しなかったんだ」
「えっ?」
「城主からしてみれば、彼らは物ではなかったってことかな。あるいは、人形達の存在を、人間には知られたくなかったか」
俺が答えると、シンディはしばらく押し黙って考えた。が、手がかりが少なすぎたのか、すぐに音を上げた。
「ライナー君。その回りくどい言い方、悪い癖だよ」
「君と一緒にいたら、癖が移ってしまったみたいだな」
ちょっとからかうと、シンディは唇をへの字に曲げた。
「遺言状にあった全財産……つまり、人形を除いた所持金、城、森など……から計算すると、何も売らずに、所持金を減らすだけで相続税を払いきることができる。だが、遺産に人形達を加えると、相続人は赤字になってしまうんだ」
「それってつまり、人形の存在は役所に隠して相続しろ、って、そういうこと?」
俺は無言で頷いた。
「そうだ。きっと城主は、人形達の存在が人間の知るところになることを、ひどく恐れたんだろう。彼にとっては大切な子供でも、他の人間からしてみれば、魅力的なオーバーテクノロジーの産物でしかないから」
自律思考・行動が可能な人型の機械の存在が明るみに出たら外の世界がどんな騒ぎになるかは、俺にだって容易に想像がつく。そして、それは決して、ここに住む人形達にとって望ましい結果は生まないだろうことも。
「なるほどね。人形を売って相続税を捻出する手もなくはないけど、そんなことしたらあのロボットとゴーレムが黙ってなさそうだし。そこまでガチガチに彼らを守る術を編んでいるのなら、確かによその世界の人間である私達にできるのは、彼ら自身に遺産を相続させることくらいかもね」
「まあ、釈然としない気持ちがないわけでもないが」
俺がこぼすと、シンディは言った。
「……当然と言えば当然の帰結だと思うよ。誰も永遠に彼らの面倒を見切れる訳じゃない以上、いずれは彼ら自身が、世界とどう関わるのか、あるいは関わらないのか決めなきゃならないだろうし。自分で考える頭を授けられたんだから、きっとうまくやるさ」
「だといいな」
陽の差さない森の地面を踏みしめながら、俺達は不完全な永遠の城を後にした。
【おわり】
[17年09月30日 14:24]
[332143]黒井由紀
年齢不詳・性別不詳・正体不明の「案内人」シンディに付いていくと、白い壁を持つ巨大な建物が目の前に現れた。
「どういうことだ?」
こんなに大きな建物だというのに、さっきまでその姿の一部さえ見えなかった。しかも、シンディが歩いたのは、俺が館を求めて堂々巡りしていた道だったはずだ。
「ここが館「ラテシン」。君の目的地だよ」
シンディは、俺の問いを無視してそう言うと、入り口目指してさっさと歩き始めた。「ラテシン」は、個人が住むにはあまりにも大きく、装飾も華美ではないため、館というよりも城という方がしっくりくる。石造りかと思いきや時折煉瓦の壁が混ざっていたり、ロマネスク様式の棟とバロック様式の棟が隣りあっていたりして、遥か昔に建てられて以来ずっと増改築を繰り返してきた、という雰囲気だ。
行き先は告げず、俺がちゃんと付いてきているかだけを確認しながら、シンディは館のドアを開け、玄関ホールそばのエレベーターに乗り込んだ。ボタンを押して早々にエレベーター内に設置された椅子に陣取っても、口を開こうとせず不敵に笑うばかり。座り心地の良さそうな椅子、2人で乗ると寂しく感じるほどの広さ、電球の光を映して輝く金色の柱と大理石の床、といういかにも豪奢な屋敷らしい内装と相まって、シンディの無言は俺を緊張感させた。
最上階に出て、廊下の突き当たりの重厚なドアを開けると、シンディはようやく一言
「どうぞ」
と俺を促した。部屋の中では、山高帽を被った男がテーブルに載ったスープ皿を前に佇んでいたが、俺の目はもっと別なものに引き付けられていた。男の背後にある窓の外には、あるはずのない大海原が広がっていた。
……アルカーノは、海に面していないんじゃなかったのか。
あまりの光景に、俺は挨拶も忘れて固まった。
「やあ。ライナー・テンニース君だね。ようこそラテシンへ。私はこの館の主。皆にはスープの男と呼ばれている」
スープの男が帽子を持ち上げてそう言ったので、俺も慌てて挨拶を返す。
「ライナー・テンニースです。この度は先せ……、私が働いている探偵事務所の所長から貰った手紙に同封されていた地図を頼りにここへ来ました。着いた後のことは先方に尋ねろと言われていますので、どうぞよろしくお願いします」
先生からの手紙を見せるべくテーブルの方に進みでると、大海原の上に、都市が現れた。煉瓦の建物が立ち並ぶそれを見つけてようやく、俺の目は真実を捉えた。この部屋の大きな窓の下半分は、青い板を後ろに貼った巨大な水槽になっており、それが街並みを覆い隠すことで海に見えていたのだ。
「見事ですね、その水槽」
「でしょう。ここに来た人は皆びっくりしていくんだから」
スープの男に手紙を渡しながらそう言うと、シンディが誇らしげに応えた。スープの男はもう手紙を読むのに集中していて、話を続けられなさそうな雰囲気だ。スープの男が手紙を読み終わるのを待ちがてら、シンディに話しかける。
「もしかして、俺が館を見つけられなかったのも何かのトリックだったのか?」
館に入るためにクイズみたいな試練を課したり、主の部屋に他人の目を欺くトリックを仕掛けたりする連中のすることだ、館自体にも何らかの仕掛けを施しているという推論は自然だろう。
ところが、シンディは首を横に振った。
「ううん。それはスープの男の力だよ」
「スープの男の力? そりゃまた大ざっぱだな」
「だって私も詳しくは知らないもの。魔法、超能力、異能、不老不死、霊、妖怪、魔物、幻獣、異星人、異常発達した科学……この世界には存在しなかったり、この世界の現在の科学では説明不能だったりするもろもろのどれかだとは思うけど」
「今度は随分と持って回った言い方だな」
「正確を期したまでだよ。まあ、面倒臭いから全部まとめて「非現実要素」って呼ぶ人もいるけど」
「その言い方でいいじゃないか」
「でも、世界や時間、人によっても非現実のラインは違うし……」
シンディが言葉に詰まった辺りで、スープの男が手紙を読み終えたらしく口を開いた。
「シンディ、この手紙の差出人を知っているかい?」
手紙を受け取ったシンディは手紙を素早く黙読すると、かぶりを振った。
「少なくとも、ここに書かれている名前に心当たりはありません。ラテシンのコレクターにも、テストに落ちた人にも、同じ名前の人はいなかったはずです」
「そうか。でも、私の知り合いでもないんだよ。妙だね」
「それは不思議ですね」
スープの男がぽつりと言うと、シンディが頷いた。てっきり先生は向こうに話を通しているとばかり思っていたから、俺も驚いた。が、ただ驚いている場合ではない。彼らが先生のことを知らないとなると、俺の立場は途端にあやふやになってしまう。急いでフォローしなければならなかったが、俺自身も先生についてそう多くのことを知らなかったことに気づかされるばかりで、口からは何も出てこない。
「何が妙なんです?」
自分の驚きはおくびにも出さずに尋ねた。俺と彼らでは、考えが違う可能性もある。
シンディが、先に口を開いた。
「まず、この差出人、ライナーの推薦者はなぜこんなにラテシンについて詳しいのかっていうこと。こんなにハッキリとした地図は、かなりラテシンに通じてないと書けないよ。それなのに、推薦者はコレクター……館ラテシンの関係者でも、それを志した人物でもない」
「そして、ラテシンの関係者でない推薦者がラテシンについて知ったのなら、何故自ら来ずに君を来させたのか。探偵事務所の所長、などという謎に目のない職業なら、まずは自分で来るはずだ。自分でテストを受けもせず、いきなり君をここに連れてくるというのは、どこか違和感がある」
スープの男の断定は、俺には奇妙に感じられた。
「あの、どうして謎に目のない職業なら、自分でラテシンに来たがると思うんですか?」
「えっ、ライナー君、それ聞いちゃう?」
シンディが、いかにも不思議そうに首を傾げた。
「悪いが、俺はその紙に書かれていることしか、ラテシンについて知らないんだ」
「こんな曖昧な情報しか書かれてない手紙でここまで来たのか。君、トラブル体質の素質あるよ」
シンディが茶化したが、俺だってそんなに迂闊ではない。他ならぬ先生からの手紙だから、ここまで来たし、どうにかここにいられるようにしたいのだ。まあ、そうしてみたらこのザマだから、あまり声高に言える訳でもないが。
「ラテシンは、古今東西どんな世界かも問わず、全ての謎を収集する館である。謎好きならば、一度は訪れてみたいだろう、と私は考えている」
スープの男は、おもむろにそう言った。彼が話すと、妙な説得力がある。
「そんな場所だったのか、ここは」
「そんな場所だったんだよ、ここは。ね、おかしいでしょ?」
「いやでも、偽名の可能性もあるだろう? それならおかしくはないはずだ」
「ふうん。つまり、ライナー君の先生は、君に対してずっと偽名を使っていたと」
「うっ。それは……考えたくないな」
「どっちにしても怪しいことに変わりはないしね」
シンディの表情が、険しくなった。これは、まずいかもしれない。
「…………ライナー君、申し訳ないんだけど、君をここのコレクターにすることはできな」
「それはダメだよ」
万事休すかと思った瞬間、シンディの言葉をスープの男が遮った。
「シンディ、君がテストをして、ライナー君はコレクターにふさわしいと判断したんだろう? ならどんなに怪しくても、それを拒絶するのは良くないよ。いつも君が言っているじゃないか、先入観は」
「真実から君を遠ざける。……確かにそうですが……チャーリーのようなコレクターが増えるれば、好ましくない事態が多々起こると思います」
「好ましくない事態のことは、それが起きた時に考えればいい。それもまた謎の一つの形なのだから」
「ぐっ……」
俺相手だとあんなに不敵で饒舌だったシンディが、言い淀んだ。鷹揚に見せかけて、スープの男は侮れない。
「それに、今いい役職が空いているのは、君も知っているだろう」
「あっ! それは、確かにそうですね。彼の前職を考えても、適任であると言わざるを得ません……」
俺には話が飲み込めなかったが、どうにか置いてもらえることにはなったらしい。シンディは頷くと、俺の肩に手を置いて、こう言った。
「よし、ライナー君。君は今日から、探偵事務所所長だ」
「……へ?」
こうして俺のラテシン生活は始まった。
[17年09月30日 14:19]
年齢不詳・性別不詳・正体不明の「案内人」シンディに付いていくと、白い壁を持つ巨大な建物が目の前に現れた。
「どういうことだ?」
こんなに大きな建物だというのに、さっきまでその姿の一部さえ見えなかった。しかも、シンディが歩いたのは、俺が館を求めて堂々巡りしていた道だったはずだ。
「ここが館「ラテシン」。君の目的地だよ」
シンディは、俺の問いを無視してそう言うと、入り口目指してさっさと歩き始めた。「ラテシン」は、個人が住むにはあまりにも大きく、装飾も華美ではないため、館というよりも城という方がしっくりくる。石造りかと思いきや時折煉瓦の壁が混ざっていたり、ロマネスク様式の棟とバロック様式の棟が隣りあっていたりして、遥か昔に建てられて以来ずっと増改築を繰り返してきた、という雰囲気だ。
行き先は告げず、俺がちゃんと付いてきているかだけを確認しながら、シンディは館のドアを開け、玄関ホールそばのエレベーターに乗り込んだ。ボタンを押して早々にエレベーター内に設置された椅子に陣取っても、口を開こうとせず不敵に笑うばかり。座り心地の良さそうな椅子、2人で乗ると寂しく感じるほどの広さ、電球の光を映して輝く金色の柱と大理石の床、といういかにも豪奢な屋敷らしい内装と相まって、シンディの無言は俺を緊張感させた。
最上階に出て、廊下の突き当たりの重厚なドアを開けると、シンディはようやく一言
「どうぞ」
と俺を促した。部屋の中では、山高帽を被った男がテーブルに載ったスープ皿を前に佇んでいたが、俺の目はもっと別なものに引き付けられていた。男の背後にある窓の外には、あるはずのない大海原が広がっていた。
……アルカーノは、海に面していないんじゃなかったのか。
あまりの光景に、俺は挨拶も忘れて固まった。
「やあ。ライナー・テンニース君だね。ようこそラテシンへ。私はこの館の主。皆にはスープの男と呼ばれている」
スープの男が帽子を持ち上げてそう言ったので、俺も慌てて挨拶を返す。
「ライナー・テンニースです。この度は先せ……、私が働いている探偵事務所の所長から貰った手紙に同封されていた地図を頼りにここへ来ました。着いた後のことは先方に尋ねろと言われていますので、どうぞよろしくお願いします」
先生からの手紙を見せるべくテーブルの方に進みでると、大海原の上に、都市が現れた。煉瓦の建物が立ち並ぶそれを見つけてようやく、俺の目は真実を捉えた。この部屋の大きな窓の下半分は、青い板を後ろに貼った巨大な水槽になっており、それが街並みを覆い隠すことで海に見えていたのだ。
「見事ですね、その水槽」
「でしょう。ここに来た人は皆びっくりしていくんだから」
スープの男に手紙を渡しながらそう言うと、シンディが誇らしげに応えた。スープの男はもう手紙を読むのに集中していて、話を続けられなさそうな雰囲気だ。スープの男が手紙を読み終わるのを待ちがてら、シンディに話しかける。
「もしかして、俺が館を見つけられなかったのも何かのトリックだったのか?」
館に入るためにクイズみたいな試練を課したり、主の部屋に他人の目を欺くトリックを仕掛けたりする連中のすることだ、館自体にも何らかの仕掛けを施しているという推論は自然だろう。
ところが、シンディは首を横に振った。
「ううん。それはスープの男の力だよ」
「スープの男の力? そりゃまた大ざっぱだな」
「だって私も詳しくは知らないもの。魔法、超能力、異能、不老不死、霊、妖怪、魔物、幻獣、異星人、異常発達した科学……この世界には存在しなかったり、この世界の現在の科学では説明不能だったりするもろもろのどれかだとは思うけど」
「今度は随分と持って回った言い方だな」
「正確を期したまでだよ。まあ、面倒臭いから全部まとめて「非現実要素」って呼ぶ人もいるけど」
「その言い方でいいじゃないか」
「でも、世界や時間、人によっても非現実のラインは違うし……」
シンディが言葉に詰まった辺りで、スープの男が手紙を読み終えたらしく口を開いた。
「シンディ、この手紙の差出人を知っているかい?」
手紙を受け取ったシンディは手紙を素早く黙読すると、かぶりを振った。
「少なくとも、ここに書かれている名前に心当たりはありません。ラテシンのコレクターにも、テストに落ちた人にも、同じ名前の人はいなかったはずです」
「そうか。でも、私の知り合いでもないんだよ。妙だね」
「それは不思議ですね」
スープの男がぽつりと言うと、シンディが頷いた。てっきり先生は向こうに話を通しているとばかり思っていたから、俺も驚いた。が、ただ驚いている場合ではない。彼らが先生のことを知らないとなると、俺の立場は途端にあやふやになってしまう。急いでフォローしなければならなかったが、俺自身も先生についてそう多くのことを知らなかったことに気づかされるばかりで、口からは何も出てこない。
「何が妙なんです?」
自分の驚きはおくびにも出さずに尋ねた。俺と彼らでは、考えが違う可能性もある。
シンディが、先に口を開いた。
「まず、この差出人、ライナーの推薦者はなぜこんなにラテシンについて詳しいのかっていうこと。こんなにハッキリとした地図は、かなりラテシンに通じてないと書けないよ。それなのに、推薦者はコレクター……館ラテシンの関係者でも、それを志した人物でもない」
「そして、ラテシンの関係者でない推薦者がラテシンについて知ったのなら、何故自ら来ずに君を来させたのか。探偵事務所の所長、などという謎に目のない職業なら、まずは自分で来るはずだ。自分でテストを受けもせず、いきなり君をここに連れてくるというのは、どこか違和感がある」
スープの男の断定は、俺には奇妙に感じられた。
「あの、どうして謎に目のない職業なら、自分でラテシンに来たがると思うんですか?」
「えっ、ライナー君、それ聞いちゃう?」
シンディが、いかにも不思議そうに首を傾げた。
「悪いが、俺はその紙に書かれていることしか、ラテシンについて知らないんだ」
「こんな曖昧な情報しか書かれてない手紙でここまで来たのか。君、トラブル体質の素質あるよ」
シンディが茶化したが、俺だってそんなに迂闊ではない。他ならぬ先生からの手紙だから、ここまで来たし、どうにかここにいられるようにしたいのだ。まあ、そうしてみたらこのザマだから、あまり声高に言える訳でもないが。
「ラテシンは、古今東西どんな世界かも問わず、全ての謎を収集する館である。謎好きならば、一度は訪れてみたいだろう、と私は考えている」
スープの男は、おもむろにそう言った。彼が話すと、妙な説得力がある。
「そんな場所だったのか、ここは」
「そんな場所だったんだよ、ここは。ね、おかしいでしょ?」
「いやでも、偽名の可能性もあるだろう? それならおかしくはないはずだ」
「ふうん。つまり、ライナー君の先生は、君に対してずっと偽名を使っていたと」
「うっ。それは……考えたくないな」
「どっちにしても怪しいことに変わりはないしね」
シンディの表情が、険しくなった。これは、まずいかもしれない。
「…………ライナー君、申し訳ないんだけど、君をここのコレクターにすることはできな」
「それはダメだよ」
万事休すかと思った瞬間、シンディの言葉をスープの男が遮った。
「シンディ、君がテストをして、ライナー君はコレクターにふさわしいと判断したんだろう? ならどんなに怪しくても、それを拒絶するのは良くないよ。いつも君が言っているじゃないか、先入観は」
「真実から君を遠ざける。……確かにそうですが……チャーリーのようなコレクターが増えるれば、好ましくない事態が多々起こると思います」
「好ましくない事態のことは、それが起きた時に考えればいい。それもまた謎の一つの形なのだから」
「ぐっ……」
俺相手だとあんなに不敵で饒舌だったシンディが、言い淀んだ。鷹揚に見せかけて、スープの男は侮れない。
「それに、今いい役職が空いているのは、君も知っているだろう」
「あっ! それは、確かにそうですね。彼の前職を考えても、適任であると言わざるを得ません……」
俺には話が飲み込めなかったが、どうにか置いてもらえることにはなったらしい。シンディは頷くと、俺の肩に手を置いて、こう言った。
「よし、ライナー君。君は今日から、探偵事務所所長だ」
「……へ?」
こうして俺のラテシン生活は始まった。
[17年09月30日 14:19]
黒井由紀さんが入室しました。
ウミガメのスープを一つください。[17年09月30日 14:16]
ウミガメのスープを一つください。[17年09月30日 14:16]
最初最後